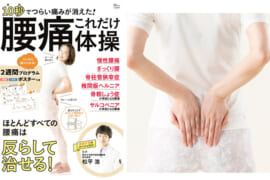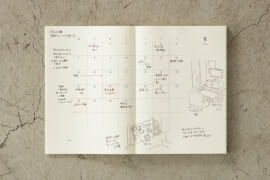仕事もある程度経験が積み重なってくると「マネジメント」や部下や後輩の育成を求められることも。いきなり「マネジメント」と言われても何をすればいいの? と戸惑う人も多いのではないでしょうか?
人材紹介、人材派遣会社向けに、業務効率化システムの開発・販売をしている「マッチングッド株式会社」でセールス・マーケティング部マネージャーをしている北村純さん(27)。20代でマネジメント業務を担当しています。
27歳でベンチャー企業でマネジメントなんて「卒業後のことも見据えて学生時代からガツガツと就活をしていたのかな」と思ってしまいますが、地元の大学の教育学部に通い「なんとなく公務員になるんだろうな」と思って過ごしていたと言います。
しかし、あることをきっかけに、まわりの学生が教員や公務員を目指す中、青年海外協力隊に応募して「外の世界」に飛び出し、帰国後は一般企業への就職を目指すことに。
「最近の若い世代は地元志向」「内向き」と言われることも多いですが、北村さんに「外の世界」に飛び出して見つけたこと、マネジメントのやりがいについて聞きました。
20代女子が「保守的」って本当?
——最初、ITベンチャーで20代ながら20代ながらマネジメント業務に携わってバリバリと働いている女性がいるよ、というので取材を……ということだったんですが、プロフィールを拝見して国立大学の教育学部出身で、青年海外協力隊に行って、現在はベンチャーで働いているということで、キャリアの築き方に興味が湧いたんです。
以前ウートピで「慶大、早大、青学卒の女性も「一般職」に殺到」という記事を掲載したら反響は大きかったのと、よくニュースでも「最近の20代は保守化している」「若いときから結婚も出産も計画して手堅い生き方をしている」と言われることもあるので。北村さんは同世代を見て、保守的だなと思うことはありますか?
北村純(以下、北村):私のまわりは、仕事をバリバリしている女子が多いので、正直「保守的」というのはピンとこないですね。
——20代っていっても10年あるわけですし、世代で括るのも雑かもしれないんですが、どんなタイプの女子が多いですか?
北村:そうですね、自立したいという思いで東京でバリバリ仕事をしてる友人は多いですね。私と同じように青年海外協力隊に行って、帰国してもまたすぐに海外に……という知り合いもいます。
——そうなんですね。北村さんは山口大学の教育学部のご出身なんですよね? 私のまわりにも教育学部出身の友人や知り合いが多いんですが、地元で小学校や中学の先生になるという人が多いので、「外に出た」きっかけを知りたいなと。
北村:実は、高校のときはあまり将来やりたいことも見つかってなかったんです。兄がいるんですけど、兄の進んだ高校と大学を同じようにたどって、学部も同じ。
兄はスポーツ系の研究職だったんですが、私は体育教員になるコースを専攻したという流れで「将来、絶対先生になりたい」という思いがあって大学を選択したわけではないんです。
「外に出てみた」理由
——青年海外協力隊に行こうと思ったのは何かきっかけがあったんですか?
北村:大学3年になって進路をそろそろ確定しなければと思っていたんですが、ピンとくるものがなかったんです。
で、ある日たまたまアフリカに行った方のお話を聞く機会があって、その方のお話を聞く中で、一度就職をする前に海外に飛び出してみようかなと思ったのがきっかけです。
——まわりは先生になる人や就職した人が多かったですか?
北村:7割くらいが先生になってます。あとは公務員かな。銀行員や警官が多いですね。
——就活はしなかったんですか?
北村:専攻していた学科は教員採用試験を受ける人がほとんどで、就職活動はまったくしていませんでした。ただ、このまま教員になるのは違うかな、という気持ちもあって……。
先ほど申し上げたアフリカに行った方のお話を聞く機会があったので、思い切って青年海外協力隊を受けたんです。
——「先生になるのは違うな」と思ったのはなぜ?
北村:何となくなんですが、アフリカに行ってからもより強く思ったことでもあるんですけど、学校という一つの環境に属してしまうと、なんとなくコミュニティが限定されてしまうのかなというイメージがあったんです。
教員免許を取得する際に教育実習を体験してとてもやりがいのある仕事だなと感じたのですが、2〜3週間という限られた時間だったからこそ楽しかったのかなと思える面があって。同じ場所で長く働くというのは私には合わないのかなと思ってしまったんです。
大学も地方の学校だったので、触れ合う人も同じような人が多い。「外に出たいな」というのは、大学の頃に強く思ってました。
——「外に出たい」という思いはあったんですね。でもいきなり青年海外協力隊でアフリカに行くことに抵抗はなかったんですか?
北村:「アフリカに行く」ということには抵抗はありませんでした。アフリカに行って実際に現地生活を送る中で、抵抗というより乗り越えなきゃいけない壁がいろいろあった、といった感じです。
文化も宗教観も使う言葉もまったく違うコミュニティの中に日本人はたった1人という状況だったので……。私が常識だと思ってたことが常識ではないという世界でした。
例えば、時間にすごくルーズで会議が朝10時からスタートするのに12時になっても誰も来ない……というのは普通、みたいな。そういうおおらかな部分が好きでもあったのですが……。
日本人の私としては信じられないんですが、あちらから言うと「人の失敗を許す」文化なので(笑)。日本人はどっちかというと「人に迷惑をかけない」というのが価値観として強いと思うんですが、それがまったく違うんだな、と。でも、そんな日本人とは違う面は好きでしたね。
——アフリカの南に位置するザンビアに行かれたんですね。ザンビアというのは自分で選べるんですか?
北村:希望国は出せるんですが、実務経験が3年必要だったりという条件があるんです。私の場合は、教員免許を持ってて、体育の中高と小学校の教員免許を持ってたので、それを条件に探していくとアフリカがすごく多かったんです。
私は「英語圏で英語を学びたいなー」とは思っていたので、一番(募集が)多かったザンビアにチェックしてそこに派遣されたという感じですね。
——ザンビアでは体育を教えていたんですか?
北村:はい。2年間、子どもに体育を教えていました。ただ、体育授業の実施がメインではありましたが「道徳みたいなことをしたい」と言えばやらせてもらえる環境ではあったので、そういったこともしてました。
現地で出会った日本人との出会いに刺激
——行ってみて変わったことは?
北村:まず、外国で2年間生活をしたというのが、すごく大きな出来事でしたね。自分の人や物事の見方が変わったというのももちろんそうなんですが、ザンビア人だけではなくて、現地で出会った日本人との出会いがすごく大きかったです。
それまでは、大学の教育学部を専攻していたので、まわりは先生になるような人が多かったんです。
アフリカに行って、いろいろなバックグラウンドを持って、かつ一般企業でキャリアをしっかり積まれている方と親しく話す機会が非常に多かったので、私も一般企業で日本人のキャリアを積んでみたいなと思ったのが、すごく大きかったかなと思います。
——その日本人というのは年上?
北村:はい。男女ともに30〜40歳くらいの方が多かったですね。シニア枠で60歳以上の方も派遣されていたので、そういった方達と話してて、こういう生き方もあるんだなとすごく刺激をもらいました。
「公務員になる」以外の生き方を知った
——それまでは「こういう生き方じゃないとダメ」というのはあったんですか?
北村:親が公務員で、特に「公務員になれ」とは言われてないんですが、「公務員として地元で働くのが、家族も近くにいるし良いんじゃないか」と、それとなく言われたことはありました。
確かにそうだと自分自身も思っていたので、漠然と将来は公務員になるのかな、という思いはありましたね。
——教育学部にいたら職業と密接しているから、あまり他の選択肢は考えられないですよね?
北村:はい。考える機会があまりないですね。
——ザンビアでの経験もあって、一般企業でキャリアを積もうと思ったんですね。
北村:そうですね。私がものを知らなかっただけかもしれないんですが、それまでは選択肢が公務員か教師かしかなかったので、お金まわりのことや経済の仕組みもなんとなくしか分からなかったんです。
だから、一般企業に就職したほうが、お金を稼ぐ仕組みや経済の仕組みも身をもって学べるのかなと思い、そういう側面から日本を知りたいと思ったんです。
アフリカに行ったからこそ、日本ってどういう国なんだろう? もっと知りたいという思いが強くなりましたね。
——なるほど。それが今の会社のキャリアにとつながっていくんですね。後編ではそのあたりのお話をお聞かせください。
※後編は12月14日(木)公開です。
(取材・文:ウートピ編集部・堀池沙知子、写真:宇高尚弘/HEADS)