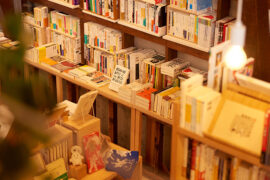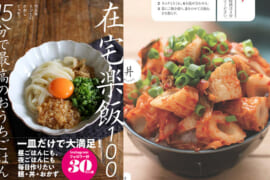会社で働きながら、家でもちゃんと稼げる副業をしたい。今の時代、そんな願いも夢ではありません。
23歳の時、日本と韓国でファッションECで起業し、現在はアパレル仕入れサービスや決済サービスを行っている株式会社BUYON代表の三浦由理(みうら・ゆり)さん。今年1月にウートピが主催したセミナー「【週末プチ起業】失敗しないためのファッションEC講座」より、初心者向けの始め方をご紹介します。
第2回となる今回は、スタートするのにオススメの時期と注意点ついて。
オープンするなら絶対に春〜初夏!
初めてのアパレルネットショップの開業。実は季節選びがスタートに影響するのだとか。
「たとえば、10月にオープンするとどうなるか。始めたばかりのサイトは、商品画像、サイトの完成度のレベルが低く、新人さんだと一目でわかるレベルのものになりがちです。さらに、顧客もいない。それなのに、冬物商品は仕入れの価格も高く、仕入れ値が高ければ必然と売り値も高くなる。売値が5000円以上になることもざらです。
正直、よく知らないショップ、ましてや素人っぽいショップで冬物を見ても手を出しにくいですよね。そうなると、お客様によさを知ってもらえないまま運転資金が足りなくなり2月頃にはサイトの閉鎖ということにもなりかねません」
だからこそ始めるなら春から初夏にかけてだと三浦さんは続けます。
「まず、春夏物は仕入れ値が安い分、売り値も安く設定できます。売り手も買い手も挑戦しやすいんです。冬のコートやロングブーツだと、ワンシーズンに1アイテム買うかどうかですが、夏物の衣類は何着か買う傾向がありますし。
初めて見たショップだけど、ワンピースが安くてかわいいから、買ってみる。買ってみたらいい商品だし、発送も丁寧で満足する。すると、秋冬物を出したときに、春夏物を買ってくれたお客様がリピーターになってくれる可能性があるんです。
そうなれば商品の単価が高くなる冬を無事に越すことができます。今すぐ(セミナーが開催された1月)秋冬物を仕入れてオープンするくらいだったら、この時期は準備に回して、春夏でショップをスタートさせたほうが絶対いいですよ」
なるほど。値段が高くなる秋冬の時期を見越して事前にうまく集客し、少しずつ顧客を増やしていくことが大事なんですね。
自社サイトか?モール出店か?
開店時期が決まったら、前回話したように販売方法を決めなければなりません。ネット販売の主流は、ネットオークション、フリマサイト、海外ソーシャル通販サイト、モール型サイト、SNS、自社サイトですが、三浦さんはこう言います。
「私が本気でオススメするのが自社サイト。まず、いろんなショップが集まるモール型サイトでノーブランド商品を扱うときにネックになるのは、検索にヒットしづらい点。ブランドならば『(ブランド名) きれいめ タイトスカート』というキーワードで調べると自分の出品商品にたどり着く可能性が高まるのですが、ノーブランドの場合は『きれいめ タイトスカート』で検索しても、多くの商品の中に埋もれてしまう」
検索のほかに課題になる点がもうひとつ。それは、お客様の情報(メールアドレス)を入手できないこと。
「モール型やフリマサイトでショップ運営をする場合に困るのが、過去の購入者のメールアドレスが取得できない点。たいていのモール型は、出店者にはお客様のメールアドレスがわからない仕組みになっています。だから自分の顧客が1000人いて、自社サイトに引っ越そうとしてもその1000人は連れていけません。だからと言って今まで努力して集めた顧客を手放すわけにもいかないから、その後もやむなく出店し続けることに」
モールによっては出店料に月額がかかる場合も。出店料や販売手数料の値上げがあっても、そこに顧客がいる限り簡単には止められないというリスクもあります。それでも集客力のあるモールに出店することで、たくさんの人に知ってもらいやすくなるメリットがあるのも事実。慎重に比較したいところです。
無料ショッピングカートの落とし穴
また、自社サイトを作る上で欠かせないのが、ショッピングカート選び。ネット通販ではおなじみの「ショッピングカート」ですが、出品できるアイテム数やクレジットカード払い対応の有無などの決済の範囲に違いがあり、使い勝手はカートによってピンキリなんだとか。
「無料で使えるショッピングカートもたくさんありますが、安さだけで決めるのはダメ。違うショッピングカートに乗り換えたいと思った時、お客様のクレジットカード情報や貯まったポイントを移行できないというデメリットがあるケースもあります。機能をチェックするために数ヵ月だけ無料のカートに登録してみるのはいいけれど、「タダだから」と安易に決めるのは後悔につながります」
出店型モールやショッピングカートなども膨大な選択肢の中で、自分に合うものを見つけるのは大変です。自分のゴールや目的を見据えた上で、どの販売方法が適切なのかを見極めないといけません。
次回は、ファッションECをサポートするために欠かせないSNSの使い方について説明します。
(薮田朋子)