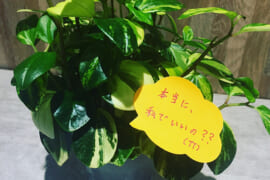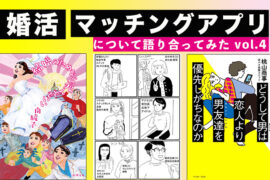今年7月、小池百合子氏が女性初の都知事に就任するなど、男性社会の中でめざましい活躍を遂げる女性が増えています。
男女関係なく働くこの時代ですが、一方で “男女比”が極端に偏った職があることもまた事実。平成22(2010)年総務省が発表した国勢調査*をもとに各職業の男女別割合を探ってみると、意外な現実が見えてきました。
*参照 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001050829&cycode=0
女性比10%未満の職業が約3割
同年の国勢調査によると、15歳以上の就業者総数5961万人のうち女性就業者は2551万人。比率は男女でおおむね6:4です。数字で表すと女性の割合が多いような気もしますが、女性がほとんどを占める仕事もあれば、その逆も存在するのです。
調査対象となった232の職業のうち、女性比が10%未満の職業は66にのぼります。約3割の職業では、女性が超少数派という環境にあるのです。
「教育」「芸術」分野では女性が目立つ
職業ごとに見てみましょう。
女性就業者数の比率がもっとも高いのは「助産師」(100.0%)、次いで「歯科衛生士」(99.9%)、「保健師」(98.7%)、「家政婦(夫)、家事手伝い」(97.6%)、「保育士」(97.2%)……と続いています。
他にも、「幼稚園教員」(93.7%)などの教育関係や、「図書館司書、学芸員」(81.6%)「個人教師(舞踊、 俳優、 演出、 演芸)」(74.7%)といった芸術分野で女性の力が発揮される傾向がありました。痒いところに手の届く細やかな気配りや繊細な美意識が活かされているのでしょうか。
ハードルの高い「警察官」「会社役員」
一方で、女性就業者数の比率が低い職業には、「診療放射線技師」(20.1%)、「警察官、海上保安官」(7.5%)、「自衛官」(6.0%)など、やはり技師や危険を伴う職業が並びました。増加傾向にあるとはいえ、女性にとってはまだまだハードルの高い世界と言えそうです。
「会社役員」も、平成17(2005)年国勢調査の13.8%からじわじわ伸びてはいますが、いまだに14.5%。国際的に見れば低い水準といえます。今年施行された女性活躍推進法がこの数字にどの程度影響を与えるのか、気になるところです。
予想以上に少ない医師と弁護士
女性の少ない職業の中でも意外なのが、「医師」(19.5%)や「裁判官、 検察官、 弁護士」(15.9%)、「弁理士、 司法書士」(12.9%)などの“士業”です。「コンビニより数が多い」と言われる「歯科医師」でさえ、21.8%という少なさ。連日のようにメディアで女医や女性弁護士が取り上げられているのを見ていると、医師や士業を生業にする女性が増えたように感じますが、割合としてはさほど高くないのです。
女性写真家はいまだ黎明期?
また、「写真家、 映像撮影者」の女性比も目を惹きます。パーセンテージにして、26.3%という低さ。蜷川実花さんの他、ウートピでもご紹介したフォトグラファー・花森友里さんやインベカヲリ★さん、ヨシダナギさんなど、鋭い切り口で高く評価されている女性写真家が続々と登場している中、予想を裏切る数字と言えそうです。
他の芸術分野で女性が存分に活躍していることを考えると、今後は女性の占める割合は高くなっていくのでしょうか。
異性だらけの職場で活躍する女性たち
職業別の男女の就業状況を数字から掘り下げてみて、いかがだったでしょうか。
「想像通り」か、はたまた「え、その仕事、そんなに男性が多いの?」か。いずれにせよ、男だらけの職場で奮闘している女性、紅一点ならぬ黒一点として女性に囲まれながら仕事をしている男性がいる。そんな現実が見えてくる数字でしたね。
かつては「女性のみ」とされていた歯科衛生士も、法律が見直され、2012年に初の男性歯科衛生士が誕生したように、「性別の枠を取り払って希望の職業に就けるようにしよう」という時代の大きな流れがあります。
しかし、同性の少ない場所に飛び込むのはちょっと勇気のいる行為。雨にも負けず風にも負けずアウェイな職場環境にも負けず、彼女たちが(彼らが)飛び込んだ理由は?
次回からは、そんな異性ばかりの仕事場で凛と生きる男女に、やりがいや生き様を伺います。
(小泉ちはる)