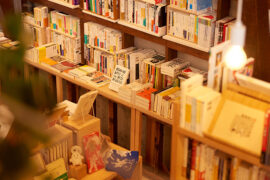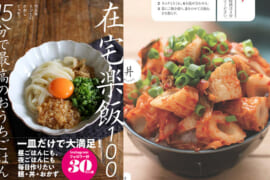「結婚相手や子どもより、家が欲しい」
編集者としてバリバリ仕事をして自由を謳歌してきた私が、30代も終わりに差し掛かった時、突然に感じた欲望。それは、インテリア好きとして常々感じてきた「ルイス・ポールセンのPHランプが欲しい」「アルネヤコブセンのスワンチェアが欲しい」(共に北欧インテリアの名作)といった物欲と同レベルの欲望だった。
でも、実際に“家”を手に入れるべく動き出してみると、気づいた。
「おひとり様オンナが家を持つのは、ひどく面倒くさい」と。
「ポールセンのランプが欲しい」と言っても、欲しい理由を尋ねられることはない。でも「家が欲しい」と言えば、必ず聞かれるのだ。「なぜ、欲しいの?」と。第2回は、これまで数え切れないほど投げかけられた、この質問について考えてみたい。
どうして、いちいち説明しなきゃいけないの?
これから回を分けて書いていくように、おひとり様オンナが家を持つことは、ひどく面倒くさい。そして、その面倒くささの大半は、「いちいち説明しなくてはならないこと」に起因しているような気がする。
カップルや家族なら、家を持ちたい理由を説明する必要はないし、そもそも、誰も「どうして、家を建てるんですか?」なんて聞かない。「家賃を払うのがもったいないから」かもしれないし、「犬を飼いたいから」かもしれないし、はたまた「楽器の練習をしたいから」かもしれないけれど、いずれにしろ、説明を求められることはない。
ところが、これが「おひとり様オンナ」というだけで、もう、うんざりするほど聞かれるのだ。「なぜ、家を建てようと思ったんですか?」と。
40歳にして7坪の一軒家を建てて以来、「独身の女性」が建てた「都心の7坪住宅」という二重のもの珍しさによって、テレビ、雑誌、ウェブメディアとさまざまな方面から取材を受けたが、最初にこの質問が確実に投げかけられる。
至極当然の問いかけだと思うし、逆の立場(私の職業はライターだ)でも同じ質問をすると思う。
家族で家を買った人へのインタビューならばさして重要ではない、文字通り話をはじめるきっかけ程度の意味合いしか持たないこの質問。しかし、どうやらオンナひとりで家を買った私へのインタビューとなると、たちまち最重要事項、つまり記事の根幹をなす質問になるらしい。
超つまらない理由で、すみません…
私の答えは「引っ越しの失敗」。
す、すみません、超つまらない答えで……。
以下に書くように、「家が欲しい」と思った理由はいくつかある。でも、最大の理由はコレだった。毎回、答えた瞬間、相手の顔にうっすら落胆の表情が浮かぶように感じる。「おひとり様オンナが家を建てるには、もっとおもしろい理由が要るよね……すみません」心の中で勝手に頭を下げながら、この超つまらない答えを少しでもおもしろくしようと奮闘する私。
37歳で借りたマンションの部屋が、引っ越し初日に後悔するほど生活音が不快だったこと、窓から漏れ聞こえる「ひゅーひゅー」という風の音、階段をのぼってくる「コツコツ」という靴音、住人のカギについているのであろう「チリンチリン」という鈴の音……。
「すぐにでも引っ越したい。でもそれなりにまとまったお金を支払って転居してきたのに、また新たな住処を探すのは面倒だし、何よりも癪だ。そうだ! それなら家を買ってしまおう! そう思ったんです!」
「ひゅーひゅー」「コツコツ」「チリンチリン」……擬音語もふんだんに盛り込んで、引っ越しの失敗をどうにかおもしろく語ろうとする私に、インタビュアーは無慈悲にたたみかけてくる。
「でも、それは大変な決意だったはず」
「不安はありませんでしたか?」
あ、こんな話は欲しくないですよね、もっとなんかドラマチックな理由が要りますよね、す、すみません、ホントごめんなさい。
オンナがひとりで家を買うことに、世間は「そうだ! それなら家を買ってしまおう!」という能天気な動機なんか求めてはいないのだ。「結婚詐欺にあってやけくそで建てた」とか、「15年付き合ってフラられた彼氏を見返したくて建てた」とか。劇的な出来事に遭遇したが上の覚悟であってほしいのだ。
「父の死」というもう一つの理由
少々不謹慎な言い方だが、そこで用意しているもう一つの理由が父の死だ。
2009年9月、突然父が死んだ。山登りを趣味としていた父は、大好きな山の頂上付近で倒れたそうだ。くも膜下出血だった。
その時、私は日本から遠く離れた北欧の地にいた。頻繁に訪れているわけでもない外国の地で父の訃報を知るとは、私の人生において想像すらしていなかったことだ。今思えば「なかなか忘れがたい、劇的な別れだったな」と思ったりもする。
当時は漠然とでも親が死ぬなんて考えたこともなかった。それに憎まれっ子世にはばかるじゃないが、なんとなく父は長生きするような気がしていた。
昔ながらの“頑固おやじ”だった父とは、仲違いしているわけではなくとも、積極的にコミュニケーションをとることもなかった。正直、父の死でこれほどまでの喪失感を味わうとは思いもしなかったし、しばらくは何をする気にもなれなかった。もう二度と幸せという感情を抱くことはないだろうとさえ思ったものだ。
でも数か月後、突然思った。
「人間、いつ死ぬかわからない。やりたいことをやろう!」
思い返せば、家を建てたことを含め、私の人生の方向転換がはじまった瞬間だった気がする。
「父の死が私の人生にもたらした変化は大きかった」
これはなかなか劇的な理由ではないか。なんて思えて話せるのは時間が経過したからだ。時間が人を癒してくれるというけれど、まさにそうである。人間は強い生き物だとしみじみ感じる。ちょっとふざけた「引っ越しの失敗」の後に「父の死」の話をすると、みなさん、なんとなく納得するのだ。
家に対するコンプレックス
父の死の他にもう一つ、世間が納得してくれる理由がある。
それは、家に対するコンプレックスだ。
私は20歳になるまで自分の部屋がなかった。家族6人で2Kという小さな町営住宅に住んでいたからだ。中学校までは、同じ住宅に住んでいる友人が多かったから気にならなかったけど、高校生になった時、私はみすぼらしい自分の家が恥ずかしくなった。
友人の家には遊びに行ったけど、わが家には絶対に呼ばなかった。雨が降ってきたからと、友人のお母さんが車で送ってくれると言っても、「大丈夫」とびしょ濡れになりながら自転車で帰った。家を見られるのが嫌だったのだ。そして小さな世界で、世間の目を気にしている自分も嫌だった。
ひとり暮らしをはじめてから、バカみたいにインテリアを取っ替え引っ替えしていたのは、その反動だろう。「いつでも人を呼べる家に住みたい」それは、たぶん「家が結婚の障害になる」なんていう世間の目よりもずっと大切な、家に対する私のこだわりだ。
世間が受け入れてくれる理由
「引っ越しの失敗」と「父の死」と「家へのコンプレックス」。
私が「家が欲しい」と思った理由は、この3つだ。でも世間が、おひとり様オンナが家を持つ理由として認めてくれるのは、後ろの2つだけなんだと、何となく感じる。身内の死というドラマ性と、みすぼらしい実家という悲劇性は、喜んで受け入れてくれるけれど、「ただ、心地よい住処が欲しかった」という凡庸な理由は、受け入れてもらえないようだ。
とはいえ、私は普通に家が欲しかっただけなのだ。
父が死んでいなくても、実家が普通の一軒家でも、私はこうして7坪ハウスを建てていたかもしれない。結局、オンナひとりで家を買うからこその理由なんていうものはない。家族と一緒だろうが、オンナひとりであろうが、それぞれに自分たちなりの理由があるのだ。
(塚本佳子)
記事トップの写真:鳥村鋼一/アーカイブ:オンデザイン