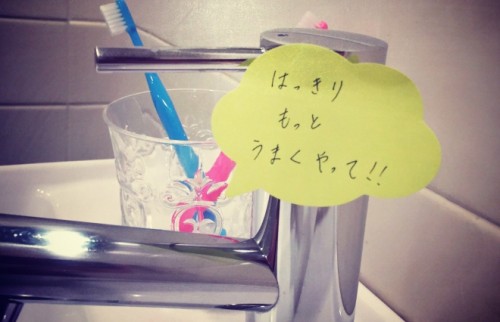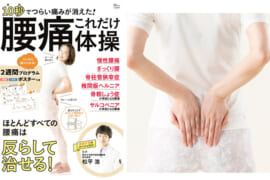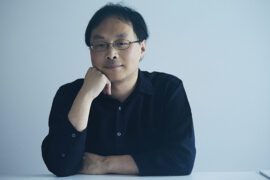人生100年(あるいは120年)時代と言われるけれど、この先の自分はどうしているだろう。仕事はどうしてる? 家族や友人との関係はどう? どんな趣味を持っている? お金や健康の心配は? 未来の自分に聞いてみたいことがたくさん浮かんでくる。
そこで、人生の後半とどう向き合いたいか「50 to 100」として、50代から100歳以上の著者の本から考えていきたいと思います。
今回紹介するのは、『102歳、一人暮らし。哲代おばあちゃんの心も体もさびない生き方』(文藝春秋/石井 哲代、中国新聞社)。作家の南綾子さんに読んでいただきました。
そんなの、もっと年とったらどうでもよくなるよ
わたしは現在42歳で未婚、子供もいない。婚活をしていた時期もあったけれど、結婚につながる出会いは得られなかった。婚活中はネットなどのメディアで高齢独身者への手厳しい意見を見聞きするたびに落ち込んだ。そんな苦しみや悩みを口にすると、年上の友人知人から、よくこう言われたものだった。
そんなの、もっと年とったらどうでもよくなるよ、と。
それは半分本当で、半分は嘘だったと思う。確かに焦り自体は40歳を境に、すーっと薄くなった。30代後半頃は、日一日とタイムリミットに近づいていく恐怖にさいなまれ、38歳2カ月が38歳3カ月になっただけで、チャンスの機会が大幅に減ったような感覚にとらわれていた。が、42歳1カ月が42歳2カ月になったところで、世界はもう何もかわらない。
それでも。44歳11カ月から45歳0カ月はだいぶ違うかもしれない。50代の大台にのった瞬間はどうなのか。結婚はともかく、出産しなかったことは後々引きずってしまうのではないか。子供がものすごくほしかったわけじゃない。それでも、女として重要な宿題をやりわすれたような感覚がずっとある。母にならなかったこと。一度もきちんと、そのことに向き合わなかったこと。すべてがどうでもよくなってしまうことなんかなくて、ずっと心の中に魚の骨にようにひっかかったまま生きていくことになるんじゃないか。
102歳になっても消えない思いはある
はたして、本書にはその答えが書いてあった。それはこうだ。
子供を産めなかった悔いは、たとえ102歳まで生き延びても消えない。
哲代さんは99歳のとき、手持ちの仏教本の表紙裏にこう書いている。「御先祖様 すみませんでした。良英さん すみませんでした」。衝撃的な言葉だ。何をすまないといっているのかというと、跡取りを産めなかったこと。哲代さんは26歳で職場の同僚の良英さんと恋愛結婚したのだが、子宝に恵まれなかった。その結婚から約70年、良英さんの逝去からも約20年の時を経てなお、彼女はいまだに心の中にやりのこした宿題を抱えている。
もちろん、わたしの感じてきたプレッシャーと哲代さんのそれは全く比較にはならない。なにせ時代が時代である。毎日のように子供についての無神経な、しかし悪気のない言葉を投げかけられたのかもしれない。本書には書かれていないが、もしかすると家族からも、あったかもしれない。
「もっと年をとったらどうでもよくなるよ」という年上の友人知人たちの言葉。実はわたし自身も、若い女の子たちに似たようなことを口にしたことが何度もある。太っていること、一重瞼であること、職場でかわいい女の子ばかりがちやほやされること。そんな切ない苦しみを吐露する彼女たちに、つい言ってしまう。
「そんなの、おばさんになったらどうでもよくなるよ」と。
それは半分本当で、やっぱり半分嘘だ。42歳になっても、生まれながらの美貌に恵まれた人を見ると、少しだけ胸がちくっと痛む。若い女性と自分とで、男性の態度があからさまにかわると悲しい気持ちになる(嘘です、本当はこのごみくず野郎と思っています)。すべてのことがどうでもよくなったわけじゃない。
なぜそんなふうに達観したかのようなセリフを口にしてしまうかといえば、それが年長者としてのたしなみだからだし、年をとればとるほど、苦しみと向き合って悩み抜くのは体力的にも精神的にもつらくなってくるからだ。どうでもよくなるのではなく、どうでもよくなったと自分に言い聞かせ、見ないふりをしているだけとも言える。
日々の小さな挫折にいちいち傷つきながら生きていく
しかし102歳、この4月で103歳になる哲代さんは違う。100歳を過ぎても心の中の宿題と向き合いながら、自分で自分を励ますことで一日一日を、一人で、生きていく。
「バアさんになったらそんなことどうでもよくなる」なんて無責任なことは言わない。そういったところが、この本が数あるシニア本の中でバカ売れしている理由かもしれない。
悩むなんて時間の無駄だと切り捨てない。うわべだけのポジティブワードを並べたてない。苦しみを抱えたままでも生きていける。苦しみをたった一人で抱えたままでも、健康に幸せに生きていける。そのことを教えてくれる。
そのためには落ち込みそうになったとき、やるべきことをたくさんつくって、体を動かすことが重要だ、そう哲代さんは本書の中で何度も何度も繰り返す。自分を励ましながら、ご機嫌に生きる。なにせ哲代さんは102歳。日々、何かができなくなる。体を動かせる時間も範囲もどんどん縮小する。そのたびに哲代さんは落ち込みそうになり、そして自分をなんとか励ますことで今日を乗り越え明日へ向かう。
気持ちはわかるが……102歳、できなくて当たり前じゃないですか? わたしなんて42歳だけど、疲れやすくなったことや、眠れなくなったことにいちいち落ち込まないですよ? 思わずそう問いかけたくなる。しかし哲代さんは違うのだ。日々の小さな挫折にいちいち傷ついて、それでも今できることをやれるだけやって、必死で自分を励ます。悩むことこそが生きること、そのメッセージは絶望であり希望だ。
(南 綾子)