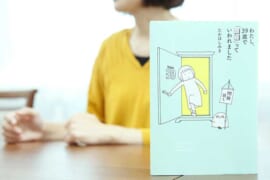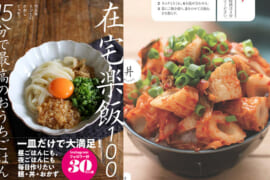心理学では、人の心の動きや行動を解き明かすために、科学的な実験を通した研究が行われています。その学問から生まれた心理学用語を軸に、仕事、家庭、恋愛、子育てなど実生活で活用できる知識を得ようと、心理学博士の堀越勝(ほりこし・まさる)さんに連載でお話しを聞いています。
第2回は「ピグマリオン効果」について、心理学的意味と実生活での活用法について尋ねます。

堀越勝氏
期待を受けるといい結果をまねく心理効果
——「ピグマリオン効果」とは、何を示しているのですか。
堀越勝さん:周囲の人から期待されると学業や仕事などの成績、成果があがる現象を言います。教育心理学における心理行動として知られています。
「ピグマリオン」とはギリシャ神話に登場する王の名で、自らが彫った彫刻に愛情を注いだ結果、愛の神の力で彫刻が人間になって結ばれたという神話にちなんでいます。
1964年にアメリカの教育心理学者ロバート・ローゼンタールが実験で検証して発表したので「ローゼンタール効果」とも呼ばれ、また実験の内容から「教師期待効果」とも言われています。
——どのような実験が行われたのでしょうか。
堀越さん:サンフランシスコのとある小学校で、「成績が向上する生徒を割り出すテストを行う」と教員に伝えて、生徒たちにテストを受けてもらいました。
テスト後、教員には「今後数カ月間で成績が向上する生徒の名簿」と伝えてそれを見せました。しかし実際には、テストの結果とは関係がない無作為に選んだ生徒の名簿だったのです。するとその名簿にあった生徒たちはその後、成績が向上したというのです。
この実験の報告論文では、教員が名簿にあった生徒に対して、無意識に期待のこもった行動をとったこと、また、生徒も期待に応えようと行動を変化させることで成績が向上していったとされています。

期待で無意識にパフォーマンスが向上する?
——本当のところは、選んだ生徒の成績が向上するという根拠はなかったのですね。なぜそのような現象が起きたのでしょうか。
堀越さん:人は誰かに期待されると、無意識に「がんばろう」「期待に応えよう」とやる気が出てパフォーマンスが向上するという説があります。
——ローゼンタールの実験結果には賛否両論があるそうですね。
堀越さん:ローゼンタール自身が論文で、期待をかけた生徒と教員のつき合いが2週間以内のピグマリオン効果は91%であったこと、一方で、2週間以上の場合は効果が12%だったと記しています。このことから、ピグマリオン効果は実証されていないという批判意見があります。
それに、同じ研究手法、条件で再度実験を行った際に同じ結果を出すことができない「再現性のなさ」や、教員の心構えの問題ではという意見もあります。
ピグマリオン効果を日常生活で活用するには
——堀越先生はピグマリオン効果をどのように考えますか。
堀越さん:端的にいうと、ピグマリオン効果は、関係がある人について自分が「推測」していることがその相手に伝わるということです。「以心伝心」と似た現象ですね。
重要なポイントは2つあります。1つは、人間はまだ起こっていないことを「推測する動物」だということです。「先を予想して準備をする」「こうなって欲しいと夢を見る」など、推測する力があるからできるのです。
2つめは先述のとおり、ピグマリオン効果は人との関係の中で起こり、自分の考えは相手に伝わりやすいということです。実に不思議なことですが、雰囲気や態度などの非言語によるコミュニケーションのほうが言語コミュニケーションよりも強いという研究報告もあります。
アメリカの心理学者アルバート・メラビアンが1971年に行った実験結果によると、気持ちを伝える手段として影響を与える比率は、「言葉の内容(言語情報)が7%」、「声のトーンや大きさ(聴覚情報)が38%」、「表情や態度(視覚情報)が55%」と報告されています。
これらのことより、ピグマリオン効果から学びたいのは、「自分は周りの人についてどのように推測しているか」ということです。そのイメージは習慣化して相手に伝わるようになるでしょう。
最悪と最高のシナリオを書いてみる
——ピグマリオン効果を日常生活でうまく活用するにはどうすればいいですか。
堀越さん:意味合いのとおりに、家族、職場、学校などで、相手に期待する言葉をかける、期待の眼差しを送るといった行動に出ると、相手のモチベーションがアップして能力を引き出す機会になるかもしれません。コミュニケーションをうまくとる手段としても有用でしょう。
それには、自分は日ごろ、他人に対して何をどのように推測しているのかに気付くことが重要です。現実的であると同時に、見えないポジティブな面を見る。そして、それが相手に伝わるという点がポイントです。
——では例えば、受験前に成績が伸び悩む子どもにはどう接すればいいでしょうか。
堀越さん:成績がふるわなければ、親はネガティブな推測をしがちです。「どうせあなたはダメだ」と思い、将来についても「絶対に落ちる」「恥をかかされるに違いない」と続き、言葉に出さずとも声の調子や表情で伝わります。こうした推測が習慣化すると、自分も相手もネガティブな思考や行動の循環に陥ります。
そうならないための方法は、状況を客観的に見つめる練習をすることです。まず紙を用意して最悪のシナリオを書いてみてください。次に最高のシナリオを書きます。現実はその真ん中あたりであることが多いのではないでしょうか。
また、この子の長所は、短所はなど、両極端を書いてから、現実を見据える考えに修正します。
もしその子が受験に失敗したとしても、「自分は愛されている」と思えたら、子ども自身は自分の将来をどう推測するでしょうか。そう考えて何度でも書き直しましょう。
そして、非言語コミュニケーションがその子に強い影響を与えることを忘れずに、それらについて正直に子どもに話してみることです。
相手の気分や行動を見つめてビジネスに活かす
——ビジネスの現場ではどうでしょうか。
堀越さん:先ほどと同様に、紙に最悪と最高のシナリオを書きましょう。それを現実に即して十分に検討をしたうえで、ビジネスの相手に非言語コミュニケーションを意識しながら話してみます。
話しづらい場合は、書いた紙をくり返し読んで、話す練習をしましょう。まずは、相手に希望を持ってもらえる推測をすることが理想です。

ただし、相手の気分や行動を見つめて実践しましょう。相手が慢心しているときにはピグマリオン効果は有効ではなく、逆に慢心をあおりかねません。
ピグマリオン効果とは、ある期間を経て徐々に生じるものです。普段から、相手をどう思っているか、どう推測しているかが効果をもたらすカギとなるのです。
聞き手によるまとめ
他人からの期待で成績や成果があがるピグマリオン効果は、教育の場での実験結果から提唱されたものである一方で、再現性もないことから賛否両論があるということです。誰かの能力を伸ばしたいときには効果のメリットを見込んで、相手に希望を抱いてもらえるような期待の言葉や態度で接したいものです。
(構成・取材・文 藤原 椋/ユンブル)