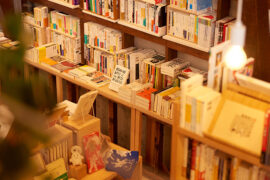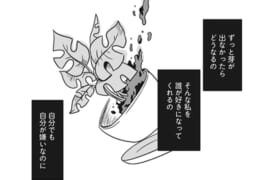“ギャラ飲み”で稼いで整形手術を受けたい女子大生、深夜の学校へ忍び込む高校生、親友をひそかに裏切りつづけた作家--。
2020年春の東京を舞台に男女6人の体験を描いた川上未映子(かわかみ・みえこ)さんによる小説『春のこわいもの』(新潮社)が2月28日に発売されました。
2年半ぶりの新作について伺った前編に引き続き、後編では、書き手として常に意識していることを中心に伺いました。
フェミニズムの重要な役割
——『夏物語』は40カ国以上で翻訳が進み、世界的にも評価の高い作品です。俳優のナタリー・ポートマンさんも自身のインスタグラムで『夏物語』を紹介し、対談も実現しました。女性の身体性やフェミニズムについての発信も多いですが、ご自身の小説とフェミニズムの関係についてはどうお考えですか?
川上未映子さん(以下、川上):わたし個人はフェミニストですし、書いた作品がどのように読まれることもすべて歓迎します。生殖倫理や、人間の生き死に、また貧困や労働について書いた小説ですが、「夏物語」は海外ではフェミズム小説として紹介されることがとても多くて、それはとても嬉しい読まれ方であり、評価でした。女性の人生について真剣に書こうとするときに、書き手がそれを意識してもしなくても、フェミニズムを通過する──それは当然のことだと思うからです。
でも、わたしはフェミニズム小説を書く、フェミニズム作家ではないと思います。いろんな文章を書きますし、それがどんなに愚かなことでも、醜いものでも、美しいものでも、人以外のものでも、とにかく世界の描写がしたいという欲望で文章を書いています。それでも、わたしにとってフェミニズムは勇気そのものであり、現実を生きて理解するための大きな力なんです。人間のひとつの側面や状態である女性という存在について、深く考える機会と、本当に多くの示唆を与えてくれます。人間と社会、そして世界を書くとき、読むときに、フェミニズムが重要な役割を担うことは疑いようがありません。
「いつも緊張していること」書き手として意識していること
——近年、小説を含めて表現や作品が多様性やフェミニズムの観点から「いかがなものか」と批判される状況があります。それを指して「ポリコレ(ポリティカル・コレクトネス=政治的正しさ)疲れ」と言われることもありますが、それについてはどうお考えですか?
川上:書き手としては好きに書くし、読み手としては好きに読む、ということになると思います。これは、いわゆる「文学無罪論」というのではなくて、もっと原理的なこととして、作家だって自分が結果的に何を書いたかなんて、どうしたってわからないからです。誰も、自分が今、生きている時代を完全に理解することはできません。そのうえで、作品を社会にだす人間は、その作品の評価、影響において、すべてを引き受けることになるんだと思います。作品は読み継がれることにも意味がありますが、同時に、読まれなくなることにも意味があると思います。
私が書き手としてできることは、小説を構成する要素すべてにおいて、手を抜かないということです。正しさや目的を意識するのではなくて、これほどたくさん物が書かれる中で、蓄積があるなかで、さらに何かを書こうとしていることが、どういうことなのかを考えること。その意味で、いつも緊張していることが、私にとっては重要だと思っています。
川上未映子が考える、「読む」ということ
——緊張感というのは、作家の感受性にかかってくるものなのでしょうか?
川上:うーん、感受性の問題なのかどうかはわからないし、他の作家のことはわからないけれど、例えば、批評って基本的に悪口だ、みたいに思われているところがありますよね。もちろん悪口みたいな雑なものもあるんでしょうけど、それは単なる悪口であって、批評ではありません。それと、作品が批判されたときに、どうも自分が批判されたように思う書き手もいるみたいですが、そこも関係ないです。批評には、愛とか礼儀といった概念は使えません。どんなに手厳しいものでも、優れて鋭い批評は作品にとって必要です。
自作でも、誰の作品でも、新しい読みが提示されたときとか、見えなかったものが言語化されたとき、感動とともに学ぶことが必ずありますよね。それが読むということだと思いますし、その意味で、私自身も批評的でありたいな、といつも思っています。それが、さっきお話した、自分が必要としている緊張と関係しているんだと思います。書き手としては、とにかく書くときに、楽をしないこと。怠慢な部分がないかどうか、いつも注意すること、それがとても大切なことだと思っています。
(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子、写真:宇高尚弘)