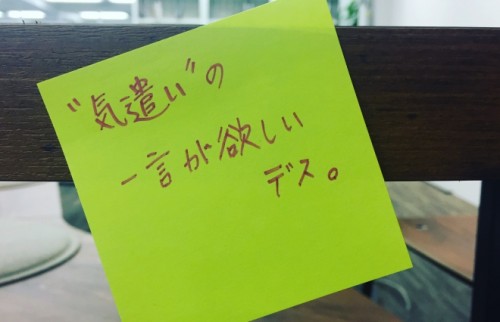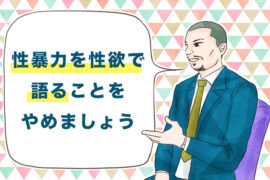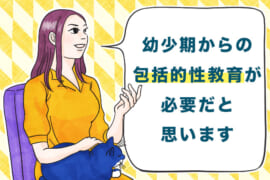コラムニストの桐谷ヨウさんによる連載「なーに考えてるの?」。ヨウさんがA to Z形式で日頃考えていることや気づいたこと、感じたことを読者とシェアして一緒に考えていきます。第27回目のテーマは「A=Adjust(調整)」です。
調整は「突破する力」がない人の処世術?
かつての自分は、調整という言葉に、いくぶんネガティブな響きを持っていた記憶がある。
たとえば、
ベストアンサーにたどり着くことができないから、調整(妥協)をかけて何とかする。
大きな仕事ができない人間だから、細かい調整役(些事係)を担当する。
乱暴に言ってしまえば「調整」とは、「ぶっ飛んだ力」や「突破する力」がない人の処世術である──というニュアンスを感じてしまっていた、というか。特に若い頃はそんなふうに考えていた気がする。いま思えば、なんて勘違いをしていたんだ! って話なんだが。
社会人を長くやっていると、仕事とは調整ごとの連続であることに気づく。
利害関係がちがうなかで、なんとか着地点を合意しようとする。あるいは金額と品質と期間の折り合いを、うまくつける。案件に道筋が決まっていなくてグチャグチャしてしまっているから、まずは交通整理をかけていく。社外、社内を問わずに人間関係のもつれた綾を、うまくほぐしていく。業界や職種はちがえど、そういったシチュエーションに誰しもが出会うことだろう。
そして、これらはその手腕によって、案件の成否が左右されるほど重要なものである。よく聞く地味であるあるな厄介ごとほど、根が深くてタチが悪いものなのである。
実は自分が社会人としてバリューを発揮しているのはこういった部分も大きくて、なかなかシステマティックに解き解せない状況で、感覚的になんとなくうまく調整できてしまうのが大きな武器となっている。顧客をなだめたりすかしたり、あるいはこれしかないという方法に割り切って攻めていくことで、わりと良い感じに終わらせることができる(そして、ここがミソなのだが、きっと本当の意味でベストなやり方ではない!)のが、ウリになっているのである。
最初の頃は、ロジカルシンキングを頑張ってやってみるけど、なんか合意形成が得られない……みたいなことが多かった記憶がある。恋愛を中心としたいろんな人との交流のなかで、「他者が満足しなくても、納得するのはどういうラインであるか」だったり「期待値が高いときにそれなりのものを持っていっても喜ばれないが、期待値が低ければそこそこのものでも喜んでもらえる、という期待値コントロールを頑張る」ということの重要性を、仕事に転用できるようになってからうまく行きだしたような気がする。
こういった「調整スキルが上がった99のきっかけ」みたいな本を出すと、売れるかもしれない。ワンチャン、マーフィーの法則を越えるかもしれない。
大人になる=調整力を身につけること?
それにしてもビジネスにおいて「この件、調整しといて」「自分が調整しときます」「ここは調整ですね」って感じで、何でもかんでもチョーセイと言われる。そもそもチョーセイって何なんだ。とりあえずめんどくさいことを片付けといて、くらいのニュアンスで言ってる感じもするよな(笑)。
そしてadjustという言葉で連想することはもうひとつ、特定の状況における身のこなし方についてである。
身のまわりの人たちを見ていると、20代の頃はそれなりに尖っていた人たちも、30代になるとそれなりに状況に対応できるようになっていった人が多い印象を持つ。もちろん自分だってそうで、昔は理由なくムカついて噛み付いていたようなことがどうでも良くなって、その場がスッと通りすぎるなら、スルーしたり、適当に合わせることができるシーンがかつてよりも多くなった気がしている。ある意味では成長であり、ある意味では感情とプライドの劣化と言えるだろう。
先日、オンライン同窓会で飲みながら喋った同期たちは、アジャストできるようになってきた自分に対する自信と、よくいる大人になってしまった自分に対するちょっとした残念さと、まだまだ機会があればはみ出したいと思っている野心がブレンドされてるように見えた。30代中盤もまだまだ面白い年代だなぁ、と同期を見て思わされた。
それにしても、adjustじゃない仕事ってなんだろう。クリエイティビティを要求される仕事ということだろうか。状況にadjustしない自分とはなんだろう。どんなときもブレない自分を持つということであろうか。どちらも微妙にちがっているような気がする。おそらくほとんど幻想のような「理想の仕事像」や「理想の自分像」に囚われているために感じる疑問ということなんだろう。最近では仕事に関する相談を受ける機会がどんどん増えてきたけれど、いくつになってもつきまとう疑問のようである。
「はたらく」において仕事のadjustと、自分のadjust。何を得られれば自分は本当に満足なのか、あるいは全てが満足できる働き方って果たしてあるのだろうか? いろいろな人が抱えている葛藤につながる、奥が深いテーマが眠っているんじゃないだろうか。