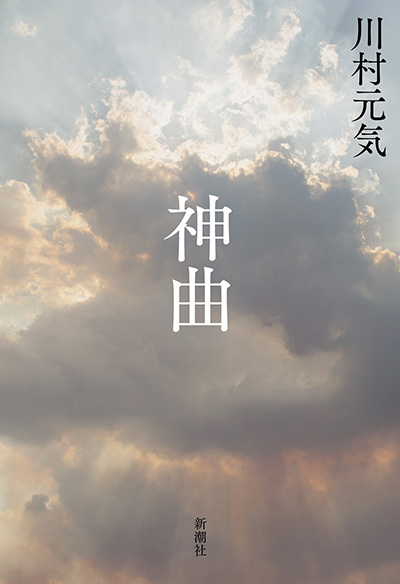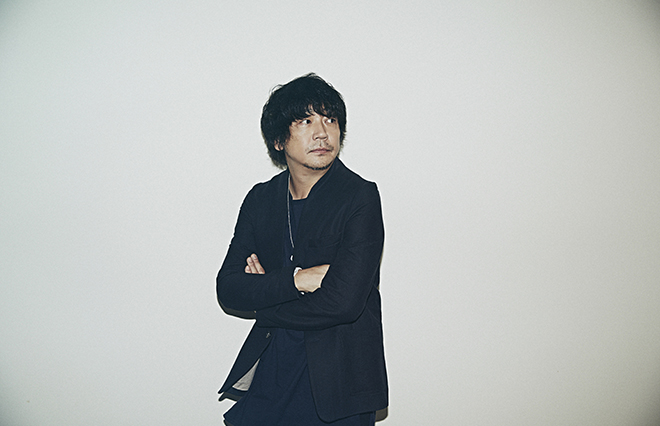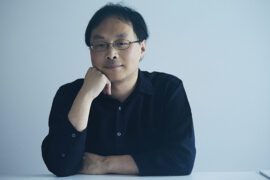小説家、脚本家、映画プロデューサーなどさまざまな顔をもつ川村元気(かわむら・げんき)さんの2年半ぶりの長編小説『神曲』(新潮社)が11月18日に発売されました。
通り魔に息子を殺され、ある「神」を信じることになった一家の、秘密と崩壊、再生を描いた物語。信心と不信、そして「目に見えないけれども、そこにあるもの」を描いています。
川村さんと言えば、映画『告白』『悪人』『モテキ』『君の名は。』などヒット作を手がけ、小説家としても全世界累計200万部を突破したベストセラー『世界から猫が消えたなら』を2012年に刊行して以来、『億男』『四月になれば彼女は』『百花』など話題作を次々に発表しています。
世間の空気をいち早く感じ取り、“今の気分”を作品に込めて多くの人に届けてきた川村さんにお話を伺いました。
【前編】川村元気が2年半ぶりの新作で描いた「不信の時代に信じられるもの」
「信仰の正体」を求めて取材を続けた
——『神曲』の執筆期間はどのくらいだったのですか?
川村元気さん(以下、川村):取材を大体1年くらいやって、書きながらも取材を続けていました。新興宗教の信者や元信者の方にも、お話を聞きました。もちろん古典的な宗教の方にも話を聞きました。イスラエルをはじめとして、この3~4年は宗教というものが中心にある国を意識的に周っていました。
——イスラエルのほかにもどこか行きましたか?
川村:もちろんバチカンも行きましたし、インドやチベットにも足を伸ばしました。京都にも頻繁に通っていろいろなお寺の住職のお話を聞いたり、青森の恐山にも行きました。自分の中で宗教とか、神とか仏とか、目に見えない信仰の正体みたいなものを知りたくてウロウロしていた4~5年でした。
——まさに(小説の登場人物の)隼太郎ですね。
川村:隼太郎がかなり自分に近いです。彼が小説の中でやっていたようにいろんな宗教や神の言葉をメモしたり。そういう意味では取材を4、5年ほどやって書くのは1年くらいかけてという感じですね。
小説の執筆は「分からないことを知るための行為」
——いつも小説はどんなふうに書いていくんですか? 書きたいテーマで取材をして、集めていく?
川村:小説って本当にしんどい仕事なんです。だからこそ、そのときに自分が切実に知りたいことを書くしかないんです。『世界から猫が消えたなら』は死に対する恐怖に向き合うために書きましたし、『億男』はお金って怖いという気持ちで書き始め、『四月になれば彼女は』は恋愛感情がなくなっていく自分に対して書きました。
要は、自分にとって小説を書くというのは分からないことを知るための行為なんです。僕は映画の仕事があるから毎年のようには書けない。だから、本当に自分が知りたいことをその時に書くというやり方しかないんです。
書いて伝えるためには、懸命にそのことを知ろうとするし、調べるし、しかも表現する過程で自分が何かを見いだしてないと書けないので。自分が分からないことや不安に思っていること、知りたいことが、今を生きる読者たちとリンクしていると信じて書いていきます。
『神曲』は、前回もお話ししたように「信心」や「不信」が今を生きる皆の潜在的な不安や興味の根幹にある気がしていて、その怖さや憧れの正体を知るために懸命に調べて、考えながら書きました。自分が知りたいことを書いているから結論が分からないし、分からないから苦しい、そんな感じですね。
敬虔なクリスチャンの親族の「心の中を知りたかった」
——書いていくと、だんだん自分の中で何かが変化していくのでしょうか?
川村:めちゃくちゃ変化してきます。冒頭、何かを信じている人に対して胡散臭い、疑わしいと思っている三知男という男の目線で物語は始まります。それはやはり当時の自分に近かった。第2章は妻の響子の視点に変わる。彼女は神を信じ切っている人ですよね。僕の親族も敬虔なクリスチャンなのですが、澄み切った湖のように神を信じていて「この人の心の中はどうなっているんだろう?」とずっと知りたかったんです。どんなちゃちゃを入れても揺るがない確固としたものがあって、その世界を垣間見たかったこともあり、一人称で書きました。
——第2章だけ一人称で書かれていますね。
川村:信じ切った人の世界を書いてみたかったので一人称で書きました。
——書いてみていかがでしたか?
川村:かなり幸せでしたね。でも自分はそっちには行ききれないし、だからと言って何も信じないでは生きられない。だから信心と不信のあいだで揺れる、第3章の花音の気持ちに近づいていきました。「自分は何を信じられるのか?」「そもそも神の正体は?」という花音や隼太郎の気持ちに同化していった。
——ネタバレになってしまうのであまり詳しくは言えないのですが、ラストが圧巻でした。
川村:宗教とか神を論じようとすると、どうしても哲学的な話になっていくのですが、そうはしたくなかった。神や宗教について深く考えたことがない人が、読んで揺さぶられてほしいと思って書きました。
「どう表現するか?」より「何に気付くか?」
——小説もそうですが、川村さんは『告白』『悪人』『君の名は。』などの映画を作られてきましたが、川村さんの作品からは常に「今の気分」を感じます。前回も「まだ言葉になっていない“気分”を、物語にしたいという欲望がある」とおっしゃっていましたが、川村さんはどんなふうに今の気分を感じ取ってカタチにしていくのでしょうか?
川村:作るという行為は、映画だったら撮影とか編集とか、小説だったら文体とか描写とかがあるわけです。けれども尊敬している作家たちと話していて感じるのは「どう表現するかよりも、何に気付くかのほうがはるかに大切である」ということでした。つまり何を受信しているかが、表現する人にとって一番大事なことなのかなと。ここがズレていくと、誰にも届かないし、そもそも面白くないものが出来上がっちゃう。その周波が世間とズレていくのが一番怖いです。ありがたいことに僕の周りには小説家、マンガ家、俳優、ミュージシャンなどものすごく受信力が高い才能がたくさんいる。彼らから受ける刺激のおかげで小説が書けているとも言えます。
ほかにも脚本家、映画監督、カメラマン、スタイリスト、美術デザイナー、そういう人たちと毎日、毎日ああだこうだと話しながら映画を作っているので、最先端の感性に触れられるという意味では相当恵まれていると思います。しかも運が良いことに、10代や20代の人たちと毎日のように接点があるので、それは自分にとって武器になっているのは間違いないです。今のティーンエイジャーの歌手が何考えているかなんて、年を取れば取るほど分からなくなっていきますから。
ただ、年齢や職種関係なく、時々惑星直列みたいに、皆が同時に同じようなことを感じている瞬間があるんです。そのときに、「ああ、今はこれを書くべきなのだ」と感じる。自分が考えていることが世間とバッチリ接続しているかなんて、誰にも分からないですよね。というか分かってやっている人はいないんじゃないかな。そう言う意味では、自分が感じているのと同じことを、この人は音楽で表現していて、この人はマンガで表現していて、この人はお芝居で表現していると思ったときに、やっぱり自分が考えていることは間違いじゃないって思えるというか……。
「私はこう思っていたんだ」物語の役割
川村:自分で書いたものが面白いかどうかは分からないのですが、今回の小説『神曲』に話を戻すと、全国の書店員の方々からの感想をまでで一番たくさんいただいているんです。もう100通を超える感想をいただきました。しかも、みんな自分の話を書いてくれるんです。私はこうだったとか、うちの家族が似たような状況だったとか……。
——この小説を読んで「俺の家の話」を喋りたくなる気持ちはすごく分かります。
川村:おそらくなんですけれど、コロナ禍の間に、たまっていっちゃった澱(おり)のようなものがあるんでしょうね。その正体が自分でも分からないし、どうしたらいいかも分からなくて鬱々(うつうつ)としちゃう人も少なくないと思うのですが……。
小説の良さって自分の外の世界をファンタジーとして楽しむというのもあるのでしょうが、「私はこう思っていたんだ」「こういうことが怖かったんだ」「私はこれが嫌だったんだ」もしくは「これがうれしかったんだ」ということに気付くのも物語の役割だと思っています。この本を手に取った人にそんなふうに自分にとっての「信じられるもの」を見つけていただければうれしいですね。
(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)