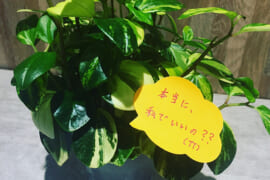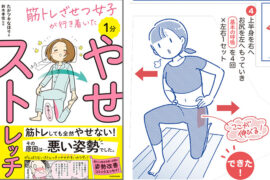仕事もある程度経験が積み重なってくると「マネジメント」や部下や後輩の育成を求められることも。いきなり「マネジメント」と言われても何をすればいいの?と戸惑う人も多いのではないでしょうか?
人材紹介、人材派遣会社向けに、業務効率化システムの開発・販売をしている「マッチングッド株式会社」でセールス・マーケティング部マネージャーをしている北村純さん(27)。20代でマネジメント業務を担当しています。
前編では、教育学部に通い「公務員になるんだろうな」と思っていた北村さんが「外の世界」に出てみて見つけたキャリアのきっかけについて聞きました。後編では、マネジメントのやりがいについて聞きます。
2年間の「ブランク」がコンプレックスだった
——帰国されて今の会社(マッチングッド)に入られた経緯は?
北村純(以下、北村):帰国前から一般企業で働こうと決めて仕事を探していたんですが、教育以外で探すと未経験から覚えるものしかないなと思って。だったら、営業職であればいけるんじゃないかと思ったんです。
とはいえ、教育分野に携わっていたこともあって、人と接することは好きだったので「人材」と「営業」という二つの軸で仕事を探してました。
——就活はどうでしたか?
北村:今の会社以外にも大手企業も受けて内定も頂いたんですが、新卒でアフリカに行ったことで、同世代と比べて日本でのキャリアにブランクがあることがコンプレックスだったんです。だからその2年間を早く埋めたい、早くキャリアアップしていかなきゃという思いがあったんです。
そして、大手企業の面接で話してると、何となく「決まった仕事をやるのかな」と思って。人事担当の人と話してても、そういう印象が強くて、そちらを選んだら選んだで今とは違う道があったとは思うんですが……。
そういう気持ちを抱えていたところに、今の会社からスカウトメールがきたので、「ベンチャーも一社受けてみようかな」と、気軽に面接を受けたんです。
面接を受けてみたら、社員がみんな個性が強くてバラバラで(笑)。こんな個性がバラバラの人達がどういう職場で働いてるんだろうと思って興味を持ちました。
——それで今の会社に入ることにしたんですね。入社してみていかがですか?
北村:すごく楽しいですね。それぞれのスキルを持ってる人がそろっていて、みんなそれぞれ違うバックグラウンドを持っているので勉強になるし、違うキャラクター、個性を持った人たちが、一つのシステムを作り上げるというのにやりがいを感じます。
——ベンチャーっぽいなというところは?
北村:やはり風通しがすごく良いですね。同じフロアで、社長と営業、デザイナー、開発が密にコミュニケーションを取れる環境で働いていて。それもすごく好きですし、あとは、会社の体制やルールについて「これはこうなんじゃないの?」という部分も全体ミーティングで「じゃあそれでやってみたら?」とすぐにガラリと変わったりもするので刺激的です。
——今は自身の営業の仕事とマネジメントをしているんですか?
北村:そうですね、営業部のマネジメントをしていて、今はマネジメントのほうが比率は高いかな。
——アラサーになってある程度経験が積み重なってくると、会社から「マネジメントやれ」って言われることも多いと思うんですが、私、マネジメントってどういう役割なのかいまいちピンとこないんです。
北村:今、面倒を見ている後輩が5人いるんですが、私がやっていることとしては、入社してからどういうふうに営業していくとか、商品やサービスの知識の研修をする、とかですかね。
あとは、研修期間は経てはいるんですが、「こういう見込みのクライアントがいるんだけれど、どういうふうにアプローチをしたら良いか?」というのを個別ミーティングで話したり……というのがメインの仕事ですね。
マネジメントってどうやるの?
——正直、「マネジメント」って面倒くさいなって思っちゃうんですが、誰かに「マネジメントってこうやるんだよ」と教えられたんですか?
北村:教えられてはないですね。ただ、私の上が代表なので、代表から「こういうところはこういうふうにやったら良いよ」というのは、適宜アドバイスはもらっています。
あとは、アフリカの経験がいきていますね。向こうでは日本人の私が1人で現地教員の中に入って行ったんです。「情操教育」というのがまったく普及していなくて、それを普及させるために私たちが派遣されるという意味もあって。
現地の教員を(体育の授業で)グラウンドに連れて行こうとすると、「外は暑いから、勝手にやっていいよ」と言われるんです。でも、それだと私が帰ったあとは前と同じ状況になってしまうので、現地の教員を巻き込んで後継者というか、インフルエンサーを育てなければならないというミッションもあったんです。
マネジメントも、自分がするだけでなく人にしてもらうという点では似たものがあるのかなと思いました。1回言っただけではやってくれないことも繰り返し言い続けてやってもらうこととか、相手の視点になって考えるということは経験がいきているのかなと思います。
アフリカに比べれば日本はラク
——ここでアフリカが出てくるとは思いませんでした。ザンビアでは英語を使っていたんですか?
北村:英語だったんですが、地方だったので現地語だったんですよ(笑)。
——ひえー、現地の言葉……。
北村:現地語は単語を覚えて。教員は英語でコミュニケーションを取れるんですが英語が話せない低学年の生徒や、親御さんもいたので、現地語を使ってという感じでしたね。
——すごく大変そうですね。
北村:今考えると楽しかったです。アフリカの2年間でだいぶ動じなくなったというか図太くなったと思います。
——それに比べると日本人なんて全然ラクという感じですか?
北村:はい、それはすごく思います。言葉も通じるし、あとは環境も同じですし、価値観とかも違えどだいたいは似てるので。そういった点で、アフリカに比べたら日本は何て過ごしやすいんだと。
——そうか……。先ほど「2年間のブランク」っておっしゃってましたけど、ちゃんと経験がいきていてブランクなんて吹っ飛んじゃってますね。
北村:今振り返ると、良いほうにきてるなと思います。やはりアフリカに行ってるときはブランクだなと思って、コンプレックスを抱いてたんですけど、今の会社に入ってもうすぐ2年になるんですけど、良いほうにきてるなと思います。
——アフリカの話をもう少し聞きたいんですが、教えてた子どもは小学生くらいですか?
北村:小学生から中学3年生までですごくかわいいですよ。
——話を聞かない子とかいました?
北村:います、います。授業中にポップコーン食べてたりとか(笑)。でも、そうは言っても「将来」は気にしていて「試験に受からなきゃいけない」とは思っているので、数学だけは勉強するんだけれど、体育は遊びって思っている。順番を守らなかったりとか、真っ直ぐ並べなかったりするので、そこの教育からですね。
——「若い女性」だからとなめられることは?
北村:なめられちゃいますね。日本人を含めて白人は学校を設立したり、助けてくれたりするものだと思っている部分もあって、私が赴任したときも「ボールちょうだい」とか、「モノをちょうだい」とか、「水をちょうだい」とか普通に言われるんです。
彼らからすると私も白人の一人で、白人は怒らない、という捉え方もされていたので、「私は違うんですよ」って言って、頼まれてもものをあげなかったりとか、「あげる代わりに、絶対これはしてね」と伝えたりして、分かってもらうところからはじめました。すごくタフになったかなと思います。
強みを伸ばして弱みは是正していく
——アフリカでの経験が本当にいかされているんですね。マネジメントに必要なものは何だと思いますか?
北村:代表からもよく言われてることなんですけど、「是正と強化っていうのをキーワードとして常にやれ」って言われていて。
下に5人もいると、それぞれで強みも違いますし、弱みも違いますので、強みは伸ばしていく、弱みは是正していく。そうなると、5通りの是正の仕方と強化の仕方があるので、それぞれにどの方法が良いのかっていうのを模索するのが、大変でもあり楽しくもありますね。
——すごく勉強になりました。最後に今後やっていきたいことを教えてください。
北村:今やらなきゃいけないのは、下にいる5人がしっかり一人でバンバン売れるようになることと、ゆくゆくは営業を増やす方針ではあるので、増やしたときに、そのマネージャー、次のマネージャーっていうのを抜擢できるような人を育てていきたいです。
——社会人でもやりたいことが分からない人も多いと思うんですけど、そういうふうに悩んでる後輩に一言声を掛けるとしたら、どういう言葉をかけますか?
北村:そうですね。私の場合なんですが、昔は「どの仕事に就きたいか?」という視点で考えていたんです。でも、そうなるとそのときの自分が置かれている状況から選択肢を考えることになって、私の場合は地方に住んでいたので、選択肢も限られているんですよね。
そうではなくて、何ができるようになりたいかとか、何をしたいかという点からちょっと広げていくような考え方をすれば、いずれは見つかるんじゃないかなと。“あの頃”の自分に言うとしたらそれですね。
——外に1回出てみるっていうのも良いかもしれませんね。
北村:そうですね。やはり触れる人や場所をガラリと変えると、それだけ選択肢が生まれるので、外に出ることはそういった意味ではすごく刺激的なことだと思います。
(取材・文:ウートピ編集部・堀池沙知子、写真:宇高尚弘/HEADS)