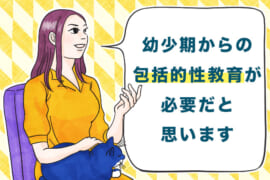胃がキリキリと痛む、重苦しいなど、検査では異常なしと言われたのに原因不明の胃痛で悩む人は多いと言います。ドラッグストアの棚に並ぶ胃薬の説明を読み比べても、どう違うのかがよく分からず、何を選べばいいのか悩むことはありませんか。
そこで、大阪府薬剤師会理事で薬剤師の近藤直緒美さんに、胃痛ケアの市販薬の選びかたについて聞いてみました。
過度なストレス、食生活や生活リズムの乱れなどが原因
みぞおちのあたりが重く感じる、少し食べただけで満腹感があり食事が進まないなどの症状があるときについて、近藤さんはこう説明します。
「検査では異常なしと言われたけれど、なぜか不快な症状がときおりある、数日続くというときは、食べ過ぎ飲み過ぎやストレス、不規則な生活、疲労などに思い当たらないかを自問してみましょう。その上で、胃痛の主な原因は次の3つが考えられるので、それらに応じて市販の薬を試してみるといいでしょう」
(1)胃酸と胃粘液の分泌量のバランスが崩れる
通常、胃では、食べ物を消化する「胃酸」と胃酸から胃の粘膜を守る「胃粘液」が、バランスよく分泌されています。しかし、過度なストレス、緊張、食べ過ぎや飲み過ぎ、食生活や生活リズムの乱れ、疲労、喫煙、薬剤の服用、感染症などが原因でそのバランスが崩れると、「胃酸が過度に分泌する」、「胃粘液の分泌量が減少する」などで、胃の粘膜が傷つくことがあります。
これが、シクシクやキリキリ、ズキズキとした痛み、胸やけ、むかつき、胃もたれなどの症状を引き起こします。また、胃の粘膜が傷ついた状態が長く続くと、「慢性胃炎」や「胃潰瘍(かいよう)」になることもあります。
(2)胃のけいれんが影響する
強いストレスを受けているときのほかに、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、膵炎(すいえん)などの病気の場合、みぞおちのあたりを中心に、数分~2時間ほど続く激しい痛みの発作が起きます。胃壁にある筋層が異常に緊張することで胃がけいれんしているような痛みを感じますが、これは胃の不快な症状の一つであり、病名ではありません。
(3)胃腸機能の低下が影響する
胃そのものに原因となる病気がないにもかかわらず、慢性的な痛みや胃もたれなどの症状が起こる場合は、胃腸の機能が低下している「機能性ディスペプシア」(かつては「神経性胃炎」と呼ばれていました)と呼ぶ病気の場合があります。
食後に症状が現れることが多く、肉体的、精神的なストレスや加齢が原因で自律神経のバランスが崩れ、胃の働きを妨げて不調を起こすと考えられています。
いつどんなときにどう痛むかを考えて、対応するタイプを選ぶ
では、薬局の店頭ではどのように薬を選べばいいのでしょうか。近藤さんはこう話します。
「胃薬には、『胃酸の分泌を調節する』、『胃の働きを活発にする』、『消化を助ける』、『胃の粘膜を保護する』など、さまざまな種類があります。
原因や症状に合った種類を選ぶことがポイントですが、成分名を覚えるのは難しいと思われるので、薬の種類を確認してください。具体的には、次のような表示があるタイプです」
(1)胃酸分泌抑制薬(H2ブロッカー薬やM1ブロッカー薬など)……胃痛、胸やけ、胃もたれ、むかつきがあるときなどに
胃酸の分泌の促進をブロックし、胃酸が過剰に分泌されないように働いて、胃の粘膜が傷つくのを防ぎます。長時間、効果が持続します。
主な市販薬の種類:アシノンZ(ゼリア新薬)、アルサメック錠(佐藤製薬)、アルタットA(興和)、大正胃腸薬Z(大正製薬)、ガスター10(第一三共ヘルスケア)など。
(2)制酸剤……食後に胃が痛む、ゲップがよく出る、むかつき、飲み過ぎがあるときなどに
出過ぎた胃酸を中和して胃の粘膜を保護します。即効性がありますが、作用は一時的です。
主な市販薬の種類:サクロン(エーザイ)、第一三共胃腸薬コアブロック(第一三共ヘルスケア)、パンシロンAZ(ロート製薬)など。
(3)胃粘膜保護剤……空腹時の胃痛、吐き気、胸やけのときなどに
傷ついた胃の粘膜を保護し、修復するのを助けます。また、消化吸収時の負担を和らげます。
主な市販薬の種類:新センロック錠(第一三共ヘルスケア)、スクラート胃腸薬(ライオン)など。
(4)消化剤……食べ過ぎ、脂っこいものを食べたあとの胃痛、胃もたれなどに
胃の中に留まっている炭水化物や脂肪を分解する消化酵素と同じ働きを持つ成分の作用で、消化吸収を助けます。
主な市販薬の種類:太田胃散A(太田胃散)、第一三共胃腸細粒(第一三共ヘルスケア)、ハイウルソ顆粒(佐藤製薬)など。
(5)健胃剤……普段からしばしば食後に胃痛や胃もたれを起こしやすいときに
胃の働きを活発にし、消化を促すために胃酸の分泌を促進します。
主な市販薬の種類:セルベール(エーザイ)、大正漢方胃腸薬(大正製薬)など。
(6)総合胃腸薬……多くの症状に心当たりがあるときに
「胃粘膜保護成分」や「消化成分」、「健胃成分」など複数の胃薬の成分がバランスよく配合されています。(1)~(5)のさまざまな症状があり、胃の不快感を和らげたいときに使用します。
主な市販薬の種類:キャベジンコーワα(興和)、太田胃散(太田胃散)、第一三共胃腸薬プラス(第一三共ヘルスケア)、パンシロンAZ(ロート製薬)など。
(7)鎮痛鎮痙(ちんけい)剤……強いストレスや緊張で、けいれんするような発作的な激しい胃痛のときに
胃腸の異常な運動や緊張を和らげて、痛みを鎮めるように働きます。
主な市販薬の種類:コランチルA(塩野義製薬)、サクロンQ(エーザイ)、ストパン(大正製薬)、ブスコパン(エスエス製薬)など。
(8)漢方薬……原因となる病気がないにもかかわらず、症状が長引いて胃腸機能の低下が考えられるときに
漢方薬は、胃と腸の働きをひとつの症状ととらえ、体質と症状によって選びます。
主な市販薬の種類:冷えがあって胃腸が弱い場合は「半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)」(ツムラ、クラシエなど)や「六君子湯(りっくんしとう)」(ツムラ、クラシエなど)、ストレスが強い場合は「安中散(さんちゅうさん)」(ツムラ、クラシエ、武田薬品工業など)など。
最後に近藤さんは、胃薬を服用する際の注意事項について、こうアドバイスを付け加えます。
「薬の種類によって、服用するタイミングは異なります。胃の働きを活発にする『健胃剤』は食事の20~30分前に服用する『食前』に、食べた物の消化を促す『消化剤』は『食後』に服用するのが一般的です。
さらに、『胃酸分泌抑制薬』や『制酸薬』、『胃粘膜保護剤』は、胃の中が空っぽに近い、食事をして約2時間後の空腹時の『食間』に服用する方が、成分が作用しやすくなります。
原因がよくわからないときは一度『総合胃腸薬』を試してみるか、ドラッグストアや薬局に常駐の薬剤師に相談してください。また、症状が長引くときは再びの検査が必要なこともあります。異常を感じたら、早めに医療機関を受診してください」
胃薬と言ってもさまざまな働きを持つ種類があることが分かりました。まずは具体的な症状や心当たりがある原因、日頃の生活習慣、自分の体質を振り返りつつ、適切な薬を選択する必要があるということです。
※2017年6月現在の情報です。
(取材・文 岩田なつき/ユンブル)