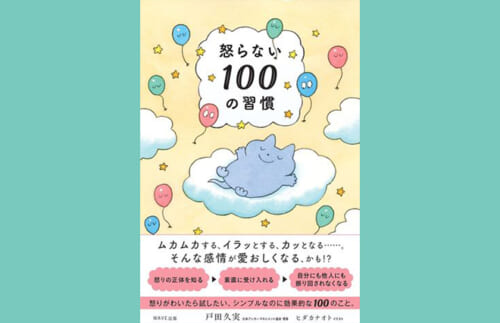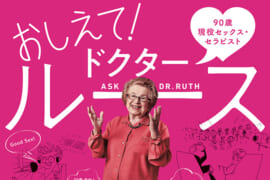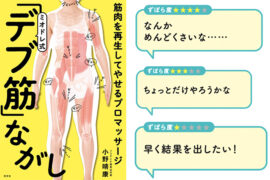「産むことのメリットとデメリットを教えてください」今年で33歳になるワーカホリックなプロデューサーが、ワーママ編集長に詰め寄ったことからスタートした本企画。第4回のテーマは、「産むと、まわりの目はどう変わるのか?」です。
私が大きな仕事を任された理由
私は娘が1歳になる頃に会社を辞めて、独立しました。
新しく刷り上がった名刺をもって、ある男性に挨拶に伺った時のこと。その方は、私にとってメンターとも言える大切な存在で、歳は親子ほど離れているのですが、数ヵ月に一度会っては仕事のこと、プライベートのこと、ほぼ何でも話し合える間柄です。
その方は開口一番こうおっしゃいました。
「お子さんも生まれて、本気になったでしょう。鈴木さんの夢は全面的に応援しますよ」
そして、彼はその場で大きな仕事を私に任せてくれました。
「子どもができて、この人は本気になった。どんな大変なこともやり抜くだろう」というのが、その方の判断だったわけです。
「子どもがいて一人前」という価値観はまだある?
他にも、こんなことをおっしゃる方もいました。
「仕事で誰かに背中を預けなきゃいけない時、私なら、必ず子どもがいる人を選びます。子どもがいない人は逃げるかもしれない。でも、子どもがいる人は絶対に逃げない」
こんなことを口にするのは、よっぽど昭和の遺物みたいな人だろうと想像するかもしれません。でも、そうじゃないんです。彼は50代で女性の活躍を心から応援している、とてもリベラルな信条の持ち主でした。そんな彼がある時、「仕事の極意」としてこっそり教えてくれたのが、先に挙げた言葉だったのです。
二人とも、業界は違えど、一流と呼ばれる世界で戦い抜いてきた百戦錬磨の方々。私が編集者として出会った中で、特に尊敬している方々です。そういう男性たちが共通して、「子どもがいる人の方が信用できる」という価値観をもっている。今や目に見えにくくはなっているけれど、やっぱり、社会のどこかに「子どもがいて一人前」という感覚は根強くあるんだと思います。
「ある」のに「ない」とされていること
こんな話を書くと、ワーカホリックな海野Pはきっとこう言うでしょう。
「大きな仕事を任されるようになるんですか!? だったら、産みます!」
だがな、海野P、物事はそんなに単純ではないのです。仮に「子どもがいる方が信頼される」という事実があったとして、そのために産んだとしましょう。言っときますけど、そんなモチベーションじゃ、この生活には絶対に耐えられませんから。そんなよこしまな心では、「自分」というものを奪われまくるこの日々を受け入れることはできませんから。
「子どもを産んだら、信頼度が上がる」のは、本当です。とりわけ、シニア層や保守層からの信頼は厚くなります。なんだかんだ言っても、「あなたはこっち側の人間よね」と認識されるわけです。しかも、そういう層がえてして組織の決定権を握っていたりします。
だから、それを「メリット」として挙げることもできるんですが、でも、そのために産むのなんて完全にバカげてるし、何より私自身が「メリット」として認めたくないんです。
プロローグで書いたように、私は産んでからかえって「産まない人生も、断然あり」と強く思うようになりました。自分のために持ちうる時間とエネルギーのすべてを使いきれる人生は、素晴らしいに違いないのです。なのに、女性はいまだに「産まないの?」という無言のプレッシャーにさらされているし、それを知らずのうちに内面化して、「産んどいた方がいいかも」と考え始めてしまう。
2017年の時点で、女性にとっては「産む人生」を選択する方が、「産まない人生」を選択するよりラクです。それは言うまでもなく、無言のプレッシャーが存在するからです。そして、「子どもがいる人の方が信頼できる」という価値観も、そうしたプレッシャーの一部をなしています。
だから、さっさと消えてなくなってしまえばいいんです、「子どもがいる方が信頼できる」なんて価値観は。自分は大きな仕事をもらっといてナンですが、心からそう思います。
というわけで、今回はメリットともデメリットともつかない話になってしまいましたが、こういう、明白に存在しているのに「ないものとされていること」について書くのが私の仕事かな、と考えているので書いてみました。
(ウートピ編集長・鈴木円香)