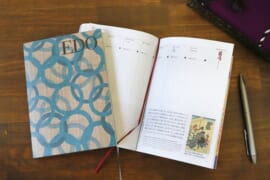小津安二郎監督の「東京物語」、尾道三部作と呼ばれる「転校生」「時をかける少女」「さびしんぼう」の他、多くの映画のロケ地であり、「映画の町」として全国的に知られる広島県・尾道市。ところが、2001年に最後の映画館が閉館し、「映画館ゼロの町」になってしまいました。
そんななか、NPO法人「シネマ尾道」を立ち上げ、「映画の町」を復活させようと奮闘する河本清順(かわもと・せいじゅん)さん。もともとはアパレル業界で働いていたという彼女がひとり、映画の世界に飛び込んで見えてきたものとは?
「映画館ゼロの町」で映画を観たい
──実は最初は、尾道が「映画の町」だと言われていることすら知らなかったそうですね?
河本清順さん(以下、河本):そうなんです。高校まで尾道で過ごし、京都の服飾専門学校に進学しました。郷里から外に出て初めて尾道が「映画の町」だと多くの人に認知されていることを知りました。
──映画館の支配人になる前は焼肉屋さんの経営に?
河本:卒業後、京都のアパレル企業に勤めていたのですが、母が尾道で焼肉屋を始めることになり、実家に戻って、姉と一緒に経営に参加したのです。19歳から36歳まで足掛け17年間、焼肉屋で働きました。父親は鉄工所の経営者です。起業家一家ですね。
──それがまたどうして映画館経営に?
河本:2001年に最後の1館が閉館して、尾道は「映画館ゼロの町」になってしまいました。最初は単純に自分の町に映画館がほしいと思ったのです。
映画館を1館維持していくには30万人以上の人口がないと無理だと言われていました。尾道の人口は当時15万人ほど。でも、調べてみると、埼玉県の深谷市のように、尾道と同規模の小さな町でもやっていけている例があることがわかり、だったら自分たちで何とかしなければという使命感が湧いてきたんです。
開館から8年、ようやく軌道に乗り始めて
──NPO法人による映画館っていうのがユニークです。
河本:ただ映画館を復活させればいいのではなくて、それによって町の人の文化的なものに対する意識を再生するのが目的だと考えました。つまり町に貢献する、公益性のある事業だと。個人で商売するのとは違うということで、NPOとして始めました。
2006年10月にNPO法人シネマ尾道を設立し、市民からの寄付を募って、2008年10月に開館の運びとなりました。オープンの時に全国ネットのニュースが取材に来て、初めて尾道に映画館ができるって、大変なことなんだなと実感しましたね。
──開館から8年経ったわけですが、現在の状態は?
河本:有給のスタッフは私を入れて4人。その他、15〜20人のボランティアの方に受付業務などをローテーションでお手伝いいただいています。
数年前にデジタル化の問題(2014年4月でフィルムによる配給は終了し、全国の映画館が高額なデジタルシステムの導入を余儀なくされた)で経営危機になったりしましたが、そこはクラウドファンディングを募って乗り切りました。なんとかギリギリの線で経営できています。映画館は日銭が入るので、その点は強みと言えますね。
一つの映画館で町が変わっていく
──ご本人の働きか方に変化はありましたか?
河本:シネマ尾道の開館から約4年間は、スタッフはほぼ私と副支配人の2人だけだったので無休で働いていました。約4年前からようやく週一で休みが取れるようになり、木曜日に休んでいます。でも、結局休みの日にも映画館に来て、お客さんと一緒に映画を観たりしていますけどね(笑)。
もともとが映画マニアではなかったのですが、今は年間140本の上映作品を含め、試写用のDVDなどで年間400本くらいは観ています。それはまったく苦になりません。
──「映画の町」の命運を背負ってしまったように見えますが、そのわりには楽しそうですね。
河本:映画館ができて町が活性化したと言われるのが一番嬉しいですね。シャッター街だった駅前の通りにお店が新しく開店したり、近所のパンさんが映画にちなんだ新作パンを売り出してくれたり。介護関係の会社から上映映画の推薦があったことも。
教育委員会と組んで、「東京物語」(1953年公開、尾道を舞台にした小津安二郎監督の名作。主演は笠智衆と原節子)を尾道の小中学生に観てもらおうという取り組みも始めました。現在年間1万5000人の来館者がありますが、ゆくゆくは地元の方全員に年に1回は映画を観
に来てもらうようにしたいです。
朝7時に起床。9時出勤。ランチは、近所から買ってきて簡単に済ませたり、打ち合わせをしながら食事をしたり。夕食も外で会食することが多い。映画館を出るのは早くて18時、平均して19時。上映後に次の週末から始まる映画のテストをする場合は深夜0時まで仕事をしていることも。