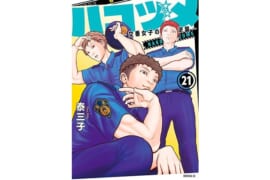慶應大学を卒業し、国家公務員の官僚コースへ進むという、いわゆる「エリート街道」を歩んできた小林味愛(こばやし・みあい)さん。かつては「鉄の女」と呼ばれるほどの仕事人間でした。
小林さんは国家公務員から民間企業へ転職し、転職先では心身の不調に苦しみ、逃げるように退職。次の当てのない生活をしている中で、小林さんの進む道となってくれたのはかつて仕事で出会った福島県の人たちでした。
現在は、「株式会社陽と人(ひとびと)」の代表として活動。福島県の農産物を活用したフェミニンケアブランド「明日 わたしは柿の木にのぼる」を立ち上げ、東京と福島での二拠点生活を送っています。
「20代の頃は他人と自分を比べてばかりいたけれど、レールから外れても大丈夫だと思えるようになった」と語る小林さん。インタビュー後編をお届けします。
キャリア官僚時代には知らなかった喜び
——国家公務員を辞め、大手コンサルティング会社も辞め、やりたいことも見つからない状態で福島へ行って、起業に至ったそうですが、なぜ福島だったのでしょうか。出身地は東京ですよね?
小林味愛さん(以下、小林):コンサルティング会社にいたとき、福島県の国見町の行政と組んで様々な仕事をしていました。おいしい食べ物や豊かな自然そして優しくて実直な人々に出会って、仕事を辞めたあとも福島へ遊びに行っていました。
そのとき出会った農家の人から規格外で廃棄処分になってしまう桃があるという話を聞いたんです。そこで、私が桃を買い取って東京に送って、路上で手売りすることにしました。
――えっ……。手売りってサラッと言いましたけど、梱包とか配送とか、すごく手間がかかるのでは?
小林:そうなんです。最初はどんなコストがかかるか全く知らなかったから(笑)。桃を東京に送るために宅急便を使ったんですけど、送料がすごいことになって。それだと手頃な価格で売れないので、送料を落とすための方法や、桃が傷まないように運ぶ方法を一つひとつ考えていきました。
自分で物を売ってお金を稼ぐのは想像以上に大変でしたけど、私はすごく楽しかった。「エリート」って言われて無理して長時間働くより、初めて会った人が、私が運んできた桃を買って喜んでくれたほうがずっといい。「ああ、私、生きてるなぁ」って感じられた瞬間でした。
柿の皮から発見した保湿成分で、デリケートゾーンをケア
——桃を手売りした経験から、どのように起業につなげていったんですか?
小林:最初から起業したいと思っていたわけじゃないんです。福島に遊びに行って、地元の農家の方々とたまたま気が合って、話をするうちに「じゃあ今度、こういうプロジェクトをやってみようよ」っていう話になりました。
でも私は、自分の身の丈に合った、関わってくれる一人ひとりを大事にできるような仕事をしたいと思っていたから、既存の組織に入って働くイメージをなかなか持てなくて。それなら起業するのもいいかもしれないと思って「株式会社 陽と人(ひとびと)」を立ち上げました。
そこから規格外の農産物を都市に流通させる仕組みを作ったり、地域資源を活用した商品を企画したりするようになって、今に至ります。
1日10秒でもケアしてもらえたら
——なるほど。小林さんが企画・開発したフェミニンケアブランド「明日 わたしは柿の木にのぼる」も、地域資源を活用した商品の一つですよね。
小林:地元の農家さんに、「干し柿の製造途中で柿の皮が大量に出るけれど、活用方法がなく捨てるしかない」と聞いたんです。そこで、皮を捨てずに済む方法を探ろうと、成分を科学的に証明するための実験と研究を始めました。すると、柿の皮に有効な成分があることがわかったんです。3年かけて、デリケートゾーン用のソープやセラム、オイルなどの商品を作りました。
——なぜデリケートゾーンに注目したんですか?
小林:実は私自身、国家公務員時代から婦人科系の症状に悩んだ経験があったんです。生理が順調に来る人なんてこの世にいないと思っていたぐらい、生理不順が当たり前でした。そのとき、デリケートゾーンをケアする大切さを初めて知ったんです。
デリケートゾーンには約500種類の菌が日々バランスを保ちながら存在しているんですよ。でも、睡眠不足や過度なストレスが重なると菌のバランスが崩れて、かゆみやにおいなどの症状が現れるんです。つまり、デリケートゾーンは女性にとって健康のバロメーターなんです。
だから、1日たった10秒でもデリケートゾーンのケアをしてもらえたら、という思いで商品を作りました。「もう少しで病気になっちゃうかも」っていう体からのSOSを察知できるようになったら、女性が自分の体と心を今まで以上に大事にできるのではないかと思って。
——なるほど。フェミニンケアアイテムを作れば売れるだろう、ということではなく、目の前にある資源と、ご自身が経験した悩みが繋がったんですね。
小林:そうですね。製品を先にして、それらをなんとかして売ろうと考えるのはいつか限界が来ると思うんです。作る側、使う側にとって本当に必要なものを考えて企画・開発を行いました。
好きなことと稼ぐことは両方必要
——小林さんのように、自分に合った環境で好きな仕事ができたら、と思う人は大勢いると思うんですが、収入面についてはどう考えていますか?「やりたいことを優先して収入を我慢する」という働き方もありますが、それだと長く続けるのは難しいですよね。
小林:そうですね。やりがいと稼ぐことはどちらかではなく、どちらも諦めないで欲しいと思います。私の仕事で言うと、社会性と経済性を両輪で回していくのは、難しいチャレンジだと思います。お金を払ってもらうって、想像を遥かに上回る努力が必要なんですよね。金額に見合ったアウトプットや、付加価値が必要とされるから。
でも、一時的なボランティアじゃ意味がない。地域の役に立ち続けるには、ビジネスを生み出して経済を回していかなければならないんです。今はとにかくお世話になっている農家さんに迷惑をかけないよう、つまり、しっかりと継続していけるように責任感を持って仕事を進めています。
——かつては、稼ぐことに罪悪感があったとおっしゃっていましたが今はもうない?
小林:そうですね。何のために何をして稼ぐのか、自分で納得しているので。抜け出せたと言っていいと思います。
——もし以前の小林さんのように、自分のやりたいことがわからなくなってしまった人、新しく挑戦する「何か」を探している人がいたら、どんなことを伝えたいですか?
小林:場所を変えてみたらどうかな、って提案したいですね。私も東京から福島へ行って、価値観が全く違う場所で過ごして、自分に何ができるのか、どんな時に喜びを感じるのか知ることができました。太陽が出たら起きて、暗くなったら家に帰って寝る。そういう生活に人間らしさを感じるような自分を肯定していいと思えたんです。
悩んだときは、今まで自分が生きてきた環境とは全く違う環境に一度身を置いてみる。簡単なことではないかもしれませんが、もしできそうなら、試してみてほしいです。自分の世界を広げるには、まず自分が動くことがいちばんだと私は思います。
(取材・文:華井由利奈、編集:安次富陽子、写真提供:株式会社陽と人)