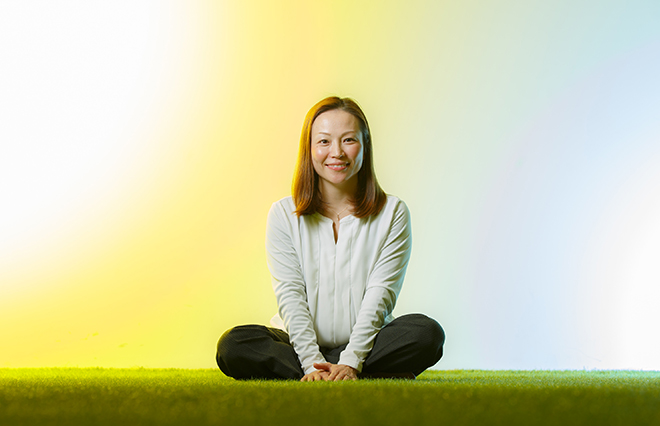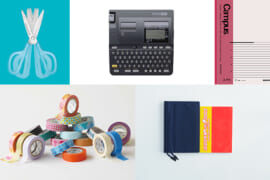新卒でベンチャー企業に入社し、バリバリ働いたのち大学院に入学。学生とフリーランスという2足のわらじ生活をするも、博士課程終了前に妊娠出産、専業主婦へ……。そして現在はフリーランス協会の代表理事を務める平田麻莉(ひらた・まり)さん。
「自分で決めたことにも、環境に流されてみたことにも等しく価値があった」と平田さんは言います。それは、あるキャリア論に影響を受けているのだとか。そのキャリア論とは?
「なりたい」より「目の前のこと」
——その時々の選択を大事にした結果が今だとのことですが、するとやっぱり現在の仕事も“目指して”いたわけではないんですよね?
平田麻莉さん(以下、平田):はい。何か組織を作りたいと思っていたというより、シンプルに目の前の社会課題を解決するには、フリーランス協会が必要だと思ったんです。
というのも、フリーランスとして8年働いて、この働き方をとても気に入っているのですが、困りごとも多くて。たとえば、何かあった時に自分の代わりになってくれる人がいない。育休・産休がないし、保活でも不利になりやすい。同じように困っている人も多いはずだ、と思ったことがきっかけです。
さらに、シェアリングエコノミーやクラウドソーシングなどの発展で、フリーランスとして活動する障壁も下がってきて、フリーランス人口も増えているので、困りごとを解決する仕組みをアップデートするなら今だな、と。それを話したら、SNSのコメント欄やランチ会で盛り上がって。フリーランスで働いている人のリアルな声を集めて、社会に届けられる場所を作ろう、という流れになりました。
——ランチ会が行動するきっかけに?
平田:そうですね。困りごとや興味関心のあることにアンテナを張っていると、「あ、今やらなきゃ」って思うタイミングがあって。その時はそのランチ会がそうでした。なんというか、オポチュニティ(機会)をキャッチしやすいのだと思います。
計画的偶発性理論って?
——でも、私だったら「今だ」と思っても、そこまで行動できるかどうか……。
平田:ランチ会の段階では、「協会」という形は想像もしていませんでしたよ。でも、どんどん目の前の機会をこなしていくうちにこの形になった。キャリア理論のひとつに「計画的偶発性理論」(プランドハップンスタンスセオリー)というものがあるのをご存知ですか?
——スタンフォード大学のクランボルツ教授が提唱したものですよね。名前は聞いたことがあります。
平田:「個人のキャリアの8割は予想しない偶発的なことによって決定される。その偶然を計画的に起こしてキャリアをより良いものにしていこう」と、クランボルツ教授は言っているんです。大学院時代、ある人に「平田さんの生き方はプランドハップンスタンスだね」って教えてもらって、確かにと思いました。
——うーん。でも、偶然と計画はそもそも対極にあるような……。
平田:前回、私は「キャリアを棒に振る」ことにも価値があるとお伝えしました。それはこの「計画的偶発性理論」に影響されているところがあって。キャリアに限らず、人生全般において、ほとんどのことが計画通りにはいきませんよね。
やりたい仕事や、一つの目標に向かって頑張ることは素晴らしいことですが、その一つにこだわることで、他の選択肢に向かう機会を失っているとも考えられます。こんなにスピードの速い現代で、一つのことだけにこだわるのはリスクかもしれませんよね。
——確かにそうですね。
平田:私の場合、専業主婦になったこと。ずっとバリバリ働きたいと思っていたけれど、産んだら少しも予想しなかった価値観革命が起きた。そして、子育てに集中した期間や、子育てから得たものが自分のエッセンスとなって、現在の仕事に生きています。それはあの時の「偶然」によって決まったのかなと思います。
計画的な偶然を起こす5つのポイント
——偶然は「果報は寝て待て」でもいいですか?
平田:どうでしょう(苦笑)。ただ待つだけでなく、チャンスを自分で創り出せるようにすることが大切な気がします。それが「計画的」ということなんですけど。具体的には、行動したり、周囲にアンテナを張ったりすること。実践する時は5つのポイントがあります。
——ぜひ教えてください。
平田:好奇心、持続性、楽観性、柔軟性、冒険心の5つです。まず、好奇心を持って常にアンテナを張ってデータを貯めておくこと。
——アンテナを張る時に、平田さんが気をつけていることがあるそうですね。
平田:はい。情報収集源に偏りがあると、アウトプットも偏ってしまうので、異業種とか、考え方が真逆の人の声もインプットするようにしています。私は学生時代から掛け持ちグセみたいなものがあって、サークルを4つ掛け持ちしたり、ゼミを2つ掛け持ちしたりしていました。興味の対象が広いということがあるんですけど、多様性の中に身を置くことにも価値を感じているんです。
所属コミュニティがひとつしかないと、その中での価値観とか不文律に染まりがちになります。でも環境が変われば判断基準が変わって、常識が非常識に逆転することもありますよね。そんな時にもフラットな視点を持っていたいな、と。副業にもそういう効果がありますね。
人生をコントロールできると思うから悩む
——「偶然」をつかむには勇気もいると思います。勇気を出すために必要な要素はありますか?
平田:そうですね。勇気を持つには、柔軟性や、冒険心。そして持続性も大事だと思います。
——持続性?
平田:勇気の裏付けになるものだと私は考えています。何かしらのものを一定期間持続して、これは自分のものになったという自信。プロフェッショナリズムとも言えますね。
継続は力なりと言うように、専門性やスキルの裏付けが勇気になるはず。立派な資格とか、コンサルできるレベルじゃなくてもいいんです。たとえば、書類の整理にすごく自信があるとか、どんな人とも仲良くなれるとか、絶対に時間を守るとか。
——なるほど。そんなにハードルを高く構えず、楽観的に考えることも大事ですね。
平田:そうですね。根拠のない自信って案外大事です。結局、飛び込んだ後の答えが良かったのか、正解だったのかどうかって自分で決めること。自分の決断を否定しない限り、それは正解だと思うんです。だから、何か始めても、諦めるまでは失敗ではないというか。
悩みがちな人は、人生をコントロールできると思っているから悩むんだと思います。でも、人生そんなもんだと割り切ってしまえば、気持ちもラクになるのではないでしょうか。子育ても結婚や離婚も、仕事の経験も、全部蓄積されてひらめきを生むためのビッグデータになります。だから、いろんなことに挑戦して、いろんなことを手放していいと思うんです。
副業ならリスクも少なく始められると思うので、やってみて合わなかったら方向転換して、自分が続けられそうなものを探してみる。そしてそれが見つかったら極めていく、ということをやれたらいいのかなって思います。
(取材・文:ウートピ編集部 安次富陽子、撮影:青木勇太、撮影協力:DIAGONAL RUN TOKYO)