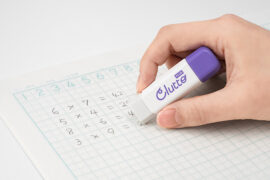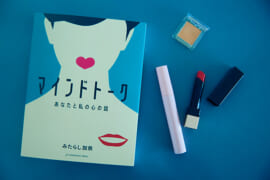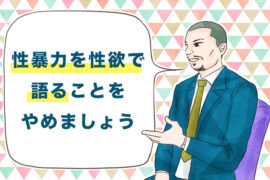慶應大学を卒業し、国家公務員の官僚コースへ進むという、いわゆる「エリート街道」を歩んできた小林味愛(こばやし・みあい)さん。かつては「鉄の女」と呼ばれるほどの仕事人間でした。
小林さんは国家公務員から民間企業へ転職し、転職先では心身の不調に苦しみ、逃げるように退職。次の当てのない生活をしている中で、小林さんの進む道となってくれたのはかつて仕事で出会った福島県の人たちでした。
現在は、「株式会社陽と人(ひとびと)」の代表として活動。福島県の農産物を活用したフェミニンケアブランド「明日 わたしは柿の木にのぼる」を立ち上げ、東京と福島での二拠点生活を送っています。
「あるとき、仕事の目標が『周囲に認められること』に変わっていることに気づいた」と語る小林さん。インタビュー前編では、小林さんがこれまでの働き方に疑問を持ったことをきっかけについて語っていただきました。前後編の前編です。
床に段ボールを敷いて寝た、国家公務員時代
——そもそも、なぜ国家公務員になろうと思ったんですか? 国家公務員の官僚って、なかなか馴染みがなくて、どういうお仕事なのかちょっと想像がつかないというか。
小林味愛さん(以下、小林):私、大学で政治学を専攻していたんです。でも教科書に載ってる政治って、キレイごとばかりで現実味がなかったんですよ。私は自分の目でリアルな政治の現場を見て社会をよくしたいという思いがあったので、国家公務員の中でもニッチな衆議院事務局という職場を志望しました。
でも実際に配属されてみると、政治うんぬんの前に、男女の性別役割分担を感じる雰囲気にびっくりしちゃって。職種の違いもありますが、お茶汲みをしているのはほぼ女性だったり……。学生時代までは男女平等が当たり前だと思っていたし、性別で役割が変わるような場面もなかったので驚きました。
——「おかしくないですか?」と上司に掛け合うことはしなかったんですか?
小林:しませんでした。当時は、まずちゃんと実力をつけて認められることが必要だと信じていたので。だから公務員時代の約5年間は、土日も仕事。熱が出ても仕事。夏休みもとったふりして仕事してました。残業時間が300時間を超えた月もありましたよ。
——300時間!? ハードすぎる。
小林:トイレの洗面台で体を拭いて、床にダンボールを敷いて寝たこともありました。でも良い仲間に恵まれて充実はしていました。ただ、20代後半になるとだんだん無理が効かなくなって。免疫力が弱っていたために気を抜くと婦人科系の病気になったり熱が出たりと体調を崩すようになりました。生理不順も当たり前でした。生理前のPMSも振り返るとひどかったです。過剰にイライラしていたと思います。
そんなとき、心から尊敬する上司に出会って、これまで無我夢中で頑張ってきていたけど、私の仕事はただの自己満足だって気がつきました。社会をよくしようと思って就職したのに、いつの間にか、他人と自分を比較して、出世して勝つことばかり考えるようになっているなって。
就職先も仕事内容も自分で決めたように感じていたけど、気づけば組織の歯車になっていたんです。このころから、「狭い組織のなかで競い合うんじゃなくて、自分にできることを探していきたい」と思い始めました。そこで転職を考えたんですけど、そこには高いハードルがあって……。組織の判断に従い続けてきたせいで、自分がやりたいことも強みも、何一つわからなくなっていたんです。
メンタル的にツラかったコンサル時代
——組織と自分がくっつきすぎて「個」がどっかいっちゃう感じですよね。組織の中で働いていると同じように感じる人も多そうです。その状態でどう転職活動を進めたんですか?
小林:消去法で決めていきました。特定の業界や業種に興味を持つことができない、それならばとさまざまな業界とつながれるコンサルティングの会社に転職しました。
でもこの転職で、さらに苦しむことになったんです。メンタル的に一番つらかったのは、まさにこの頃。残業時間は公務員時代より少なかったんですが、価値観のギャップに苦しみました。
——価値観のギャップ?
小林:はい。企業ですから最大のミッションとして売上は絶対なんです。でも私は、お金を稼ぐことにさほど興味を持てなかったんです。その会社で働いていたころは、各地域の行政と手を組んで進めるような仕事が多く、まさに社会をよくするための案件によく携わりました。
例えば、福島県の会津で若い世代に日本酒を広めるためのプロモーションをしたり、過疎化する町で若い人たちが集まるようなイベントを企画したり。しかし、イベントの成功と売上は切り離せないので、会社からは効率的に仕事をこなしてお金を稼ぐことを求められていて。人や社会と満足に向き合えていないような気がしたんです。
東北地方で仕事をした際には、津波で娘さんを亡くした方に出会いました。悲しみのなかで地域をよくしていこうと頑張っている人たちが目の前にいて、向き合いたいと思っているのに、私は大企業で売上を伸ばすために仕事をして、高い給料をもらっている。その矛盾に耐えきれなくなりました。当時、あまりにも思い詰めてしまったせいで10円ハゲが2つできて、在職中ずっと治りませんでした。
——そこから次の挑戦として、会社を立ち上げたんですね。
小林:そう言うとかっこいいんですが、実際は、次の就職先も決めずに逃げるように退職したんです。その後、コンサル時代に訪れた福島で農家の方々に出会い、地域の支えになりたくて起業しました。もともと起業家になりたかったわけではありません。私はただ、地域の人たちと向き合って仕事がしたかったんです。
レールから外れても大丈夫、と思わせてくれた人
——ちょっといじわるな言い方になってしまうんですが、小林さんは、いわゆるエリート街道を歩まれていましたよね。手放すのが惜しいなと思うことはありませんでしたか?
小林:私の周りにちょっと変わった人が2人いたので、特に惜しいとは思いませんでした。1人目は、先ほども少し話した国家公務員時代に出会った上司です。良い言葉が見当たりませんがまさに「天才」でした。国家公務員のなかではとても有名で、知らない人はいないくらいだと思います。
その人は「俺は俺の好きなことをやる。意味のないことはやらない」って言って、みんなが長い時間残業しているなか、驚きのスピードで業務を全部終わらせて帰るんです。他人と自分を比較しない生き方を間近で見られたのは大きかったですね。その上司のことは、今でも大尊敬しています。
2人目は、夫です。夫はもともと農水省の国家公務員で、同期でした。国家公務員の試験に上位で受かるほど頭が良く、仕事ができる人でした。でも、たった4ヶ月で国家公務員を辞めてしまったんです。
夫は子供の頃から早寝早起きで、夜9時になると眠くなってしまう体質で。「国家公務員の働き方は自分には合わない」と言って、気づいたら豆腐の引き売りのアルバイトをしていました。決して儲かるような仕事ではありませんでしたが、私はその姿をすぐそばで見ていて、「仕事を辞めても生きていけるんだ」と感じました。
そういう変わった人たちが周りにいたので、私も気楽に選択できたのかもしれません。レールから外れても大丈夫、きっとなんとかなるって、思えたんです。
後編は5月26日(金)公開予定です。
(取材・文:華井由利奈、編集:安次富陽子、写真提供:株式会社陽と人)