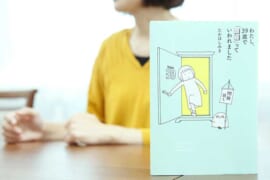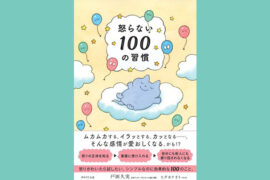アンガーマネジメントのプロ、戸田久実さんの『怒りの扱い方大全』(日本経済新聞出版)から特別に本編を抜粋して公開。全3回にわたってお届けるする第2回は、できない人に対する怒りを感じた時の対処法について紹介します。
Q. わたしはできたのになぜこの人はできないのか、と思ってしまいます。
A. 自分と相手を比べるのをやめよう。
優秀な人や管理職の人ほど、この感情に振りまわされがち。まずは「自分と相手は能力も背景も違う」ということを認識して対処しましょう。
自分の基準=常識ではない
「なぜこの人はできないのか」
という怒りは、管理職の人がよく抱きがちです。できない相手に対して、「わたしが若かった頃にはできたのだから、同じようにできるのが当たり前だろう」「これが普通だろう」という思いがついわいてしまう。
これは、自分の基準=常識という価値観があり、その価値観を相手に押しつけてしまうところから起こります。
だからこそ、怒りがわいてくるのです。
人はそれぞれの能力も、得意とすることも違います。
能力が異なるということは、苦手とすることももちろん異なるということ。だからこそ、どうしたらその人ができるようになるのかということに意識を向けて、行動したいところです。
そもそも、「なぜできないのだろう」と思っても、何も解決しませんし、相手との関係性に溝が生じるだけです。
では、なぜ「わたしはできたのに、なぜこの人はできないのか」という怒りがわいてきてしまうのでしょうか?
それは、相手への期待値が高いからです。
期待がある分だけ、怒りもわいてしまうのです。まずは、そのことを知っておきましょう。
自分の期待を押しつけない
じつは、こういった怒りを抱えている人は、できる人に多く見受けられます。自分ができる分だけ、「なぜわたしのまわりにいる部下は、バカばっかりなんだ! わたしならできたのに!」と、相手に求める基準も高くなってしまうわけです。
思い当たるという場合は、「その怒りを持ち続けていても部下が成長するのだろうか」というところに立ち戻ってほしいのです。
あるとき、大手企業の常務がこんなことをおっしゃっていたのが、とても印象的でした。
「わたしはずっと、野球でいうと150キロの剛速球が飛び交うなかで野球をしてきた。でも、わたしがいま担当している30代の部下たちは、草野球のチームからのスタートなんだよ。置かれた環境も経験も、キャリアも違うということがようやくわかった。150キロの剛速球の経験をしたことがない人に、この剛速球がなぜ取れないのか! と言っても、経験がないものは仕方がないよね」
この常務は、若手の頃、150キロの剛速球が飛び交うような職場でビシビシしごかれて、平均値を出さなくてはいけないような環境で過ごしてきたそうです。
そして、それが当たり前にできるようになった頃には、できない人たちのことを「なぜこの球が取れないのだろう」と思っていたのです。
でも、相手に経験がなければ、すぐにできるようになるはずもありませんし、無理な話ですね。
相手の能力を冷静に分析し、望ましい未来を共有する
もし「自分はできたのに……」と思ってしまう場面に遭遇したら、相手のキャリアや経験してきたこと、能力を洗い出してみてください。
ひと通り把握したうえで、
・その人にどうなってほしいのか
・どうしたら望んでいることをしてもらえるのか
ということも、書き出します。
実際に話すときには、「なぜできない」という点にフォーカスするのではなく、こうあってほしいというゴールの未来を共有しながら伝えます。
「まず、今後◯◯さんにはこういうことをできるようになってほしいと願っているんだ。そうなるには、どんな取り組みをしたらいいかを話し合えたらと思っています」
自分と比較してただ高い期待値を掲げるのではなく、小さな一歩一歩のスモールステップから取り組めるように、関わっていきましょう。
(『怒りの扱い方大全』P93〜97より抜粋)