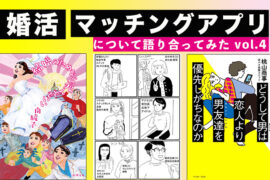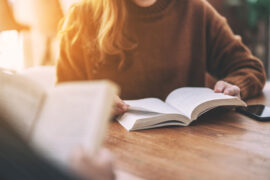日本には障がいのある方が788万人いると言われています。さまざまな法律や制度が整備されているとはいえ、まだまだ「障がい者が暮らしやすい」とは言えない日本。暮らしやすさを実現するために何が必要なのでしょうか?
「障害のない社会をつくる」のビジョンの下、障がいのある人の「働く」をサポートする事業などを行っている株式会社LITALICOの古澤祐幸(ふるさわ・まさゆき)さんにお話しを伺いました。
たった14%しか働けていない
―日本では「障がい者」にマイナスなイメージも持つ人も多いようです。
古澤:「障がい」とはその人と、その人を取り巻く環境の間で生まれている問題に過ぎないと捉えています。得意なことがあれば不得意なこともあるというのは「健常者」と呼ばれている人々も当たり前のことです。そのことを互いに認め、調整し合うことで、障害のある方はもちろん、社会全体の暮らしやすさにつながっていくのでは、と考えています。
その中で重視していることの一つが、「働く」ことのサポートです。働くことと人生の満足度の間には密接な関係があり、社会の中で仕事をして対価ややりがいを得ることは、自己肯定感を高めていくことにもつながります。
しかし、障がいがあるといわれている788万人のうち、労働可能人口とされる18~64歳の方は324万人いらっしゃいますが、現在一般企業で働くことができている人は約14%に過ぎません。多くの人が働く喜びを感じにくい状態にあるのです。
ほんの少しの柔軟な対応で変化する
――働きやすい職場にするために大事なことは何でしょうか?
古澤:実は、ほんの少しの柔軟な対応で解決するんです。例えば、A社に精神疾患による幻聴や幻覚が原因で、多くの人が集まる場所が苦手な方がいらっしゃいました。その方は朝の満員電車に乗って通勤することが難しく、これが働く上でのネックになっていたんです。
こうした状況を変えるために、A社が行なったのは「出社時間を朝9時から11時に変更する」という方法でした。人が多い時間帯を避けることで「満員電車」という障がいはなくなり、無事に働けるようになったのです。
また、B社には、ルールに則って行動しなければパニックになってしまうという、強いこだわりを持つ発達障がいの方がいらっしゃいました。職場に存在している曖昧なルールのなかで働くことをとても苦痛に感じていたそうです。
これに対しB社では、個人の自由に任されていた曖昧なルールを「休憩は1時間毎に5分間、フリースペースでとること」といったように、より具体的にしてその方に提示しました。その結果、その方はパニックを起こさずに働くことができるようになったそうです。
このように、さまざまな特性を持つ方が働きやすい職場をつくるカギは身近なところにあります。特別な何かをしようとするのではなく、その方の特性に合わせてほんの少し柔軟な対応すること――それがお互いに働きやすい環境をつくるきっかけになるのではないでしょうか。
障がい者雇用が働きやすさにつながる
――企業からの反響はいかがでしょうか?
古澤:障がい者雇用を行なっている企業にアンケート調査を行ったところ、およそ9割の企業が「雇用してよかった」と回答しています。
その理由として、雇用したご本人が期待通りに活躍してくれたことはもちろん、障がいがある方を雇用するために、マニュアルや制度等を整えることができたことや、それにより業務が効率化し、他の方も仕事がしやすくなったという声も多く上がりました。また、互いに配慮することができるようになり、職場の雰囲気がよくなったという回答も見られました。
――社会が変わることで社会に属する個人も変わっていくんですね。
古澤:一般的に障がいというと個人が有しているものだと思われがちですが、弊社ではさまざま人の困りごとに適した対応できない社会の側にこそ障がいがあると考えます。
例えば、目が悪い人のことを考えてみてください。もし、この世の中に眼鏡がなければ、多くの人は介助がなければ生活できない状態になっていたかもしれません。
しかし、眼鏡のように人々の困りごとを解消する製品やサービスさえあれば、生きる上での困難である「障がい」はなくせますよね。社会の側を変えていくことで「障がいのない社会」を実現することができるはずです。