ビジネスやIT、医療分野など、ニュースがよりわかりやすくなるための、メディアでよく見聞きする用語の意味や使用例を連載で紹介しています。これまでの「ホールディングス」「エビデンス」「コンプライアンス」などの用語は文末のリンク先を参照してください。
今回・第17回は、2022年後半ごろからメディアで頻繁に触れるようになった「リスキリング」という用語について、大正大学表現学部の前教授・講師で情報文化表現が専門の大島一夫さんに、編集スタッフ・藤原椋(むく)が尋ねます。
デジタル技術を身につけようという動き

リスキリングは英語では「reskilling」で、直訳すると「スキルを学び直す」という意味です。スキル(skil)とは、学習や訓練によって習得された技能のことをいいます。経済産業省は、リスキリングを「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」としています。
海外ではもっと早く、2020年に世界経済フォーラムが「2030年までに10億人の人々により良い教育、スキル、経済的機会を与える」と宣言して以来、大きく注目されています。

「必要なスキル」とは具体的にどういうことですか。

世界的に産業のデジタル化、AIによる業務の変革が進んでいます。これまでIT化といっていた「仕事にデジタルを取り入れる」段階から、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」と呼ばれる、製品やビジネスモデルそのものをデジタルによって変革する(トランスフォームする)動きが求められています。
つまり、仕事そのものがデジタル化によって、内容も方法も変わる時代がやって来ているのです。
それによって一部の仕事が消え、DXによって新たな職業が生まれて、従来の仕事内容も大幅に変わります。いま、リスキリングというと、とくに「新たなデジタル技術を獲得する」ことを意味するでしょう。
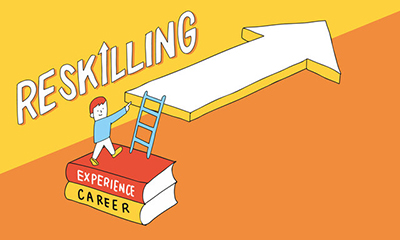

デジタル技術の応用で身近な例では、スーパーやコンビニのレジのセルフ化、電子マネーの普及、住居やビル、スマホやパソコンの開錠のための指紋認証や顔認証など、さまざまにありますね。最近では、質問に答えて文章を生成するAIツールの「ChatGPT(チャットジーピーティー)」の話題も盛んです。

そうした身近なデジタル化の背後で動く膨大なデータをどう活かすのか。「ChatGPT」も膨大なデータをAIで活用することで実現しています。こうした社会のDX化にデジタルスキルが必要なわけです。これは脱炭素社会への取り組みにとっても必要なスキルとなります。
業務効率化の一方で手間やコストの課題も

リスキリングのメリットは具体的にどういうことが挙げられますか。

DXによって必要な仕事が変化するわけですから、いちばんのメリットは必要な仕事に人材を動かせることでしょう。
また多くの人が新たな技術や知識を獲得してさらなるアイデアを生み出し、各自のスキルアップ、キャリアアップにもつなげることができます。

デメリットはありますか。

企業としてはリスキリングの成果を出すために時間、手間、経費がかかります。また、新しいスキルを習得した社員が、そのスキルを活かせる別の会社へ転職していくということも考えられます。
国や自治体、企業なども取り組みに参加

リスキリングを取り入れた企業の事例はありますか。

日本では日立製作所、富士通、住友商事らが早々に実践したことで知られています。
2022年6月には、リスキリングに取り組むための「日本リスキリングコンソーシアム」が発足しました。2023年2月現在で、国や自治体、企業などの約150団体で構成されています。ウエブ上で700以上のトレーニングプログラムと就業支援サービスを提供しています。
そうした、リスキリングへの動きは活発化していますが、個人のレベルでは、まだまだリスキリングに対する反応は鈍いと思われます。社会のDX化の流れは止められません。もし、自分の会社がリスキリングに乗り出したら、積極的に参加していってほしいですね。

リスキリングの実践を機に、企業と社員がメリット・デメリットを見つめながら、近い将来の技術者養成の仕組みを具体的に構築する時代になりそうですね。
次回・第18回は「メタバース」についてお尋ねします。
(構成・取材・文・イラスト 藤原 椋/ユンブル)















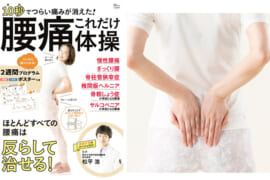









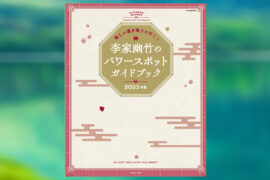









昨年(2022年)11月に岸田総理が今後5年でリスキリング支援に5兆円を投じると発言して以来、話題の用語となっているようです。どういう意味ですか。