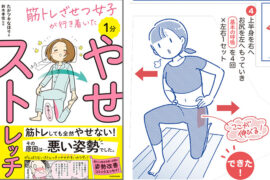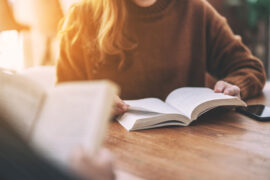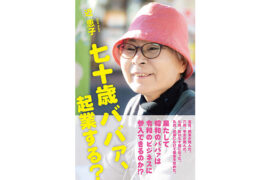俳優の東出昌大さんと三浦貴大さんがダブル主演する映画『Winny』(松本優作監督)が3月10日に公開されます。BitcoinやNFTなどで使用されているブロックチェーン技術の先駆けといわれたファイル共有ソフト「Winny」。2002年に開発者の金子勇さんがこれを「2ちゃんねる」で公開するやいなや瞬く間に広がり、ピーク時は200万以上の人が使用していたといわれています。
Winnyとは何だったのか? そして、音楽シーンを一気に変えたiPodや世界最大の音楽配信サービスSpotifyとの関係は? 音楽プロデューサーの渋谷ゆう子さんに音楽著作権の観点からつづっていただきました。
「殺人に使われたナイフを作った人を罪に問えるか?」
ファイル共有ソフトWinnyの開発者である金子勇氏の実話をもとにした映画『Winny』が3月10日に公開された。
ブロックチェーン技術の先駆けと言われる技術「P2P(ピア・ツー・ピア)」の技術を使ったWinnyは2002年に開発され、200万人以上が使用したとされる。ソフトを開発した金子勇氏は2004年、著作権法違反ほう助の容疑で逮捕された。金子氏は逮捕が不当であると訴え、弁護団とともに検察側と全面対決した。この映画は裁判の進行を軸に、ひとりの天才開発者と彼をとりまく国家権力との闘いを描いている。
金子勇役は東出昌大、金子氏と共に裁判へ挑む弁護士の壇俊光は三浦貴大が演じた。それぞれ本人や関係者との取材を念入りに行って、人物像を似せていったという。
裁判のシーンが多く含まれるため、実際に模擬裁判も行ってリアリティーを追求したという。また東出は、金子氏に体形を寄せるために18キロの増量まで行い、金子氏の話し方や身振りや手振りも綿密に似せた。金子氏の実姉は東出の演技を見て、そこに本人がいるかのようだと評した。

「殺人に使われたナイフを作った人を罪に問えるか?」
三浦貴大演じる壇弁護士のこのセリフが、この映画の核をなす。革新的なソフトウェアが開発され、それが法を犯すことに使われた場合に、その開発者が罪に問われるのか、という意味である。
ユーザー同士が互いにネットワーク内でやりとりができ、ファイルを共有できるWinnyは、映画や音楽など、本来対価を払って手にいれるものをユーザー同士が無料でやり取りをしてしまうことをも可能にした。実際に、違法ダウンロードで逮捕されたユーザーもこの映画に出てくる。
一方で、先の壇弁護士のセリフのとおり、犯罪に使われたからといってナイフ職人が罪に問われるのか。これらの争点の掘り起こしと、弁護側と検察官、また捜査を担当した警察との間の理論立てと質問の応酬で見応えのある法廷劇に仕上げられている。
金子氏は著作権侵害を目的として開発をしてはいないこと、また法廷で闘うのは、エンジニアが自由に開発できる社会を目指したいからだと主張していた。実際、この裁判に際してWinnyのユーザーらが弁護団に寄付をし、金子氏を励まし続けていた。
この映画では、新しい技術を生み出した天才エンジニアを畏れから糾弾に回った側と、新しい技術革新を願い、それを支えようとする側という、相反する二つの勢力の攻防が事実に基づいて綿密に描かれている。

iPodが世界を席巻できた理由
実はこれに先んじてアメリカでも、音楽著作権ビジネスを大きく揺るがした技術が開発されている。この映画の中でも名前の上がったファイル共有システム「ナップスター」だ。1998年にアメリカで開発されたナップスターは、Winnyと同様にP2Pのシステムで、MP3というフォーマットで音声データを簡便にユーザー間で共有でき、3千万人のユーザーを獲得していた。そして著作権侵害、違法ダウンロードなどで多数の裁判を起こされた。しかし一方で、この革新的なP2PとMP3はその後の世界中の音楽シーンを一気に変える礎ともなったのだ。
2001年、AppleはMP3で1000曲持ち運べるとした音楽プレイヤーiPodをリリースし、大ヒットする。そしてメディアデータの管理ソフトiTunesにより、音楽産業はフィジカル(レコード盤やCDなど)から一気にデジタルデータに移行することになる。
この流れに乗れなかったのは他でもない、日本のSONYである。実際にナップスターの開発、経営陣はMP3の技術がウォークマンのデジタル化に有益であるとして交渉を持ちかけていた。だが、SONYは著作権管理に問題があるとしてこの申し出を拒んだ。結果、SONYは音楽プレイヤーとデジタルコンテンツ販売でAppleの後塵を拝することとなる。
ナップスターは確かに問題点が多かった。しかし一方で、新しい技術の登場によって発生した問題点を解決しようとする技術もまた生み出された。ナップスターの一人が、その後ストリーミングサービスSpotify誕生にも大きく関わっていたことはあまり知られていない。Spotifyはデジタルコンテンツ著作権問題の救世主ともいわれたサービスである。さらにナップスターはその当時から月額課金制(サブスクリプション)サービスを展開していた。彼ら卓越した技術者の先見の明により、今では数多くのP2P技術を使ったサービスが展開され、新しいクリエイターが生まれている。
コンテンツを生み出すクリエイターの権利、そしてその制作を担う会社の権利は正しく保護され、正しく収益を得られなければならない。しかし時代は変遷し技術は革新する。その都度マネタイズ手法は変動して当然であり、それに追随できないものが脱落することはあろう。だからといって新しいものに杭(くい)を打ってつぶしていいはずがない。また同時に、新しい技術を生み出す側の自由も保障されるべきである。それこそ、この映画の中で金子氏が訴え続けたことである。

さて、杭を打ち込んだのは誰なのか?
金子氏がWinnyを開発していたのは、アメリカでナップスター問題の法的議論が出尽くし、音楽ビジネスのあり方と著作権保護の問題点は既にテーブルに並べられていた時期である。しかしそれらの前例は日本で議論されることなく、金子氏は逮捕され、裁判が終わるまでの7年もの間、金子氏は開発を続けられない状態となった。さらに悲しいことには無罪確定後、たった2年で彼はこの世を去ってしまった。この天才エンジニアを開発の世界から葬ったのは誰なのか。誰かに出る杭が打たれた、果たしてそれだけなのだろうか。

映画の中で、弁護団の一人、秋田弁護士(吹越満)は言った。「杭は一人では打ち込めない」大きな杭を打つためには、その杭を支える人たち、杵(きね)を下す人、そして杭打ちを指示する人が必要なのだと。才能あるものを妬(ねた)み、貶(おとし)める発言をする人、実際に暴力行為にでる人、ネットに書き込む人、それらを扇動する人、そして権力をもって押さえ込む人……。どこかで目立つ杭があったとき、自分はその杭打ちに関係ないと誰もが胸を張っていえるだろうか。
日本にまん延するそれらの空気を少しでも社会をよりよくする機運に変えていくにはどうすればいいのか。既得利権への固執ではなく、未知への恐怖でもなく、新しい技術の生まれる先を信じるためにどうしたらいいのか。この映画はその未来への一つの解を提示しているだろう。
『Winny』
監督・脚本:松本優作
出演:東出昌大 三浦貴大 皆川猿時 和田正人 木竜麻生 池田大 金子大地 阿部進之介 渋川清彦 田村泰二郎 渡辺いっけい / 吉田羊 吹越満
吉岡秀隆
公開表記:2023年3月10日(金)全国公開
配給:KDDI ナカチカ
(C)2023映画「Winny」製作委員会