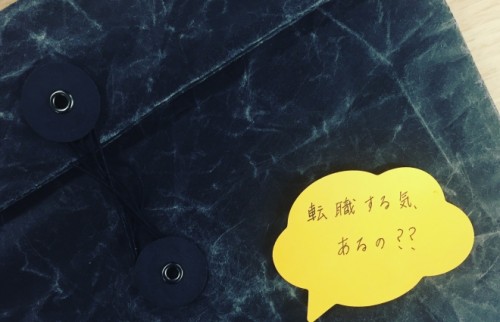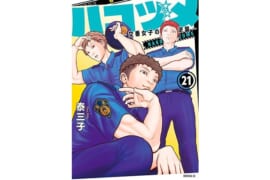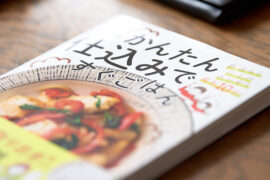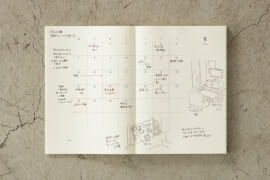「しばらく会わないうちに親がずいぶん老けた気がする」
「年老いた親と離れて暮らしている私は親不孝?」
「まだ大丈夫だとは思うけれど、ゆくゆくは介護のことを考えないといけないのかな」
例えば、年末年始の帰省で久しぶりに親に会ったときにそんなことを感じてしまう人は少なくないはず。育ててもらった恩はあるし、親のことは大事だけれど、介護のことを考えると気が重い……。
そろそろ”介護のお年頃”の人に手にとってほしい書籍『親不孝介護 距離を取るからうまくいく』(日経BP)が10月に発売されました。「介護=親のそばにいる=親孝行」と思われがちですが、実は親と適切な距離をとったほうがうまくいくという従来の介護の“常識”をひっくり返す指南本です。
著者は東京で働きながら、地方で暮らす母親の介護を5年間続けた編集者の山中浩之(やまなか・ひろゆき)さんと、NPO法人「となりのかいご」代表で、介護コンサルティングに長年携わっている川内潤 (かわうち・じゅん)さん。山中さんの、親との距離を取る“親不孝介護”の実体験を川内さんと振り返ることで誰にでも役立つようなロジックとしてまとめられています。
そこで、ウートピではそろそろ「親の介護が気になる/すでに介護に関わっている」読者向けに、川内さんと山中さんに対談していただきました。全4回。
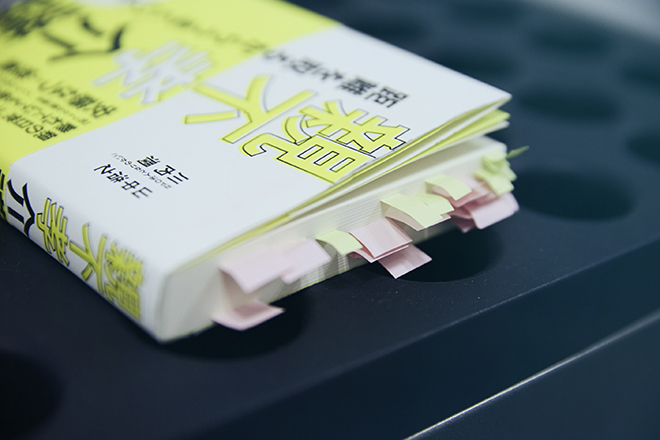
根強い「嫁だから」「長男だから」介護しなきゃの呪い
——(ウートピ編集部、以下同)女性の場合、現実問題として義理の親の介護をしている方もいると思います。山中さんの奥さんのスタンスはどうでしたか?
山中浩之さん(以下、山中):基本的に、帰省費用や介護にかかるお金は、母のお金を使ってました。それは、奥さんから、「お義母さんの介護にかかるお金は、お義母さんから出してもらってください」とハッキリ言われたので。親にも伝えたら、「もちろんいいよ」と了承してくれたので、ハッピーに済んだんですけど。
介護は、いつまで続くか分からない。奥さんにも子どもにも日常があるし、自分がうっかり“親孝行”気分で、簡単に家計を、家族を介護に組み込んだら、どうなるか分かったもんじゃない。そして、家族関係を安定させていくためには、奥さんのご機嫌が何より大事なので(笑)。精神的にちゃんと信頼し合ってないと、回るものも回りませんよね。
川内潤さん(以下、川内):親を呼び寄せる選択をしたら、確実に夫婦関係にヒビが入ります。それは結局、「誰のためなのか?」ということが見えなくなってるわけですよね。でも世の中には、「嫁だからやらなきゃいけない」「長男だからやらなきゃいけない」という思い込みがあるんだと思います。それって実は、何も考えてないんですよ。「そういうもの」という思い込みに当てはめただけで、「親にとって何が最善なのか?」ということを考えていないんです。「子どもは親の近くで直接面倒を見るべき」という“親孝行の呪い”に縛られているというか。
山中さんの奥さんが「お金はお義母さんに出してもらってください」と言ってくれたのは、大変すばらしいと思います。逆に、奥さんが、「私が介護したい」「お金もうちから出したい」と言ってきたら、夫は全力で止めたほうがいいです。
山中:本格的に介護が始まる前だと、田舎の親を訪ねて面倒を見る、ということで、ついつい「帰省で親を温泉に連れて行く」とかと同じようなイメージになるんですけどね。帰省は数日で終わりますが、介護は何年続くかも分からない。帰省は非日常で、介護は日常なんですよね。
川内:そう、「介護はいつまで続くか分からない、終わりなき日常だ」というリテラシーを、夫婦で共有するべきです。実際に、奥さんが、義理の親のために仕事を辞めたりだとか、子どもを連れて義実家に帰って面倒を見たりするケースもあります。でも、どんなに頑張っても、子どもが直接介護することはお互いにとってストレスが大きくて、うまくいきません。家族の中に「そばにいるのが親孝行」という思い込みから自由な、冷静な人がいればいいんですけど、どうもそういう人はあんまりいないのかなと感じています。
山中:ウートピは女性読者が多いということで申し上げますと、パートナーや夫を説得するときには、ぜひこの本を活用してほしいですね。特に会社員で40、50代のおじさんには、日経ブランドが結構効くはずなので(笑)。それくらい、私たちの偏見や呪いは強いということでもあるんだけれど。おそらく、どなたも夫と、夫の親のことで正面切って対決なんか、したくないじゃないですか。第一面倒だし(笑)。だったら、「日経の本に会社員の介護について書いてあるから、読んでおいたら?」くらいの感じで渡してみるとか。
この本がビジネス書テイストになっているのは、ビジネスパーソンはミッションを具体的に提示されると反応できるからなんです。「こういうふうにすればうまくいく」という手順を示されると、能力のあるビジネスパーソンだったら考え方を変えるんです。
川内:そう、しかも、ビックリするほど劇的に変わります。優秀なビジネスパーソンは、自分でやる前に要点をつかもうとして、介護制度を一生懸命に調べたり、介護技術を学ぼうとしたりします。でも、それは絶対によくない。介護の制度や技術を学ぶのではなくて、親のためには距離を取って、プロに任せるほうが大事なんだ、ということが分かった瞬間に、ガラッと変わる人が多いんですよ。たいていそこからはうまくいく。
山中:私もまさしくそうでした。
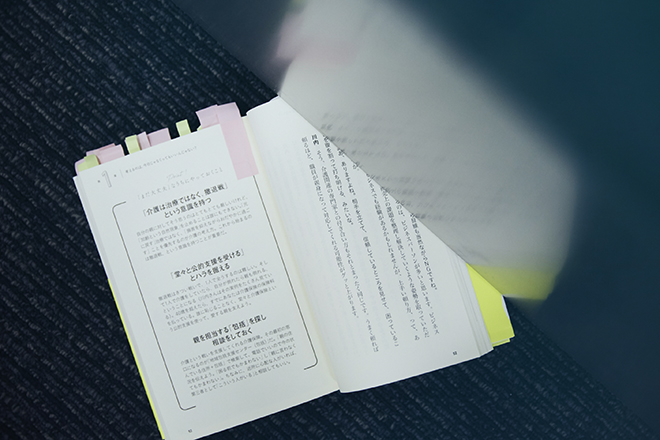
「親を呼び寄せる」のは誰のため?
——実はこの本を読むまで、「近い将来、親を呼び寄せようかな」と考えていました。
川内:二世帯住宅とか、親を呼び寄せて同居するケースがどうしてうまくいかないかというと、「親子で近くに暮らすのが幸せ」という、思い込みしかないことがほとんどだからなんですよ。
山中:近くに居ることで、子どもは親の衰えに直面して、そこからストレスがかかっていくわけで。
川内:都会のほうが医療施設が充実しているから、と言う人もいます。でも、住み慣れた家を捨てさせて東京に呼び寄せて、最先端の医療を受ける、それが、高齢の方にとって最善のことなのか? というと、そんなことないわけですよね。80歳を越えてから、生活環境を変えてまで「がんの最先端治療を受けたいか?」というと、うなずく人は多くないと思います。じゃ、なぜこういう発想が子どもから出てくるかといえば、最先端の医療を受けさせたいのは、本人じゃなくて子どもだからなんですね。
「親が都会に来ることは、誰のための幸せなのか?」「呼び寄せることで、誰の不安を下げたいのか?」ということを整理していくと、「自分が安心したいからでした」という話になることが、実際に多いです。親じゃなくて、自分のためだったと。
山中:私も親を呼び寄せようかなと思ったんですけれど、川内さんに止められました。それでよかったと思います。ただ、いまさらですが、私の母親はとても甘ったれなので、一緒に住んだらすごく喜んだ時期もあっただろう、とは思いますけど。
川内:はい、でも、「会えなくて寂しいね」とか、「今度また会える、うれしいね」と言えるぐらいの距離感がいいんですよ。会ってないから、言えるわけじゃないですか。だけど、「寂しそうだったから呼び寄せたんですけど、うまくいかなくなってきて……」となったらどうしますか。厳しい状況になってから、親を元の場所に戻すなんてことは無理なんですよ。だから、まだ呼び寄せてないときに、その“寂しさ”について掘り下げて考えてほしい。
山中:“寂しさ”について掘り下げる……。
川内:“寂しさ”って、会いたい気持ちの根源だと思うんですよ。会いたい気持ちって、「お互いを大切に思ってる」という、とても大事な気持ちですよね。そうなると、「寂しい気持ちを持たせないことが、本当にゴールなのか?」と。“寂しさ”は“寂しさ”のまま、置いておく。その“寂しさ”がありながらも、親がどう穏やかに生活できるのかを考えることが大切だと思います。
山中:良い話ですね。本に入れたかったな。
川内:「私たちの首の上についてるのは、帽子を乗せる台じゃない」っていう。フランスのジョークらしいんですけど。
山中:「頭を使って考えてみろ」と……。
川内:そうですね。だって、親のことをよく知っているのは、子どもですよね。親が何を思っているのか、もう一回考えることが、子どもができる仕事だと思うんですけど。
山中:それこそが本当の親孝行なのかも。
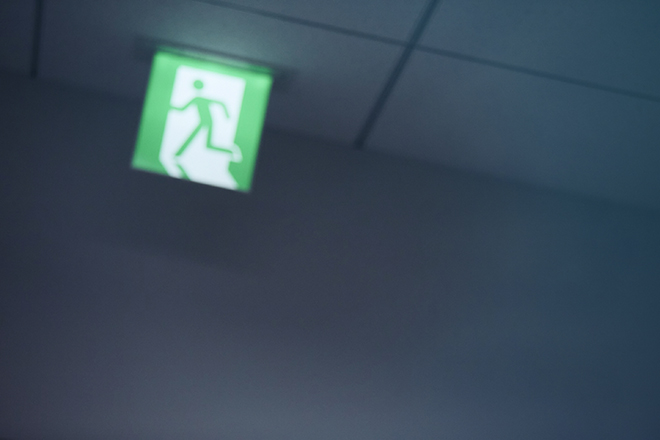
親のことになると子どもは正気を失う
山中:頭を使えと言われたばかりですけれど、でも、実際に子どもが、冷静に考えてここまでたどり着くのは、無理だと思うんです。寂しいと思った瞬間に、脳がショートして、「なんとかしなきゃ!」モードになっちゃう。
川内:そうですよね、それは分かります。自分だって、自分の親についてはこんな冷静なことは絶対言えません。他人のことだから頭が使えるんです。
山中:ですよね(笑)。ただ、川内さんに相談したり、本を読んだり、こういったインタビューを読むことで、冷静になることはできますよね。あらかじめ「親のことになると、子どもは“親孝行の呪い”が発動して正気を失うんだ」くらいに思っていると、ちょうどいいと思うんです。そこから正気を守るために、「“親不孝”だと思える介護でいい、親不孝介護でいい」という考え方をお守りにしてください、と。
川内:そして、自分と家族の日常を大事にする。
山中:そうですね。「あなたの日常をできる限り変えないことが、介護では大事だ」ということを大前提に、「その範囲で何ができるのか?」を考えるのがいいんじゃないかな。「そんな自分中心でいいの?」と思う方もいると思いますが、そのくらいにしないと“呪い”は解けないので。別の言い方をするなら、「私が苦労する分、親が幸せになる」わけではないんですよね。
川内:親の世話や介護のことを考えていると、マイナスなことしか思い浮かばないかもしれない。でもやっぱり、人は誰でも年を取るので。もう少しフラットに考えて、ある意味、無責任に考えていくほうが、よっぽど“親孝行”になるんじゃないかな。
(構成:ウートピ編集部・堀池沙知子)