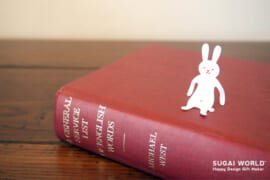就寝中にトイレで目覚めることがよくあり、起き上がるのがおっくうです。日中もトイレが近く、デスクワーク中何度も席を立つことがあります。そこで鍼灸師で太子橋鍼灸整骨院(大阪府守口市)の丸尾啓輔院長に、トイレが近い悩みを改善するための頻尿ケアツボを教えてもらいました。
頻尿の原因は「気・血」の循環停滞で体調悪化
丸尾さんは、頻尿の原因についてこう説明をします。
「日本泌尿器科学会では『排尿の回数が朝起きてから寝るまでに8回以上を頻尿』、また、『就寝中に1回以上だと夜間頻尿である』とし、ただし、『回数に関わらず、自分がトイレが近いなと思えば頻尿と言える』とも伝えています。
頻尿の原因を東洋医学では、体内の血液以外の水分を表す『水(すい)』の循環が停滞して、排尿や水分調節、ホルモンバランスを調整する『腎(じん)』の働きが衰えていると考えます。またそれらには『冷え』が深く関係しているととらえます。トイレが近いときは体調を見つめたうえで、次に紹介するツボを刺激してみてください」
ツボ・中極(ちゅうきょく)を刺激する
「中極」の「中」は中心や重要なところ、「極」は端から端まで張った柱を表すとされます。つまり中極は、頭から足先まで全身に張っている柱の中央にあるツボという意味合いです。
このツボのケアで、泌尿器系の血流を促して機能を整え、頻尿、腰痛、下半身の冷えやむくみ、月経痛の改善が期待できます。
<ツボ「中極」の位置>
体の中心線上で、おへそからおや指の幅4本分下がったところ。
<刺激法>
両方の手のひとさし指、なか指、くすり指の3本を重ねて、軽くへこむ程度にひと押し5~10秒を5~10回くり返します。また、ツボの部分を中心に手のひらでさする、カイロをあてるのも有用です。
ツボ・膀胱兪(ぼうこうゆ)を刺激する
「膀胱兪」はその名のとおり、膀胱の働きを活発にするツボです。泌尿器系の症状や下半身の血流を促し、頻尿、冷え、便秘、下痢、腰痛などに働きかけます。
<ツボ「膀胱兪」の位置>
腰骨のでっぱりに手を置いて、おしりの後ろに親指が届くあたり。仙骨(せんこつ)部の上から2つめのくぼみと同じ高さで、背骨から外側に手のおや指の幅2本分離れたところ。少しくぼんでいます。左右にあります。
<刺激法>
両方の手を左右それぞれ、腰骨のでっぱりの上に当て、左右のツボを同時におや指でひと押し5~10秒を3~5回くり返します。手のひらでさする、カイロを貼るのも有用です。
ツボ・曲泉(きょくせん)を刺激する
「曲泉」は膝(ひざ)の内側にあるツボで、「曲」は膝の曲がりめ、「泉」は生命活動に必要なエネルギー「気(き)・血(けつ)」が湧き出る場所を表します。頻尿、排尿痛の緩和、血液の流れ、また、足の痛み、だるさなどを改善します。
<ツボ「曲泉」の位置>
膝を曲げたときに、内側にできる横じわの先端。太い骨のきわ。左右にあります。
<刺激法>
押しやすいほうの手のおや指でひと押し5~10秒ほどを3~5回くり返しましょう。残りの4本の指で膝をつかむように支えると押しやすいでしょう。ツボ周辺を手のひらや指の腹でさするだけでも有用です。
聞き手によるまとめ
おなか、おしり、膝の内側と、順に押してみたところ、すぐに下半身がほんのり温まったように感じます。デスクワーク中や休憩時、就寝前に毎日2週間行うと、トイレに行く回数が減ってきました。試してみてはいかがでしょうか。
(構成・取材・文 藤原 椋/ユンブル)