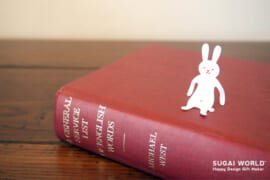治療の現場に立つ医師は冬の間はとくに、多くの時間をかぜやインフルエンザにかかった患者さんと接しながら、感染を防いで自身の健康を保ち、診療にあたっていらっしゃいます。そこには、医師だからこその知恵と工夫による予防策があるにちがいありません。
そこで、臨床内科専門医で正木クリニック(大阪市生野区)の正木初美院長が実践している方法を聞いてみました。
マスクを指で触らない
はじめに正木医師は、「かぜやインフルエンザの原因となるのはウイルスなので、ウイルスを予防することを考えましょう」と話し、続けて、
「(ア)ウイルスが生きにくい環境をつくる、
(イ)体の中に侵入させないで、もし体内に入ってしまっても、
(ウ)いかに早くやっつけるかを実践しましょう」と説明します。
そのうえで、まず、(ア)と(イ)について、次のポイントを挙げます。
(1)ウイルスの嫌いな室温、湿度を保つ
かぜやインフルエンザのウイルスは、低温と乾燥が大好きです。温度22℃程度・湿度50%以上でインフルエンザウイルスの生存率は2~4%に低下したという論文もあります。患者さんのせきやくしゃみが飛び散る診療室は、ウイルスが嫌うそういった環境を保つようにしています。部屋の湿度が保たれると、鼻やのどの粘膜の保湿につながります。
(2)手洗いを徹底する
子どものころから意識はしていても、習慣として実践している人は実は少ないのではないでしょうか。私は患者さんを一人診察するたびに手洗いをしますが、必ず石けんで、指先、指の間、手首までていねいにウイルスを洗い流す意識を持って行いましょう。
外出先のトイレによくある手の乾燥機は、空気の吹き出し口にウイルスがついて飛沫する可能性が高いため、使い捨てのペーパータオルを使用しましょう。家庭では、手を拭くタオルを家族と共用しないようにしてください。
(3)外出時はマスクをしてのど飴をなめる
のどと鼻の乾燥を防ぐ対策です。自分の息や唾液で鼻腔(びくう)、口腔(こうくう)の湿度を保つことができます。また、マスクをしながらのど飴をなめると、のどと口腔内の潤いが増し、ウイルスの侵入を防ぎやすいでしょう。
(4)マスクをつけたら、ゴム以外は触らない
マスクは一度つけたら、全体にウイルスが付着していると考えます。「汚物」として扱うようにしましょう。顔からはずすときにはとくに注意が必要です。鼻や口の部分には触らずに、耳にかけたゴムの部分からそっとはずしてください。
捨てるときは、室内のごみ箱にぼいっと放るのではなく、ビニール袋に入れて口を閉じてからそっとごみ箱に入れましょう。できれば、家に入る前に玄関先で取りはずしてビニール袋に入れてから捨てるのがもっともよい方法です。これで室内にウイルスが飛び散る可能性が減るでしょう。
湯上がりには、バスルームで体を拭いて体温キープ
次に正木医師は、先述の(ウ)について、
「手洗いやマスクなどでウイルスを徹底的にガードしていても、100%侵入を防げるわけではありません。そこで、侵入しても水際でいかに素早くウイルスを排出させるか、体内でウイルスが増えるのを抑えるかが肝心になります。それには、水分補給、体温保持がポイントです」と具体策の紹介を続けます。
(5)つねに白湯を飲む
ウイルスが体内に入っても、のどの粘膜や鼻毛といったバリア機能が働けば、そこで一部は侵入を食い止めることができます。バリア機能を十分に引き出すには、粘膜を乾燥させないことが重要です。ですから、水分補給をいつも心がけましょう。冷たい水ではなく白湯を飲むと、体温をキープすること、また体温のキープは免疫力の活性化につながります。私は患者さん一人の診察が終わるごとに、白湯を一杯飲んでいます。
(6)湯上りは浴室内で体の水分を拭き取る
入浴中は体温が高まり、蒸気でのどや鼻の粘膜が潤っているため、ウイルスの侵入を防ぎやすい状態です。しかし湯上がりが問題で、体の水分を素早く拭き取らないと、寒い脱衣所では気化熱で一気に体温が奪われます。そこで、バスタオルを扉のすぐ外に置いておき、湯上がり時には浴室内にぱっと取り込んで、脱衣所に出ずに浴室内で、肺に近い胸、のど、背中側の首からけんこう骨のあたりからさっと拭き取ります。
(7)カイロや湯たんぽで体温をキープする
体温キープには、おなかや腰にカイロを貼る、また、睡眠時には湯たんぽが有用でしょう。湯たんぽを使うコツは、寝る前まではおなかのあたりに置いておくこと。そして、寝るときに布団に入るタイミングで足元に移動させます。そうすると全身がほどよく温められ、体温の低下を防ぐとともに質のよい睡眠を得ることも期待できるでしょう。
(8)良質な睡眠、栄養バランスが整っている食事を心がける
免疫力や抵抗力が低下しないように、睡眠やバランスの良い食事をすることが最重要です。睡眠不足、食事の内容が偏っている、また食事時間が不規則、疲れている、ストレスがあるときに風邪を引きやすいことは経験的に皆さんもご存知でしょう。休養と栄養補給は常に意識しましょう。
手洗いやマスクの扱い、水分を取るなど、一つひとつは難しいことではありませんが、「続ける」、「習慣にする」ことができるかどうかがポイントだということです。また、湯上りや就寝時にちょっとした工夫をするだけで風邪予防になりえるということです。新しいルーティンとして、ぜひ毎日の暮らしに取り入れたいものです。
(取材・文 ふくいみちこ×ユンブル)