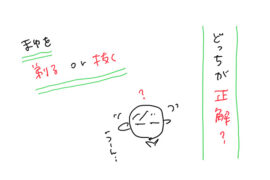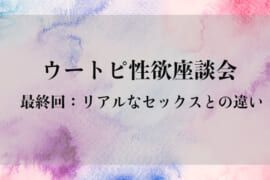便秘が続くときは体も心もすっきりせず、水分をとったり、食物繊維が豊富と言われるものを食べてみたりしますが、結局、下剤に頼ることも少なくありません。
臨床内科専門医で正木クリニック(大阪市生野区)の正木初美院長は、「便秘の原因は水分不足や食物繊維不足と思われがちですが、無理なダイエット、ストレス、運動不足など、さまざまな要因が挙げられます。要因や症状によって便秘の種類が異なるので、自分に合った対処法を知る必要があります」と話します。詳しく聞いてみました。
排便に不快感や苦痛があれば便秘
正木医師ははじめに、「便秘とは、排便の回数や量に関わりません」と言い、こう説明します。
「『便が硬くて量が少ない』、『残便感があってすっきりしない』、『排便に苦痛を感じる』、『薬を飲まないと便が出ない』など、本人が排便に不快や苦痛を感じる場合を、便秘と考えます。
いずれも便が腸内に長く停滞するため、肌荒れ、吹き出もの、肩こり、腰痛、疲労感、イライラなど、心身にさまざまな不調を引き起こします。
また便秘には、一時的や慢性的、また、腸の状態によって弛緩(しかん)性やけいれん性、便意に関わる直腸性など、種類があります」
そこで正木医師は、「自分の便秘の種類を見分けましょう」と、次のポイントを挙げます。どの項目に当てはまるかを確認してください。
(1)旅行や出張などで生活環境が変わった。
(2)普段は快便だが、急に便秘になった。
(3)暴飲暴食である。
(4)ダイエットを始めた。
(5)ストレスを感じることが起こった。
(6)デスクワークや立ちっぱなしなど、同じ姿勢を続けることが多い。
(7)運動不足である。
(8)硬くコロコロとした便で、残便感がある。
(9)頻繁にダイエットをしている。
(10)おなかが張っているのに、何日も便が出ない。
(11)便秘と下痢を繰り返す。
(12)ストレスや疲労、睡眠不足などが続いている。
(13)食後に、下腹部が痛くなることがある。
(14) 便意があるのに、トイレに行けず我慢することが多い。
(15) 便意をあまり感じない。
(16) 便が硬く、排便時に肛門に痛みや違和感がある。
(17) 排便に時間がかかる。
次に正木医師は、チェックした項目ごとに、便秘の種類と対処法をこう解説します。
(1)~(5)に当てはまる……一過性便秘
<原因>
これまでは便秘の自覚がなかったのに、環境の変化、緊張やストレスなどのメンタル面、食生活の乱れなどの影響を受けて、一時的に便秘になります。
<対処法>
それぞれの原因を改善し、規則正しい生活習慣を送る、環境の変化に慣れる、自分なりにストレスを解消すると、元の排便リズムに戻るケースが多いでしょう。ただし、放っておくと慢性的な便秘になる可能性があります。
(6)~(10)に当てはまる……弛緩性便秘
<原因>
運動不足などで筋力が衰えると、腸のぜん動運動が弱まり、便がスムーズに送り出されずに便秘になります。女性に多く見られます。
また、摂取する食事や食物繊維の量が少なくて十分な便が作れない、たまった便の水分が腸に吸収されて硬い便になって排便しづらくなるなど、慢性的な便秘につながることがあります。
<対処法>
朝コップ一杯の白湯を飲む、軽く汗ばむくらいの運動をする、乳酸菌や食物繊維を多く含む食材をとるなどして、腸のぜん動運動を促しましょう。
(11)~(13)に当てはまる……けいれん性便秘
<原因>
精神的、肉体的に強いストレスを受けていると、腸のぜん動運動をコントロールする自律神経に影響を及ぼし、腸の一部がけいれんを起こしたような状態になります。すると、便がスムーズに送り出されずに、便秘になります。
<対処法>
ストレスの原因を見つめ直し、ストレッチやウォーキングなどで体を動かす、好きな音楽を聴く、趣味の時間を大切にするなど、リフレッシュする方法を見つけて実践するようにしましょう。
(14)~(17)に当てはまる……直腸性便秘
<原因>
排便を我慢し続けると、便が直腸まで運ばれても便意を感じにくくなります。また、便秘薬を長期的に服用していると、直腸が鈍感になって大腸に排便のサインが届きにくく、さらに便秘になる悪循環をまねくことがあります。
<対処法>
便意をもよおしたときは我慢せず、トイレに行きましょう。便意の有無にかかわらず、決まった時間にトイレに行って、排便の習慣をつけるのもいいでしょう。
最後に正木医師は、便秘対策についてこうアドバイスを付け加えます。
「便秘の原因や種類は一つとは限らず、複数の要因が組み合わさっていることもしばしばです。まずは、『栄養バランスがよい規則正しい食生活をする』、『十分な睡眠をとる』、『適度な運動をする』よう心がけましょう。
また、食べ物が胃に入ると大腸に信号が送られて、腸が動いて便を直腸に送り出そうする『胃・結腸反射』と呼ぶ反応が起こります。これは特に朝食後に強く起こるため、15分以上かけてゆっくりと朝食をとりましょう」
便のタイプや原因を振り返り、食事、睡眠、運動を基本に、自分の便秘の種類に合わせた対策をとる必要があるということです。
(取材・文 岩田なつき/ユンブル)