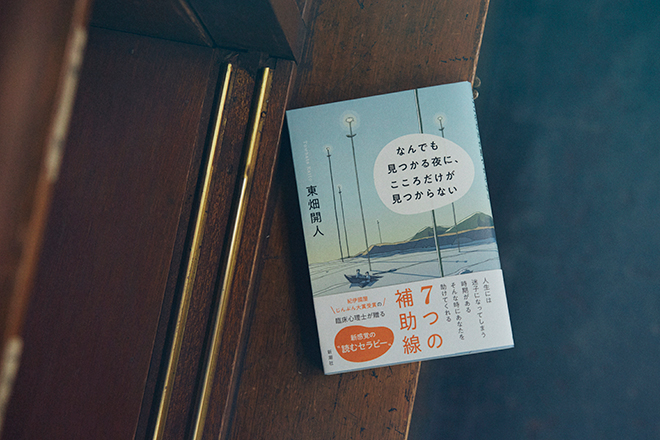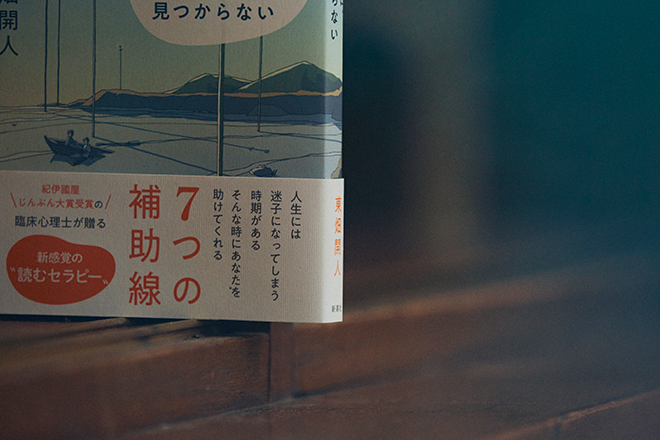心理士として15年、人々の心の問題に向き合ってきた東畑開人(とうはた・かいと)さん(39)による新刊『なんでも見つかる夜に、こころだけが見つからない』(新潮社)が3月16日に発売。1週間足らずで重版が決定し、話題を呼んでいます。
これまで私たちを守ってくれていた社会のしくみやつながりが壊れ、遭難しようが沈没しようが自己責任の“小舟化した”社会。自由だけれど気がつけば孤独に陥りやすい社会で私たちはどんなふうに生きていけばいいの?
東畑さんに3回にわたってお話を伺いました。第1回目のテーマは「傷つくかもしれない関係の価値」です。
大船から小舟の時代へ…今、必要とされる心理学の本を書きたかった
——同書は深層心理学者のユングの言葉「夜の航海」をコンセプトに書かれています。「夜の航海」は誰の身にも起こる人生の危機の時期を指すそうですが、執筆されたきっかけを教えてください。
東畑開人さん(以下、東畑):「読者の役に立つ本を一冊書きたい」というのが出発点にありました。読者が自分のことを考えるきっかけになるような本を書きたいと思っていたんです。“大船”が主だった時代は、心理学者の河合隼雄がそういう役割をしていたんですけれど、当時とは時代もだいぶ変わりました。「今の時代に合わせた本を、心理士として一冊書けたら」という思いでした。
そんなふうに考えていたときに、「夜の航海」という言葉が出てきたんです。今の時代は、すごく自由だけれども誰も責任を取ってくれない。つまり、方向を自分で決めなきゃいけない。河合隼雄は、向かう方向が決まっていた“大船”の時代に、違う方向で生きていく勇気を与えてくれましたが、今の時代は方向が決まってないから、方向自体を自分で見いだしていかなければいけません。
調子が良いときはスイスイ進んでいけるけれど、ときどき方向が分からなくなって、もう一回考え直さなければいけないときもある。そんなときに、人はカウンセリングに来るんだろうなと思ったんです。これが大きなコンセプトとしてありました。
——図形の問題を解くために使う“補助線”になぞらえた「心の補助線」というのも分かりやすかったです。補助線によって複雑な心を分解すると、自分の中にどんな思いがあってどう葛藤しているのかが見えてくる。
東畑:最初は『こころの処方箋』(1998年、新潮社)のダジャレだったんですけど、心理学は本質的に「補助線」なんだと感じています。心って実態がないので、補助線を使って便宜的にいったん整理してみました。第二章では「馬とジョッキー」という補助線を登場させましたが、何が馬(心の衝動や欲求に突き動かされる部分)で何がジョッキー(現実を把握して心のかじ取りを担っている部分)なのかはそのときどきで違います。
結局、カウンセリングというのは自分が考えたり、整理したりするために人に話をするものです。もちろん、クライエントに「何をするべきです」と告げるときもあるのですが、究極的には「補助線」を提供する仕事なんだと思います。
——心理学で「補助線」という言い方をするんですか?
東畑:あまりしないのですが、だからと言ってオリジナルな言葉でもないような気がします。心理士は何となくみんな思っているんじゃないかな? 心を考えるって、そういうことだと思うんですよね。「間違っているかもしれないけど、その線で考えてみる」というか……。
今の時代だからこそ求められている「ナイショの関係」
——今回の本では、七つの「補助線」が提示されています。
東畑:一番書きたかったのは、「シェアとナイショ」(4章、5章)の部分なんです。
——どういうことですか?
東畑:ここ10年ぐらい、SNSで「シェアしよう」とか「シェアリングエコノミー」とか「シェアハウス」とか、「シェア」という言葉が浸透して良いところがたくさん語られてきました。シェアは確かに良いのだけれど、一方でいろんなリスクも孕(はら)んでいます。「シェア」という言葉の軽やかさに対して、もう一つのシリアスな問題として人間関係にみんな苦しんでいる。でも、みんな何となく「シェア」のロジックで語っちゃうので、一対一の親密な「ナイショ」の関係の良さみたいなことが語られにくい。それはやっぱり、バランスを欠くのではないかと感じていました。
——確かに「ナイショの関係」と言うと、昭和というかクローズドなイメージがあってちょっと重いなと思ってしまうかも……。
東畑:そうなんです。「ナイショの関係」と言うと、みんな昭和的なナイショの関係をイメージするんですよね。「家父長制の中で抑圧される、自由を奪われる」というようなイメージ。でもむしろ、みんなが“小舟”で生きるようになった今の時代は、ナイショの関係で人と人が深くつながっていくんです。本の中では、「二人がそれぞれの小舟を降りて、一つの小舟に乗り込んだかのよう」という表現を使いましたけど、昭和のときとは違ったナイショの関係が、今必要とされていると思いました。
例えば、「親戚の目があるから離婚しない」というのは昭和的だし、ただの不自由だけれど、自由な時代でいつ離婚してもいいのに「この人と一緒にいることを選び取っていく」というのはお互いの人生に責任を持っていくあり方ですよね。そんなふうにナイショの関係の抑圧的ではない側面を語りたかったというのはあります。
——「ナイショのつながりとは、傷つけあう関係のこと」とありましたが、自分を振り返ってみても、傷つきが怖いあまり密接な人間関係を避けてしまう部分があるなあと思いました。
東畑:一緒に暮らしていても、本当のことは話せないとかね。
本の中でも、「“本当の自分探し”の時代から、“本当のつながり”へ」というようなことを書いたと思うんですけれど、「他者とつながるために本当の話をするって、どういうことなんだろう?」ってなりますよね。自分が苦しいことをシェアすることはあるけれど、僕は相手との一対一の関係において、「あなたのこれに傷ついていた」と言うことに価値があることを、この本の中では強調したかった。つまり、2人の関係について、2人でしっかり話をする。周りの人から見たら理解できないことでも、「2人にとっては真実である」ということがあるじゃないですか。それを、変に単純化しないでできるだけ複雑に話し合うんです。「面倒くさい話をしよう」ということですね。それが、「ナイショの関係」というものだと思います。
特に今の時代は「なぜ分かってくれないの?」と言いにくいとは思うのだけれど、そう言えないからいろいろな別のことをしてしまうわけで……でも、やっぱり「なぜ分かってくれないの?」と言ったほうがいいんじゃないかなと思います。
——「ナイショをめぐる傷つけあいは、あなたを相手と一緒にいられる形へと研磨していく」とあったように、傷つきは確かに怖いけれど、それでもやっぱり誰かとナイショの関係を築いて「本当のつながり」を持ちたいと思いました。その際にベースとなるのが傷つかない「シェアの関係」ということでしょうか?
東畑:そうです。「ナイショの関係」って、傷つかない関係である「シェアの関係」の後にくる話なんですよね。例えば、少女マンガは、主人公の女の子と相手の男の子が向き合っていく話なのだけれど、あれは、周りにいる登場人物たちとの熱い友情がすでにあるから、「相手と向き合ってみよう」という話になるわけで。「シェアの関係」が先にあるんですよね。周りの人にいろいろな相談をしたり、愚痴をこぼしたりできるから、ナイショの関係に進むことができる。そういう構図だと思うんです。
——安心できるんですね。
東畑:本当に周りに助けてくれる人や友達がいなくて、「ナイショの関係」だけがあるのは、搾取的です。シェアのつながりが「ナイショの関係」に進むためのきっかけになると思います。
「傷つけ合うことの価値」を書いた本
——本になるまで、3年かかったと伺いました。振り返ってみて、執筆時の苦労などはありましたか?
東畑:振り返ると、死ぬほどつらかったですね(笑)。「補助線はこういうふうに分けられます」って書くだけだとリアルじゃないし、読者も腑(ふ)に落ちないのでは、と思いました。血肉の通った「補助線」にするためには、具体的なエピソードが必要だと思いました。
この本は、傷つけ合うことの価値を書いている本でもあります。傷つけ合うことはもちろん良くないんだけど、「他者と傷つけ合わないと孤独になってしまうよ」という理論です。でも、本当に傷ついている方もいっぱいいますから……。そこをきちんと書けるようになるのに、3年くらいかかりました。
——意地悪して傷つけ合うとかではなく、人間のやりとりとして傷ついちゃった、傷つけちゃったということですよね。
東畑:そうなのですが、「傷つけ合うのが怖い」「傷つけ合いを避けたい」という思いも非常によく分かる。ただ、それだけでは……というところなんですよね。単に傷つけ合うだけでは“昭和のおじさん”になっちゃうわけだし、傷つけ合わなければいいというのも違うと思っていて……。「傷つけないのは大事だけど、傷つけ合うこともある」ということをうまく言葉にするのに、すごく時間がかかりました。
※第2回は4月12日(火)公開です。
(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)