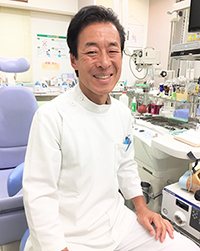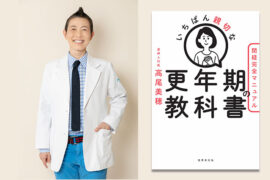「耳鼻咽喉科では風邪もインフルエンザも診てくれるの? どんな診療科?」などの疑問について、耳鼻咽喉科・気管食道科専門医で『免疫入門 最強の基礎知識』(集英社新書)の著書がある遠山祐司医師に連載で尋ねています。
前回(耳鼻咽喉科①)、耳鼻咽喉科では、鼻炎や中耳炎、難聴のほか、風邪やインフルエンザ、嗅覚障害、味覚障害、めまい、花粉症などのアレルギー性鼻炎、いびき、ドライマウスなどの場合も専門的に診察すると教えてもらいました。風邪や鼻炎の際の鼻やのどの処置は、内科とは違う処置法があるという情報も印象的でした。
今回は、新型コロナウイルス感染症の症状のひとつとしても注目されている嗅覚障害について、そのメカニズムや検査法、治療法について尋ねます。
なお、「この不調、何科へ行けばいい? 診療科ナビ」の第1回・消化器内科、第2~4回・精神科、第5回・心療内科、第6回・耳鼻咽喉科①については文末のリンク先を参照してください。
鼻の奥の上のほうににおいを感じるセンサーがある
——前編で、嗅覚障害は、新型コロナウイルス感染症だけではなく、風邪やインフルエンザ、花粉症などのアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎でも起こること、また、「感冒後嗅覚障害」という、通常の風邪でも後遺症となる病気があるということでした。鼻のどこがどうなってにおいがわからなくなるのでしょうか。
遠山医師:左右の鼻腔の奥の天井のほうには、約1センチ四方のにおいのセンサーとなる嗅粘膜があります。そこには300万~500万もの嗅細胞が存在しています。外部から鼻ににおいの分子入ってきて嗅細胞を通過すると、興奮が嗅神経を経て大脳に伝わってにおいを感じます。
カレーやコーヒーなど、強くて特徴的なにおいを感じるときをイメージしてください。鼻から流入したにおい分子が、鼻腔の奥の上のほうにあるごく小さなセンサーがスイッチの役割をしてにおいを感じているわけです。
そのにおいセンサーは、ウイルスや細菌、異物によってダメージを受けたり、炎症が起こったりすると一時的ににおいがわからなくなることがあります。これを「嗅神経性嗅覚障害」といいます。風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症などによって起こります。風邪が治っても長く続く感冒後嗅覚障害や新型コロナウイルス感染症の後遺症の原因といわれます。
炎症から回復して嗅覚が戻るまでには、1カ月から3年ほどかかる場合があります。ただし、若い人では時間がかかっても薬なしで自然に治るケースが多く見られ、そのうち30~40%の人は1年以内に回復しています。
鼻づまりでにおいが分からなくなる原因は
——においセンサーがウイルスによって故障するイメージですね。花粉症などのアレルギー性鼻炎のときにも、においがわかりにくくなりますが、それはまた違う原因なのでしょうか。
遠山医師:従来の風邪やアレルギー性鼻炎に伴う嗅覚障害の原因は、主に鼻づまりです。鼻がつまる場所は、においセンサーがあるところとは違って、鼻腔の下の前端です。そこにむくみや腫れが生じて鼻がつまります。
そこは空気の通り道です。むくみや腫れがあると道が狭くなって呼吸がしづらくなり、鼻がつまったと感じるわけです。そして鼻がつまると、においの分子がにおいセンサーまで届きにくくなるため、においを感じにくくなります。新型コロナウイルス感染症の場合でも、鼻がつまると起こります。これを「気導性嗅覚障害」といい、鼻づまりが治ると嗅覚障害も治ります。
嗅覚障害には、もうひとつ、「中枢性嗅覚障害」があります。これは外傷などで脳に障害があってにおいを認識しにくい脳挫傷、脳出血、脳しゅよう、脳梗塞(こうそく)や、パーキンソン病、アルツハイマー型認知症などの神経変性疾患の場合に起こりやすいことがわかっています。
嗅覚障害の診察、検査、治療法は
——感冒後嗅覚障害や新型コロナウイルス感染症では、嗅神経性嗅覚障害と気導性嗅覚障害のどちらか、または両方を併発している可能性があるということでしょうか。
遠山医師:そうです。新型コロナウイルス感染症では症例の蓄積と分析が進んでいるところですが、現在のところ、風邪のときのように鼻づまりがなくても、突然に嗅覚障害が起こるケースが多いのが特徴です。
——どういう検査や治療を行うのでしょうか。
遠山医師:診察には、症状を尋ねる問診をし、内視鏡による鼻腔の検査、アリナミン注射による静脈性嗅覚検査などのほか、必要に応じてX線、CT、MRIで鼻腔、頭部の画像撮影を行います。
治療はその程度やほかの病気の有無などによりますが、第一選択としてステロイド点鼻療法を行います。点鼻療法とは、薬剤を鼻腔天井部の嗅上皮に届くように鼻に垂らしてしみこませていく方法です。また、抗生物質や抗アレルギー剤、ステロイド剤、漢方薬や亜鉛製剤などを服用します。
薬以外の治療では「嗅覚トレーニング」を行う場合があります。例えば、コーヒー、ミント、レモン、アロマオイルなど、いくつかのにおいの素(嗅素)を毎日2~3回かいで認知機能を向上させる方法です。
——嗅覚障害をいち早く自覚する方法はありますか。
遠山医師:コーヒーやカレーをかいでみて、いつもよりにおいを感じなければ、発症しているかもしれません。
これらの検査法や治療法はすべての耳鼻咽喉科で行っているわけではありません。まずはかかりつけ医に相談して専門の医療機関を紹介してもらうか、ホームページで耳鼻咽喉科専門医のいる医療機関を探しましょう。また、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は直接医療機関を受診するのではなく、かかりつけ医や自治体の相談窓口(ホームページに掲載されています)に電話をして、近隣の受診可能な医療機関を尋ねてください。
聞き手によるまとめ
嗅覚障害は、新型コロナウイルス感染症だけではなく、風邪や鼻炎のとき、また風邪が治ってからも長く続く場合があること、その種類は原因によって3種類があるということです。においがわかりにくいかもと思ったときは、コーヒーやカレーなどの特徴的なにおいをかいでみて、嗅覚にダメージがないかどうかを確認したいものです。
次回は、「耳鼻咽喉科ナビ③ 味覚障害」について尋ねます。
(構成・取材・文 藤井 空/ユンブル)