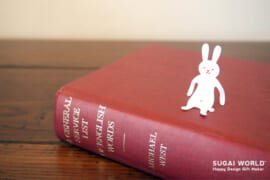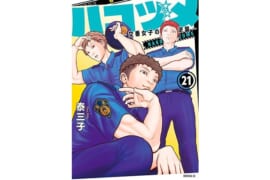ひがみ、ねたみ、そねみなのか、無邪気なのか。アドバイスかクソバイスか……。私たちをモヤっとさせる言葉を収集する「モヤる言葉図鑑」。
作家のアルテイシアさんと一緒に「モヤる言葉」を観察していきます。今回は「〇〇なんて関係ないよ」です。
ジョンとジェニファーの実験が可視化するもの
ジョンとジェニファーの実験をご存じだろうか?
これは2012年にアメリカで行われた実験で、まったく同じ履歴書の名前のみをジョンかジェニファーかに変え、求人に応募するというものだ。
実験の結果、ジョン(男性名)の方が高い評価を受け、年収も高く提示された。(参考文献『ジェンダーについて真剣に考えてみた――あなたがあなたらしくいられるための29問』(明石書店))
これは男性が履いている下駄(=特権)をわかりやすく示している。
ジェンダーギャップ指数30位のアメリカですらこうなのだから、いわんや日本をや(反語)
ジェンダーギャップ指数120位のヘルジャパンで「太郎と花子の実験」をしたら、雇用格差や賃金格差はさらに大きくなるだろう。
そこで太郎が花子に「性別なんて関係ないよ」「本人のやる気と実力次第だよ」と言ったら、花子はバチギレるだろう。
「それはあなたが性別で差別されずにすむからだよね?」と。
たとえば、履歴書で落とされた時に「俺が男だから落とされたのかも」と考える男性は少ないだろう。
また女性は応募する企業の女性社員や女性管理職の割合を気にするが、男性社員や男性管理職の割合を気にする男性は少ないだろう。
このように“考えずにすむこと”“気にせずにすむこと”が特権なのだ。そのため、人は自分が持つ特権に気づきにくい。
「そんなの関係ないよ」と言えるのは…
「人種差別をなくす実験授業」というイギリスのドキュメンタリー番組を見た。
これは学校の授業の中で、11歳の生徒たちに「差別や偏見を減らすプログラム」を3週間行うという内容だった。
プログラムを受ける前、白人の男の子が「人種なんて関係ないよ」「僕はそんなの気にしたことないよ」と話していた。
その後、子どもたちは様々なプログラムを体験する。
たとえば校庭に横一列に並んで「今から徒競走をします」と言われる。そしてヨーイドンの前にトレーナーから以下のような指示を受ける。
「差別に気をつけて、と親から言われたことのある人は一歩下がってください」
「警察に職務質問されるんじゃないか?と心配した経験がない人は一歩進んでください」
するとスタート地点の距離がどんどん離れていき、子どもたちは前方にいるのが白人だけだと気づく。
その結果、差別の構造を直感的に理解することができる。
「人種なんて関係ないよ」と言っていた男の子は「僕がそう言えるのは、人種を理由に差別されずにすむからだ」と自分の持つ特権に気づく。
また、黒人の生徒が「万引きするんじゃないか?と店員にジロジロ見られるのがつらい」と話したり、白人の生徒が「あいつは人種差別者だ、と周りに誤解されるのが怖い」と話したり、それぞれの体験や気持ちを素直に語り合えるようになる。
この3週間のプログラム終了後、生徒たちのアンコンシャスバイアス(無意識の偏見)が著しく減少した、という結果が出る。
これやがな!!
と私は膝パーカッションを打ち鳴らした。子どもは周りの大人をお手本にして育つ。我々大人にもこういう教育が必要やがなと。
偏見の全くない人間はいない
不適切発言をした際に「差別する意図はなかったフンガフンガ」と言い訳するマンは多いが、そっちに踏むつもりがなくても、踏まれた側は痛いのだ。
無意識に誰かを踏まないためには、差別や偏見について学ぶ必要がある。
「自分は偏見がない」と思っている人ほど差別や偏見に鈍感で、うっかりやらかしがちだ。「偏見の全くない人間はいない」と肝に銘じて、注意することが大切だろう。
かくいう私もうっかりやらかしマンだった。
たとえば新入社員の時に「〇〇ちゃんは女子だけど、同期で一番優秀なんだよ」とか発言していた。
「男子だけど優秀」とは言わないわけで、この男尊女卑アレルギーの私の中にも「女は男より劣っている」という偏見があったのだ。
恐ろしい子…!!
と白目化するぐらい、アンコンシャスバイアスは手ごわい。なんせアンコンシャスなもんだから、自覚するのが難しい。
「あたしったら……うっかりミソジニー発言しちゃうみそっかす」と気づけたのは、私がフェミニズムに出会ったからだ。
ブツブツブツ……とフェミニズムの本を読んで学ぶことで「学び落とし」することができた。
私の目が黒いうちに、紅天女を見たい。じゃなくて、差別や偏見に苦しむ人のいない社会を見たい。
そのためには、それぞれが自分の特権を自覚することが大切だろう。
「〇〇なんて関係ないよ、気にすることないよ」(〇〇に入るのは、性別、人種、セクシャリティ、障がい、宗教、学歴…等など)と言いそうになった時に「それを言えるのは、自分がマジョリティ側だからでは?」と考えてみること。
そうすれば、うっかりやらかしマンにならずにすむ。
善人でも差別することはある
また「善人でも差別することはある」と肝に銘じることも大切だ。
拙著『モヤる言葉、ヤバイ人』(大和書房)に書いたが、ドイツに住んでいた友人は「人種なんて関係ないわ」「私はアジア人に偏見がないから、あなたと友達になりたいわ」とめっちゃ優しいドイツ人たちから言われたそうだ。
発言した側に悪気はないのだろうが、言われた側は「あなたは私とは違う、本来は差別されるマイノリティだけど受け入れてあげますよ」というマジョリティの上から目線を感じる。
自分は善人だと思っている人は「あなたの発言は差別的ですよ」と指摘されたら、ショックを受けるだろう。
だからこそ、周りは指摘しづらいのだ。「でもまあいい人だし」「悪気はないんだろうし」と遠慮してしまうのだ。
私も麻生太郎に「婦人に参政権を与えたのが最大の失敗だった」とか言われたら「ふざけんなコノヤロー!!」とアウトレイジできる。
一方、めっちゃ優しいおじいさんに「やっぱり女性のいれたお茶は美味しいねえ」とか言われても「それ千利休に言ってみろ!!」と茶をぶっかけるわけにいかない。
何度も言うが、偏見の全くない人間はいない。特にこの日本で生まれ育って、男尊女卑を刷り込まれてない人はいないと思う。
たとえば「自分もジェンダー平等に賛成だ」という男性が、配偶者を「嫁」「家内」と呼んだりする。それジェンダー平等に矛盾してますよ、と指摘されるとキョトンとする。
みたいなことはあるあるで、彼らには悪気はないけど知識もない。知識を得るために努力しないのは、「ジェンダー差別は自分には関係ない」と他人事だからだろう。
そんな無関心な善人に届きますように…とこつこつコラムを書き続ける我(体言止め)
私は難しい文章は書けないので「ミソジニー?それどんな汁物?」みたいな人でも読みやすいと思う。
私の読者は女性が多いが、最近は男性からも感想をぽつぽついただくようになった。
「自分もうっかりやらかしマンだったから、耳が痛い」という感想が多いが、耳が痛い言葉に耳を傾ける姿勢こそが、なにより大切で尊いものだ。
批判された時に「俺は悪くない!」「いちいち騒ぐ方がおかしい!」と逆切れするマンは、永遠に変われない。
人はみんなアップデートの途中なのだ。あれは間違っていたなと気づいたら、反省して改めればいい。変わらなきゃと気づいたなら、そこから変わればいい。
過去は変えられないけど、未来の言動は変えられるのだから。
人は自分の特権を認めたがらない
前出の友人がドイツに住んでいた頃、ドイツ人の夫とレストランに行った時と日本人の友達と行った時では、店員の態度が違ったという。
その話を夫にすると「気にしすぎじゃない?」「きみはちょっと敏感すぎるよ」と言われたそうだ。
友人いわく「夫は高学歴のエリート白人男性で、バリバリの特権を持つ強者だけど、本人はそれを認めなかった」とのこと。
「僕は特権なんて持ってない、ここまで必死に努力してきたんだ」と夫は主張していたという。
このように、人は自分の特権を認めたがらない。
たとえば、アメリカの大学で白人の男子学生に「白人であること、男性であることは特権だ」と言うと「自分は貧乏暮らしで苦労している、だから特権なんてない」と否定するようなケースが多いという。
特権を持っている=人生薔薇色でイージーモード、という意味ではない。“その属性”を理由に差別される機会が少ないことが特権なのだ。
みたいなことをみんなが理解すれば、差別や偏見を減らせるし、多様な人々が生きやすい社会になるだろう。
同質性の高い環境ではマジョリティは自分がマジョリティだと思わずに生きているため、自分のもつ特権に気づきにくい。
それこそ、政治やメディアのトップにいるのは高学歴エリートのおじさんやおじいさんがほとんどだ。
社会が大きな教室だとすると、エリート男性は一番前の席に座っている人たちだ。後ろの席の人からは黒板が見えづらいし、授業の声も聞こえづらい。
一番前の席で後ろを振り返ったことのない人には、それがわからない。
弱い立場の人やマイノリティの存在が見えないから、「本人の努力が足りない」「自己責任だ」といって、社会の構造を変えようとしない。
「俺だって必死に努力してここまで来たんだ」と彼らは主張するが、そもそもスタート地点に立てない人が見えていない。
そんな人ばかりが政治やメディアの世界にいたら、視野が偏るのは当然だろう。よって同質性の高いメンバーから、多様性のあるメンバーに変える必要がある。
たとえば、欧米の公共メディアでは多様性の確保に取り組んでいる。
英国BBCでは職員やスタッフの雇用において、多様性(年齢、性別、人種、セクシャリティ、障がい、宗教など)を反映して、全職場で機会均等を目指すことを表明している。
一方、日本のメディアは女性社員や女性役員の少なさが問題視されている。女性の政治家も諸外国と比べて極端に少ない。
世界では100カ国以上がクオータ制を導入して女性議員が増えているのに、日本の衆議院では女性が1割以下しかいない。
おまけに女性の政調会長が選択的夫婦別姓に反対したり、「男女平等は絶対に実現しない妄想」だの「LGBTは生産性がない」だの発言する女性議員もいて、白目化が止まらない。
けれども、時代の流れは止まらない。
2017年に#MeTooや伊藤詩織さんの告発があり、性暴力や性差別に対する意識は大きく変わった。
森喜朗氏の女性蔑視発言、検察庁法改正、入管法改正の時もSNSで抗議の声が広がり、政治を動かした。1人1人が声を上げることで、社会は変えられることを証明したのだ。
小さな声が集まると大きな声になる、すると政治家は無視できなくなる。
「男尊女卑を守りたい」「多様性なんていらない」とか言っててももう無理なんやぞ!!と気づかせるために、私はこれからも声をあげ続ける。そう簡単に変わらなくても、たとえ時間がかかっても、絶対に諦めないと決めている。
「諦めたらそこで試合終了ですよ」を合言葉に、みんなで少しでもマシな社会にしていこう。どすこい。
(イラスト:飯田華子)