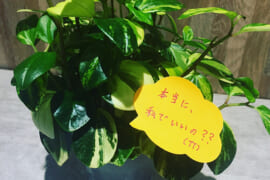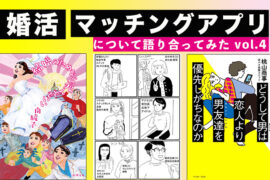パソコンやスマホの操作に10分ほど集中しただけで、肩や首、背中がガチガチになるといった経験はありませんか。
理学療法士・鍼灸師でアース鍼灸整骨院(千葉県市川市)の仲川豊基(なかがわ・とよき)院長は、「短時間でも同じ姿勢をとっていると痛むというのは、けんこう骨の関節や筋肉が硬くなっているからでしょう」と話します。
そこで、けんこう骨まわりのガチガチを改善するストレッチ法を教えてもらいました。
まずは、けんこう骨の硬さをセルフチェック
はじめに仲川さんは、けんこう骨の周囲が柔らかくなることのメリットについて、こう説明をします。
「けんこう骨の関節が柔らかくなると、肩の関節への負担が減って肩や腕が大きな範囲で動くようになります。血流も促されます。そうすると、けんこう骨や肩にかかる負荷が分散されて、疲れにくい体になると言えるでしょう。硬かったときより代謝もアップします」
ここで仲川さんは、「けんこう骨の硬さを自分でチェックする方法」として、次の動作を提案します。まずは試してみてください。
右の腕を背中に回して、おや指を上に向けます。そのおや指が左右のけんこう骨の「内側のふち」まで届くかどうかをチェックしましょう。無理に届かそうとせずに、自然に届く範囲を確認してください。次に左の腕で同様に試しましょう。
このとき、左右のけんこう骨におや指が届かない場合は、けんこう骨が硬いと判断しましょう。また、猫背になっている可能性もあります。さらに、二の腕や肩、背中のどこかが痛む場合も同様です。右と左で届きかたが違う場合は、左右のけんこう骨の柔軟性のバランスがとれていないと自覚しましょう。
その上で、左右両方が届くようになることを目標として、次に紹介するストレッチを続けてください。届いていれば現状維持でOKですが、オーバーワークや疲れたとき、しばらくストレッチや運動をしなかったときなどには届かないことがあります。時おり、セルフチェックをしましょう。
けんこう骨柔らかストレッチ3選
「けんこう骨を柔らかくするとは、けんこう骨が動く範囲、可動域と言いますが、それを大きくするということです。同じ姿勢や動作しかしていないと関節や筋肉は硬くなりがちです。普段とは違う動きを取り入れることを意識してストレッチをしましょう」と、仲川さんは次の3つの方法を紹介します。
(1)組み手アップストレッチ
両手のひらを組んで腰に回し、手のひらは後ろに向けます。胸を開くようにひじを寄せていきましょう。慣れてきたら組んだ手の位置を上げて、5秒ほどキープします。これを5~10回ほど繰り返しましょう。胸を開き、けんこう骨を寄せるエクササイズにもなり、肩こりを改善します。デスクワーク中にいつでもできる動作です。
(2)わき腹ストレッチで効率アップ
両方の手を頭の上にして、まず右のひじを左の手で包むように持ちます。包んだ手でひじを下方に向かって力を加えます。右の二の腕から首、背中、腰まで伸びるように感じるでしょう。さらに、上体を左側に倒して、右のわき腹を伸ばします。この状態で10~15秒ほどキープし、元の姿勢に戻ります。反対側も同様に行い、両方で1回として3~5回、繰り返します。
わき腹が硬いと、腕が上がりにくい、横に倒しにくくなります。左右のどちらかが硬い場合は、硬いほうを1・2回多く伸ばし、バランスをとりましょう。
肩の可動性を高めるストレッチです。オーソドックスな方法ですが、(1)~(3)の流れの中で「わき腹を伸ばす動作」が加わることになり、けんこう骨のストレッチとしてかなり効率が上がります。
肩や背中の筋肉は、寝ているとき以外は常に、手の重みで引っ張られています。時おり、手を上げて伸ばし、負荷を分散するようにしましょう。
(3)けんこう骨ぐっと寄せストレッチ
左の足を前に、右の足を後ろに大きく一歩ずらして立ちます。次に両方の手を組んで腰に回し、上体を前にゆっくりと倒しながら、組んだ手の甲を天井に向けて上げます。けんこう骨をぐっとよせ、ひじをできるだけまっすぐ上に向かって伸ばしましょう。10~15秒ほどキープし、元の姿勢に戻ります。次に左右の足を入れ替えて同様に行い、両方で1回として3~5回、繰り返します。
けんこう骨だけではなく、背中、腰、前に出した足が伸びるのを感じるでしょう。全身のストレッチにもなります。一方、足を前後に出すことで下半身が安定し、肩からけんこう骨のストレッチに集中できるというメリットもあります。
これらを行うタイミングについて、仲川さんはこうアドバイスをします。
「長時間座っているなど、同じ姿勢を続けている最中にもできる範囲で行ってください。そのうえで、立ち上がったときに全部を通してするようにしましょう。デスクワークや長距離の運転、フライト中、映画館や劇場で長く座っている、あるいは仕事や行列、フェスなどで立ちっぱなしなどの場合に覚えておいてください」
さっそく試したところ、まずセルフチェックで右の手が左よりおや指の高さ1本分ほど上がらないことに気づきました。右の方が硬いということにほかなりません。(2)のわき腹は、右側を2回ほど多く伸ばすことを毎日数回、続けています。気持ちがいいので、特にデスクでパソコン操作中に何度も実践するようになりました。「肩こりを感じる前に行うことがコツ」(仲川さん)ということです。ぜひお試しください。
(取材・文 海野愛子/ユンブル)