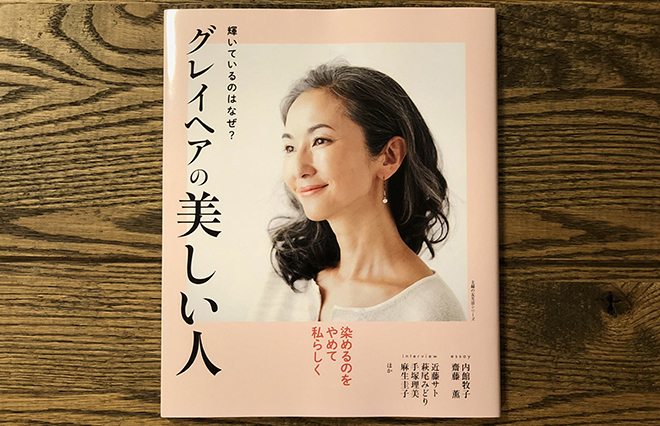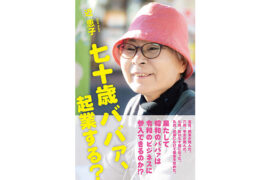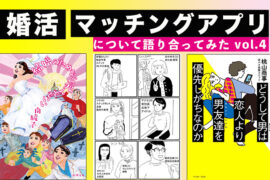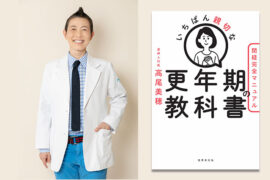誰もがなんとなく頭に思い描く「理想の家族像」。でもそれっていつの時代のもの? その「理想の家族」を手に入れれば、幸せになれるの?
前回に引き続き、『生涯未婚時代』(イースト・プレス)を上梓した、永田夏来(ながた・なつき)さんに、これからの家族のカタチについて話を聞きました。
自分の家庭=常識と思いがち
——前回、従来の家族のカタチに還る人は応援されやすいと伺いました。でもそれは本当の意味で多様性を認めているわけではない、と。なぜそんなことになるんでしょうか?
永田夏来さん(以下、永田):家族に関することって、基本的にみなさん、自分の経験を基準に考えますよね。たとえば政治家とか、政策に関わる人、大手メディアにいる人。彼らは自分の経験として奥さんが専業主婦をしていて、子どもがいる。将来的にも年金がもらえるだろうという暮らし方ができている。
それってこれからのスタンダードだとは必ずしも言えないのですが……。それを基準に考えてしまうと、「自分もできるんだからみんなも頑張ればできるよ」と思ってしまうんでしょうね。
——ああ。何となくわかる気がします。外から見るとおかしいよって思うことでも、「自分の家庭=常識」だと思いがちですよね。
永田:そうなんですよね。家族について客観的に考えるとか学術的に考えるということが、これまで非常に少なかったということなのかな。
フィールドワークをしても、夫は外で働き妻は家庭を守り、定年まで勤め上げて家を買うというケースばかり出てきちゃうんですよ。今までの積み重ねがあって母数が多いから。
従来の家族の枠にとらわれなくても生活できる
——でも、そうじゃない人も結構増えたと思うんですけど……。
永田:うん。マンガやドラマで描かれる新しいライフスタイルを見て、「私もそう」っていう人も多いですよね。でも、それを数字で示すとか、オフィシャルな形で出すにはまだ情報が足りていない。
『生涯未婚時代』は、新書ならみんなに「現状はどうなの?」って問いかけられるなと思って書いたんですよ。すると、「私の経験に似ています」とか、「自分の姉妹、兄弟の経験に似ている」という声が届いた。これまで言えずにいたけど、従来の家族の枠にとらわれない夫婦やパートナーシップで繋がっている人がいるというのがわかってきたんです。
——ウートピでもいろんな夫婦や家族のカタチを紹介しています。以前、「大黒柱女子」という女性の方が家計を担っているというケースを紹介しました。
永田:それは今後も増えると思いますよ。それは単純に世の中が変わってきているということに加えて、テクノロジーの進化で、肉体的な負担がなくても十分稼げるような仕事が増えていますからね。
結婚しても今のライフスタイルを変える気はない
——「主夫」も増えていますよね。
永田:そうですね。夫が家のことをやるというタイプの結婚も増えつつあると言われています。だから、いつまでも「自分より上のランクの男子をゲットしないとダメだぜ」みたいなぬるい考えに浸るのはそろそろ卒業しなきゃですね(笑)。
——上昇婚を目指すと「いい男」がいないというやつですね。
永田:従来の家族に関する考え方とか恋愛に対する考え方というのは、女性には地位がないという前提だったんです。だから自分よりもいい結婚相手を探そうとしていた。つまり、高学歴、高身長、高収入。何か尊敬できるような条件を持っている人と結婚することで自分もよりよく生まれ変わることができるんだという発想ですよね。
——まあ今は……。ちょっと古いですよね。
永田:そんなのいまさらでしょ。現代は男女問わず新卒で働くのなんて当たり前だし、社会との接点を自分で作れる人は増えていますよね。そこにも男女の区別がなくなってきている。男性の力でよりよく生まれ変わるなんて考えなくてもいい時代なんです。
——確かに、結婚して生まれ変わって、「主婦にクラスチェンジ!」「サポート第一!」「仕事はそこそこモード!」ってイメージできないです。こんなに自由に毎日好きな仕事をしているのに……。
永田:そんなのできないよね。男女問わずそうだと思うんですよ。
仕事も子育ても選択肢があって当然
——男子も?
永田:そう。男子も、大黒柱とかちょっとしんどい。家族を経済的に養うことに加えてイクメンも求められる。
——女性も男性も「仕事」も「家」もって。結婚のハードルが高く感じますね。今のままで十分でいいのに、なぜそんな不自由な生活に合わせていかなきゃいけないのかと思っちゃうかも。
永田:従来はそれを甘えだと言っていたんですよ。子育てをしなくないんだろう、いつまでも遊んでいたいのだろう、と。それは未熟な考えだと言われていました。ただ、海外の例などを見ていくと、本来はいろいろ選べて当然なんですよ。
——選べる?
永田:たとえば子どもが生まれたら何歳ぐらいまでは自分が頑張るけれど、何歳以降は夫が頑張るとか。月水金は自分が時短をするけれど、火木土は夫が時短をするとか。子どもが小さい時は思い切って実家に帰るけど、その後復職できるような環境を整えるとか。
いろいろ選べることによって、選択の幅が広がるはず。なのに今はどうでしょう。保育園に入れられない、長時間労働はなくならない。選択肢を持つどころか子どもを育てるというハードルは依然として高いまま、世の中はどんどん変わっていますよね。
その中で、「昔の家族のカタチ」に合せるのは厳しいですよね。なのに、家族に対する考え方自体は変わっていないから、それができないやつは甘えだというふうに言われちゃう。
実は歴史が浅い「昔の家族のカタチ」
——「昔の家族のカタチ」っていつからなんですか?
永田:スタンダードになったのは、高度経済成長期でしょうね。あの頃は妻は家にいて、夫が働いて。結婚したら女性は今までの仕事を辞めて、家庭に入って生まれ変わってというのが、常識だとみなされていました。今に比べて女性の地位が低かったですし、年功序列や終身雇用に守られていたので、男性も人生設計を立てやすかったというのがありますよね。
でも、それよりちょっと前、つまり戦前とか戦後まもなくの頃は、日本は第一次産業がまだまだ盛んでした。その頃は女の人だって当たり前に働いていて、労働力として扱われていました。だけどそれが高度経済成長期になって、人々が企業で働くようになってから女の人が除外されたというか、働くとしても「腰掛け程度」っていうことになったんですよ。
——意外と歴史は浅いというか、こんなに短い期間に変わっちゃうものなんですね。
永田:そうですね。働き方は、時代や産業の状態で変わっていくものです。だからそれに合わせて家族が変わっていくというのは健全なことなんですよ。
(取材・文:ウートピ編集部 安次富陽子、撮影:面川雄大)
【イベント情報】
永田夏来さんと、エッセイストの紫原明子さんの対談トークイベントが開かれます。
結婚と家族にしばられない生き方って? ~「呪い」の言葉をはね返す「白魔法」~
日時:2017年9月22日(金)19:00〜21:00
参加費無料
詳しくはこちらをご覧ください。