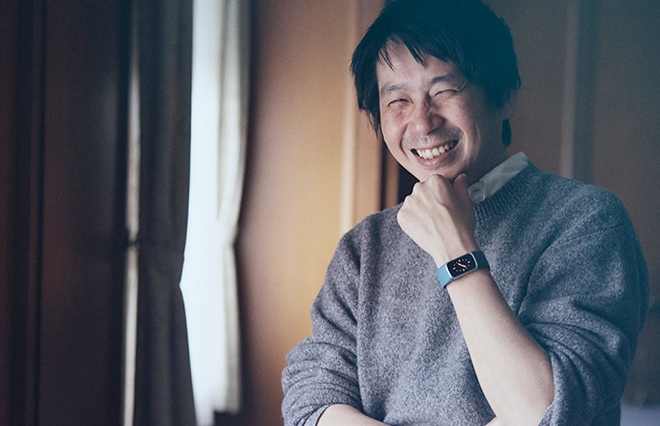歌人・小説家の小佐野彈(おさの・だん)さんによる小説『僕は失くした恋しか歌えない』(新潮社)が11月30日に発売されました。
かつて帝国ホテルを傘下に置くなどホテル事業・バス事業などレジャー事業を幅広く手掛けた「国際興業グループ」の御曹司として生まれ、幼稚舎から慶應のセレブ人生を歩んできたオープンリーゲイの小佐野さんによる自伝的小説で、15歳のときの初恋から台湾に渡るまでに「僕」が出会った恋を、物語の中に短歌を交えてつづっています。
先日発表された「2021ユーキャン新語・流行語大賞」では、生まれてくる親を選べない「親ガチャ」という言葉がトップテンに入ったばかり。
「親ガチャ」は大当たり。同時刊行された歌集『銀河一族』(短歌研究社)でも、“華麗なる一族”に生まれた自身を詠んでいる小佐野さんに話を聞きました。前後編。
恵まれていることへの罪悪感
——ご自身のことを「恵まれている」とおっしゃっていましたが、確かに小佐野さんが生まれた家や経歴を見ると「セレブ」「超勝ち組」に見えます。小説からは、だからこその苦しみやなかなか人に分かってもらえない悩みが伝わってきて切なかったです。
小佐野彈さん(以下、小佐野):例えば、僕の場合は日本で一番恵まれている母子家庭の一つだったと思うんです。でも、一般的に「母子家庭」と言うと、「父親がいなくてかわいそう」というイメージもあると思います。「お金持ち」と言うとそれこそ「セレブ」というイメージがあるかもしれないですが、人には言えない何かを抱えていて苦しんでいるかもしれないしってことですよね。
——つい「セレブ」とか言っちゃうけれど、人には人の「地獄」があるというか、それぞれの「リーシュ(足枷)」があるんだなって。
小佐野:「やっぱり学校の送り迎えもすごかったんでしょ?」とかって聞かれることも多いのですが、そもそもうちの学校は送り迎え禁止だし、普通に電車通学でした(笑)。
そんなふうにイメージで語られることも多いのですが、それも分断の原因になっているんですよね。人ってレッテルを貼りたがるし、例えばLGBTQだってめっちゃ多様です。うちの彼氏みたいにどれにも属していないし、本人の自意識としてはノンケだけど「ダンくんとはこれからもずっと一緒にいるだろうな」みたいなことを平気で言えちゃう人もいる。男性の同性愛者と女性の同性愛者が置かれている状況も全然違うし、ヘテロセクシュアルにおける男女の不平等はゲイとレズビアンの間にも存在します。
思想や信条だって、当然ながら人によってさまざまです。ただ、「LGBTQ」というとなんとなく意識高い系でリベラルっぽいイメージがあるみたいで、以前「あなたは当然、自民党なんか嫌いでしょ?」って言われたことがあるんですけれど、僕はさておき自民党が好きなゲイもいるし(笑)。それは一概には言えないですよね。
どんな立場であれ、どんな経済的に恵まれていようが人間である以上はやっぱり悩んでいて、自分の体のこともそうですし、色だの恋だのも普遍的な悩みとして、苦しみとして存在している。それこそ『伊勢物語』の業平だって、平安時代の日本ではめちゃくちゃめぐまれていた貴族。めちゃくちゃイケメンでめちゃくちゃモテているくせに、彼もやっぱり苦しんでいるし、孤立するわ、不遇な目にも遭うわで結構大変で、彼には彼なりの苦しみがある。でもこうして後世まで読み継がれているのは、普遍的なものが描かれているからこそだと思うんです。
それに匹敵するようなものを書いた、なんて大それたことはもちろん思わないけれど、自分の中で「この作品を書いてる意味って何だろう?」「これを世に問う意味って何だろう?」というのを考えたときに、やっぱり僕はずっと恵まれているって言われ続けてきて、実際に経済的に恵まれてはいるのですが、一方で苦しみだって人並みにあるんですよね。
——お話でも小説でも「恵まれていること」が繰り返し出てきますが、罪悪感のようなものを持っているのでしょうか?
小佐野:「苦しい」とか「生きづらい」と言うことにはばかりはあります。「自分は苦しかったのか?」と言われたら苦しかったときもありましたが、それは明日食べるものがない人との苦しみとはやっぱりまったく違う。
僕は博士課程まで経済学を専攻していたのですが、途上国と先進国との経済格差の問題をテーマとして扱ってきました。国内でも経済格差を見てきたので、経済的な悩みがないというのは人生のかなりの悩みから解放されているわけですよね。僕がセクシュアリティの悩みを抱えているからと言って、「自分が苦しかった」なんて簡単に言っていいのか、という思いは今でもあります。
ただ、僕が最初に短歌を始めようと思ったきっかけが俵万智さんの『チョコレート革命』だったのですが、不倫についての歌集で、あとがきで「短歌は、事実(できごと)を記す日記ではなく、真実(こころ)を届ける手紙で、ありたい」と書いていたのが印象的でした。
僕も今回書いているものは少なくとも「こころの本当」ではあるんです。それを読んで「なんだかんだ恵まれているよね」って思う人もいれば「一見恵まれているように見える人も苦しさや悩みを抱えているもんなんだな」って思う人もいるかもしれない。作品の受け取り方や読み方は自由ですし、さまざまですから。ただ、国籍や立場、セクシュアリティとかあらゆるものを超えて普遍的な苦しみがあるということに気づくきっかけになってくれれば嬉しいです。
「いい時代になった」のかは分からないけど…
——令和になって「多様性のある社会」という言葉を聞く機会が多くなってきました。小説の舞台にもなっている1990年代後半から比べれば、「いい時代になった」のか、あるいはそうではないのか? 小佐野さんはどうお考えですか?
小佐野:例えば、作中でも書いたように母親は「いい時代になってよかったわね」みたいなことをよく言うのですが、本当に“いい時代”なのかはまだ分からないし、自分が死ぬときにならないとわからないんじゃないかなとも思います。
例えば、同性婚やパートナーシップ制度は選択肢あるいは権原として絶対にあるべきだとは思いますが、自分が結婚を選択するかどうかは分からないです。それによって縛られることもいっぱいあるかもしれない。でも、これから良い方向には変わっていくとは思います。確かに昔に比べたらまだ住みやすくなっているとは思うし、誤解も減ってきてはいる。でも、基本的には全部が「自分ごと」にならないと意味がないと考えています。
僕は近代経済学の父といわれるアダム・スミスがすごく好きで、彼の思想から多分に影響を受けています。スミスは『道徳感情論』という本の中で、市民社会は「同感」によって成り立っていると言っています。資本主義市場経済における市民社会の絶対条件は「同感(シンパシー)」。言い換えれば、他者の痛みや苦しみを想像することです。「資本主義」と言うと、弱肉強食と思われがちなのですが、近代資本主義の思想的な父でもあるスミスが言っている資本主義社会の姿は、相手の立場を想像して極端なことをしないように、自分の行動をある程度適宜性の中にちゃんととどめることなんです。それがスミスが唱える近代市民社会のあるべき姿です。
他者のことを想像するという意味で、現代のネット社会は一長一短です。多くの言論や情報に触れられるようになった反面、ネット社会は匿名性が高く、他者の「顔」が見えづらい。他者の立場を想像することが難しくなっている側面があると思います。
情報化社会において映像や劇画ではない活字の文学、とりわけ余白だらけの詩歌句が残っているのは、ひとえに想像力のためだと思います。余白を埋める作業というのは想像することだから。
例えば死刑の是非に関しても、僕は積極的な廃止論者でも存置論者でもないですが、被害者や遺族の気持ちはもちろんのこと、死刑執行の命令書にサインをする法務大臣の気持ちや、その死刑囚と人間関係が深くなってしまった教誨師の気持ち、あるいは実際に死刑のボタンを押す三人の刑務官の気持ち、そういうものを全部情報を得て、しかも自分で想像をしてその同感をした上で結論を導き出すかどうかが肝だと思っています。
性的マイノリティの問題についても、台湾では労働市場の流動性などさまざまな要因で当事者のカミングアウトがしやすい環境ができ、マイノリティの可視化が進みました。そして結果として、社会的受容が進み、さらにカミングアウトがしやすくなる、という好循環があります。日本社会も可視化が進んでいけば、大きく変わっていくんじゃないかなと思っています。
分かり合えないことを分かり合う
——「理解」についてはどうお考えですか? ウートピは編集方針の一つに「『分かり合う』のではなく、『分かり合えないことを分かり合う』価値観を大事にする」を掲げていて、作品に登場する母と息子の葛藤の部分と重なると思いました。
小佐野:理解と受容に関しては、僕も「受け容れることと理解のそのあわい青く烈しく川は流れる」と詠んだ通り、理解と受容は似て非なるものだと思っています。うちの母親はよく僕に「私はあなたのことを理解している」と言うのですが、完全な理解は無理だよって。理解って、「同感」の力、つまりシンパシーを100%働かせたあげくに、相手の痛みや相手の苦しみを完全に追体験できる状態にならないと、理解なんてできないと思うから。そういう意味で「理解」はおこがましいと思うし、逆に僕もノンケのひとや経済的労苦の中にいる人の気持ちを理解できているとは思わないです。
例えば「結婚」だって、僕の場合はオープンリーゲイであることによって結婚というソーシャルプレッシャーからかなり解放されている。30代の男性や女性が「そろそろ結婚が」とか「そろそろ子供を」と周りから言われている気持ちを僕は分かってあげられないし、それを「分かるよ」「理解しているよ」なんておこがましくて言えないし……。
僕は経営者として、サラリーマンではないからこその自由さの中にいるので、上司や会社からの圧力を頭では分かっても実感はない。でも、やっぱり受け入れることから始まるとは思っています。まずはいろんな人がいるんだなって認知することが大事なんじゃないかなって。理解はそんな生やさしいものではないので、まさに「理解できないことを理解する」というのは正しいと思っています。
——目の前にいる相手は自分とは違う他者だから。
小佐野:そう。自分はあなたになれないし、あなたも私になれないから。だからこそ、想像する。僕は、それを「受け容れることと理解のそのあわい青く烈しく川は流れる」という一首に託しています。これが僕の思いですね。
(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)