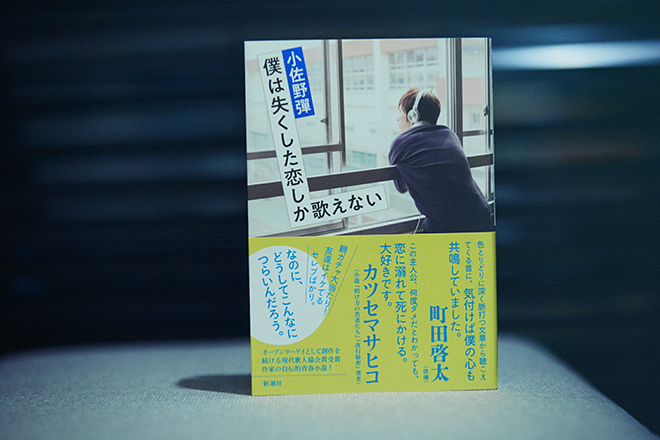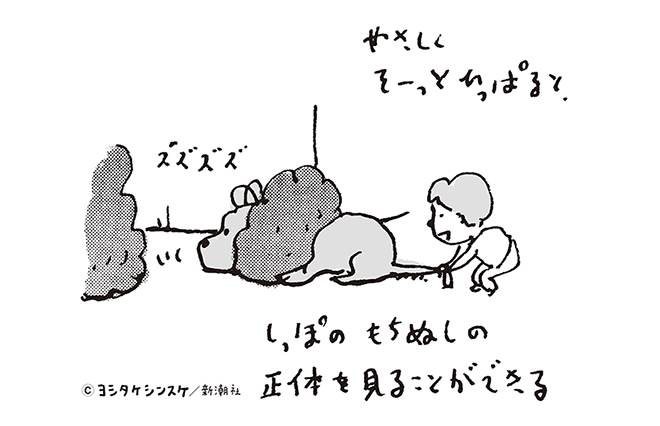歌人・小説家の小佐野彈(おさの・だん)さんによる小説『僕は失くした恋しか歌えない』(新潮社)が11月30日に発売されました。
かつて帝国ホテルを傘下に置くなどホテル事業・バス事業などレジャー事業を幅広く手掛けた「国際興業グループ」の御曹司として生まれ、幼稚舎から慶應のセレブ人生を歩んできたオープンリーゲイの小佐野さんによる自伝的小説で、15歳のときの初恋から台湾に渡るまでに「僕」が出会った恋を、物語の中に短歌を交えてつづっています。
先日発表された「2021ユーキャン新語・流行語大賞」では、生まれてくる親を選べない「親ガチャ」という言葉がトップテンに入ったばかり。
「親ガチャ」は大当たり。同時刊行された歌集『銀河一族』(短歌研究社)でも、“華麗なる一族”に生まれた自身を詠んでいる小佐野さんに話を聞きました。前後編。
「リーシュを外していく作業」日本から離れて書いた作品
——『僕は失くした恋しか歌えない』は文芸誌『yomyom』で連載されていた、自らのセクシュアリティに戸惑うダンの青春小説ですが、ご自身のことをどの程度反映したものなのでしょうか?
小佐野彈さん(以下、小佐野):ざっくり言えば7割ノンフィクション、3割フィクションのような感じかもしれませんが、やはり小説は小説です。ただ、『車軸』をはじめこれまで自分が書いてきた小説にはたいがい“小佐野彈っぽい人”が出てくるのですが、がっつり自分で名前も同じというのは今回が初めてです。
新潮社からは「小佐野さん版の『伊勢物語』を書いてください」とお話をいただきました。『伊勢物語』は平安初期を代表する歌人・在原業平を思わせる男の話で、フィクションとノンフィクション、歌と小説の枠やカテゴリーを超えた超絶自由な文学です。じゃあそれを現代でやるとしたらどんな形になるのかな? と考えた結果こうなりました。
——一冊の本になってみていかがですか?
小佐野:連載時期の半分以上が、コロナ禍に丸かぶりだったんです。僕はずっと台湾にいて、1年半日本に帰って来られなくなり母とも日本とも物理的に距離が離れていました。慶応の同級生や自分が日本で属していたコミュニティとも完全に隔てられていたので、そのおかげで客観的に書けた部分はあります。
『伊勢物語』は基本的には業平がモデルの「昔男」の色恋のすったもんだが描かれていて、業平は東に流されていく旅の中でも悲しい別れや道ならぬ恋、あるいは理不尽など、さまざまな経験をする。僕自身も海外生活が長い上に出張も多く、コロナ前は日帰りで香港に行って翌週はカナダ、その次はオーストラリア、というような旅の多い生活をしていて、平安の大スターに恐れ多いことではありますが、どこか業平と自分を重ねていました。今回の原稿も、コロナ前に執筆した部分はラトビアやザルツブルグなど世界中のいろんな場所で書いて送っていました。
旅をしながら僕の人生の旅のことを書いていて、「旅」がずっと自分の中でのキーワードの一つでした。そういう意味でも、ずっと日本にとどまっていたら書けなかった作品かもしれません。
車は「どこにでも行ける」象徴
——確かに「旅」はこの小説のキーワードの一つですね。中国語の先生を訪ねて台湾に一人で行ったダンが「自由」をかみ締めている部分が印象的でした。
小佐野:やっぱり特殊な家庭で育ったので、常に家がドーンと存在しているんですよね。幼少期から旅行も半ば出張みたいなことが多かったので、今は自由な旅ができて本当に幸せというか……。
——作中でも、家族旅行ではホテルのスタッフや関係者に山のようなお土産と心付けを用意して、常に見られていることを意識して品行方正を求められる様子が描かれていましたね。
小佐野:僕にとっては、旅は長らく自由なものではなかったんです。今は台湾でも日本でも自分で運転して移動するのがすごく好きなんですけれど、基本的に自由にいつでも思い立ったときにどこにでも行けるからだろうなって。電車にも乗るのですが「何時何分のこの電車に乗ってください。この席に座ってください」というのが苦手なんです。年々物欲が少なくなっている実感があるのですが、こと車だけは、僕の物欲を存分に刺激してくる(笑)。好きなメーカーの新車の情報とかは絶えずチェックしています。いつでもどこにでも行ける車というアイテムが、僕にとって「自由の象徴」のようなものだからかもしれないです。「今の俺にはリーシュがないんだ」って実感できるというか。
——「リーシュ(足枷)」という言葉も頻繁に登場するキーワードの一つです。
小佐野:この作品を書きながら、自分を規定していたものから解き放たれていくのを感じました。物理的にも日本の外から自分を振り返る状況で、この作品を書いていくことで自分のことも分かっていきました。短歌も入っていますが、短歌ってどうやっても嘘(うそ)がつけないものなんですよね。それを詠みながら「あの頃の僕はこんなふうに思っていたんだ」とか「こんなことを考えていたんだな」と思いながら自分につながれていたリーシュを一個一個外していく作業だったと思います。
「名前がない関係」を書き続ける
——短歌と言えば、「擁きあうときあなたから匂い立つ雌雄それぞれわたしのものだ」と詠んでいました。誰もが心の中に矛盾やもやもやとしたグラデーションを抱えて生きているという部分が印象的でした。
小佐野:やっぱり基本的に割り切れないものが好きなんです。割り切れないものが好きじゃないと短歌もできないだろうし、グラデーショナルなものというか、きれいに線引きできないものが好きというか……。そういうものが自分の中にいっぱいあります。
経済的な意味で僕はすっげー恵まれてますし、“超勝ち組”と思われがちで「めっちゃ恵まれているね」っていろんな人から言われてきました。確かにその通りなのですが、でも恵まれている人間にも恵まれている中で、僕の場合はセクシュアリティの部分で苦しさがあったのは事実です。それは僕の心の真実なので。恵まれてはいるんだけれど、そうは言っても割り切れない部分を書いてきたし、これからもおそらくそういうものを書いてくんだろうなという気はします。
——ふと世の中を見渡すと、白黒に分けたがると言うか「正しい」「正しくない」でジャッジし過ぎなのかなって。
小佐野:すごく分けたがりますよね。「あいつはあいつのことをフォローしているから右翼だ」とか「あいつはあの新聞に寄稿しているから左翼だ」とか。でも一人の人間、僕だってビジネスマンとしての立場、作家としての立場、うちの母の息子としての立場、あるいは一人のゲイとしての立場、彼氏のパートナーとしての立場、全然やっぱりその時々で違うし、明日になったら自分でも知らなかった一面に気づくかもしれないし、何一つとして「この人はこういう人間です」って言い切れないですよね。常にたゆたっていると思うんです。人って基本はたゆたっているのかなって。
小佐野:僕自身はやっぱり割り切れないし、人の属性自体もそんなにきれいに分けられない。例えば自分も100%完全なゲイだとは言い切れない。確かに僕の性的指向はゲイだけど、この小説の中でも書いた通り、僕は少なくともアイコちゃん(作中に登場するダンの“ともだち”)に対して抱いていた感情は完全に友情かどうかと問われたら分からないです。男同士の関係もホモソーシャルな部分とホモセクシュアルな部分ってめっちゃ曖昧だと思うんですよ。
それこそ『源氏物語』とか『伊勢物語』の時代からつい最近までセクシュアリティってそんなにきれいに分かれていなかった。特に何も規定はなかったわけですよね。でも、皮肉なもので、言葉が増えてくれば増えてくるほど、人は言葉によってくくられていく。もちろんそれによって救われることもあるかもしれないけれど、一方でどんどん苦しくなっていくこともある。自分はどこかに属さなきゃいけない、名前を持たなければいけないと思わされるようになってくる。
僕も、パートナーに対して対外的に便利だからという理由で「彼氏」という言い方をしていますが、「彼氏」という名称が正しいかどうかは実のところ分からないです。僕が『車軸』で書いた3人の人間関係も友達でも恋人でもセフレでもない、名前を付けようがないものです。何となくたゆたってるうちに、導かれてそうなっちゃった感じ。
おそらくこれまで僕が小説の中で書いてきた人間関係というのは、どれも名前を付けられない感じなんです。友達でもないし、何だろうこれ? みたいな。狙ってるわけじゃないんですけど、自然とそういうのが出来上がっちゃうんです。
※後編は12月26日(日)公開です。
(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)