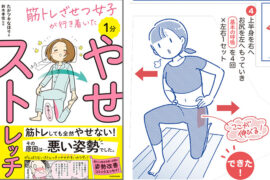仕事がのってくると同時に、結婚や出産がリアルになってくるアラサー世代。自分のこれからを考えたいけど、キャリアと子育ての情報が分かれていて、リアルな生活がイメージできないという人も多いのではないでしょうか。
「結婚して、子どもも欲しいけれど、仕事でも活躍したい」という若い世代に向けて、子育て家庭に訪問して日常を体験するサービス「家族留学」を提供しているmanma(マンマ)の取締役副社長、青木優(あおき・ゆう)さんに、新卒での就職活動を打ち切ってまでジョインすることを選んだ「家族留学」という事業に対する思いについて話を聞きました。
【前編は】「やりたいことに気づいたから、思い切って就活やめました」
ずっと子どもが苦手だった
——事業を始める前後で結婚や出産に対する考え方は変わりましたか?
青木優さん(以下、青木):はい。いまは早く結婚して早く出産したいと思っています。でも、もともとは子どもが苦手でした。
——苦手? 意外です。
青木:どう接したらいいかわからなかった、という方が合っているかもしれません。私は転勤族の家庭の一人っ子だったし、近所の子どもとの交流もなかったので。
それから、「子育ては大変」という風潮をわりと鵜呑みにしていたので「私は絶対に子育てしたくないな」って思っていました。いい教育を受けさせてもらったのに、結婚や出産で人生を台無しにされるなんて耐えられない、と。
——人生台無しかぁ。そう見えていたんですね。
青木:生意気ですよね(苦笑)。今は全然そんなこと思わないんですけど。当時は、母がパートで働く姿を見て、子育てはキャリアのマイナスになるものというイメージが強かったんです。母は、転勤族ということもあって結婚、出産とともに正社員の仕事を辞めました。そこからは私をしっかり育てることを優先したため、在宅ワーク、パート、契約社員などで、隙間を埋めるような働き方をして。当時の私には、自分のキャリアを生かしているように見えなかったんです。
それに、キャリアの講演をしに来るOBOGの方々は、結局子どもがいなかったりする。やっぱり二者択一なんだなと思っていました。
平等ではなく尊重しあえる仲に
——その思いが変わったきっかけは?
青木:留学先で自分の価値観革命が起きたんです。私自身、子育てに対してネガティブだったのが、「家族」をテーマにフィンランドと台湾に留学したことで価値観が変わりました。「働きながら子育てをして、こんなに心が豊かな生活ってあるんだ」って。
仕事はそこそこに、家庭とバランスを取るのではなく、仕事でも活躍している方に出会えた。その瞬間にポジティブな衝撃を受けたんです。
——留学先はどうやって決めたんですか?
青木:男女平等国家、社会福祉国家、お母さんに優しい国と言われるフィンランドと、子育てをしている世代の労働力率が一番高い台湾。その海外事例を日本に持ち込めたらいいな、と思いました。
——実際に行ってみて、どんなことに気づきましたか?
青木:フィンランドでの一番の学びは、平等国家と聞いて行ったけれど、実感としては“尊重国家”だったことですね。
——尊重、ですか?
青木:平等って言葉のイメージだと、50:50ですよね。でも、フィンランドだって女性が多い職場もあれば、男性が多い職場もある。男性の育休取得率が80%以上という数字はありますが、別に義務化されたりとか、完全に均等にされたりしているわけじゃない。
彼/彼女たちには、性別を問わず全ての人にチャンスが与えられていて、あとは個人の選択である、と。さらに、「あなたの選択はOK、私の選択もOK」と他者を尊重しつつ自分も肯定する。現地で女子大生にインタビューをしていて、そんな違いがあるのかなと感じました。
結婚・出産がリアルになってきた人たちへ
——自身の生い立ちや、関心を持ってやってきたことがパズルのピースみたいに組み合わさって、「家族留学」の立ち上げや事業化に繋がっていくわけですね。「家族留学」ってmanmaオリジナルのサービスですか?
青木:はい。manmaが独自で始めたサービスです。学生が子育て中の家族の家で1日過ごし、生き方のロールモデルに出会うという体験プログラムで、シッターさんとして子どもを預かるのではなく、親御さんがいる状態で一緒に過ごすのが特徴です。
——学生向けのサービスなんですね。
青木:今は社会人の「留学生」も増えています。元々は代表の新居(におり)が大学1年生の時に任意団体としてスタートさせていて、当初は「大学生が大学生のために」、つまり「自分たちの未来を自分たちで作る」という部分で共感してもらっていました。
でも、私たちも学生じゃなくなって。活動が徐々に広まっていくうちに、社会人からの申し込みも増えるようになりました。
——結婚とか出産がもっとリアルになって来た人たちのニーズが顕在化したんですね。参加した人の感想はどうですか?
青木:価値を感じていただいているようです。参加者であるミレニアル世代、80年代後半くらいの人で、学歴もそこそこ高めの人って、母親が専業主婦という人がまだ多い。
でも、今は?となると、自分の親は働いていなかったけれど、世の中では女性の社会進出だ、働き方改革だと言われていて。働くことが当たり前の時代。自分の親世代がロールモデルにならないから、「どうしたらいいの?」という人が多いんですよね。「家族留学」はそこに、今までなかった情報を提供できる。
家庭版OBOG訪問の役割
——働き方はいろいろ情報があるけれど、家庭運営に関しては「親になればできるよね」的な部分がありますよね。
青木:そうなんです。仕事なら、OBOG訪問、インターンシップなど、その企業で働いたらどんな雰囲気で、どんなことをするのかってリアルに知れる機会がありますよね。でも、働きながら家族とどう接するかということをリアルで知れる機会ってあんまりないと思うんです。
——うんうん。友人の家に遊びに行っても数時間とかですもんね。
青木:受け入れ家族側のフィードバックからも気づかされることがありました。自分の体験をシェアすることで、誰かの役に立つということに喜びを感じてくれる人がすごく多かったんです。
manmaに協力してくれている受け入れ家庭1号世代の人たちって、育休世代1号の人も結構いるんです。会社によっては、育休の仕組みがやっとできたという時に子どもを産んだという人も多い。だから、その人たちが生む前や後に知りたかった情報を家に来た若い世代の人に伝えられたり、子どもにとっても普段関わることのないお兄さん/お姉さんに遊んでもらったりするといい刺激になる、と。
——参加者と受け入れ側で相乗効果が。
青木:そうなんです。自分の家族以外との関わりが無くなってきている社会の中で、「家族留学」というものを介在すると違う家族と出会える。それが、家族側にとっても参加者側にとっても互いに良い影響が生まれているんです。この体験の延長線上に、多様な生き方が尊重される社会が実現できたらいいなと思います。
(取材・文:ウートピ編集部 安次富陽子、写真:青木勇太、撮影協力:RYOZAN PARK Otsuka)