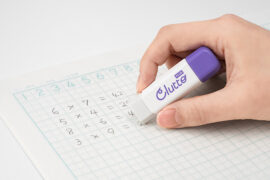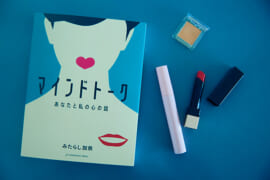「フリー編集長」と「社畜プロデューサー」というまったく異なる立場から、ウートピ編集部というチームを運営している鈴木円香(33歳)と海野優子(32歳)。
脱サラした自営業者とマジメ一筋の会社員が、「心から納得できる働きかた」を見つけるため時にはケンカも辞さず、真剣に繰り広げる日本一ちっちゃな働きかた改革が現在進行中です。
「社会人10年目32歳、IT企業勤務のメディアプロデューサー」海野Pの市場価値を、リクルート エグゼクティブ エージェントでエグゼクティブ・コンサルタントを務める森本千賀子(もりもと・ちかこ)さんに聞いた前回。今回は、そこから見えてきた「キャリアの選択肢」がテーマです。
自分の市場価値を知ると、予想外の選択肢が見えてくることもあるんです。
「そろそろキャリアチェンジするか……」とお悩みのみなさんはご参考に!
「中途半端」と「マルチタスク」は表裏
鈴木:社会人10年目32歳、メディアプロデューサーの海野Pの市場価値を考えてみた前半で、海野Pが「マネジメント力」と「プロデュース力」という最強カード2枚を持っていることが判明しました。後半は、本人も意外なほど市場価値が高かった海野Pの、今後のキャリアの選択肢について考えていきたいと思います。
森本千賀子さん(以下、森本):これだけカードがあれば、相当選択の幅は出てくると思いますよ。
海野P:でも、やっぱり、私って中途半端だと思うんです。マネジャーもプロデューサーも一応やってますけど、できてるとは言えないし。ディレクターとしても、営業としても中途半端。どれも「これが専門です」「これなら完璧にできます」って言い切れない……。
森本:でも、中途半端ということは、マルチタスクとも言えるってことなんです。
海野P:(やっぱり中途半端なんだ……涙)
森本:要は、どんな時もネガティブになるな、と。常にポジティブに言い換えていきましょう! 言いかたなんて、実際にはどうにでもなります(笑)。仮に今、海野さんが転職するとして、1時間弱の採用面接で担当者は何が見抜けるの? これまでやってきたことを、どういうふうに「強み」として認めて、人に伝えるか。それをお手伝いするのが、まさに私の仕事なんです。だから「中途半端」とは言わせませんよ。
海野P:(ぐすん……)
鈴木:今の「ウートピ」では、編集は編集の仕事、営業は営業の仕事で、それ以外の仕事は全部、海野Pの仕事みたいになっちゃってるところがあるんです。ある意味、雑用係みたいな。
海野P:そうそう……自分は所詮雑用係……って思っちゃうことあります。
森本:それ、ホントに思っちゃってるだけだから(笑)。自分がこれまで一生懸命やってきたことを、「中途半端」とか「雑用係」とか、ネガティブに捉えちゃったらもったいない。そこに価値を見出すのは自分以外にいません。一見雑用に思える仕事でも、それを海野さんにしかできない業務にしていけばいいんです。
海野P:「海野さんにしかできない業務にしていく」とは?
森本:そこに海野さんがいてくれないと困るという状態にしていくんです。
社会人のチャンスは不平等に与えられる
森本:大前提を話しておくと、社会人は不平等なんです。学生は平等にチャンスを与えられるけれども、社会人はデキる人にばかり仕事が集まる。これが基本。そうなると、普段から「自分にしかやれない仕事」「まわりを唸らせるような仕事」をしておくことが大事になってきます。
海野P:まわりを唸らせるような仕事……。
森本:どんな小さな、雑用みたいに見える仕事でも「唸らせること」はできるんです。例えば、議事録のとりかた一つでも、自分にしか出せない付加価値はある。数週間後に見直しても議論の流れがわかるようになっているとか、超多忙な人でもすぐに読めるようにA4用紙1枚にまとめるとか。
その人が「自分にしかできない仕事をする」という意思をもってやったか、「雑用だから」という意識でやったかは、見る人が見れば一瞬でわかっちゃうんです。そして、そういう感度のある人がきっと次のチャンスを与えてくれる。だから、「雑用係だから」って思っちゃうって、すごくもったいないんです。
海野:確かに、その意識はなかったです。
森本:仕事内容は同じでも、いかに自分にしか出せない付加価値をつけていくかという発想になった時に、アウトプットがガラリと変わってきますよ。
転職が失敗するタイミング
海野P:「どうせ私なんか……」って思っちゃう原因として、自分よりデキる人ばかりに目がいってしまうことがあると思うんです。能力的もポジション的にも上ばかり見てしまって、自分とのギャップに気づいては落ち込むばかりで自分を見られていないというか。
森本:それはすごく健全なことだと思いますよ。「脳の空白の原則」って知ってますか? 器に水が半分しか入っていない状態を見て、「半分も入っているから十分」と感じる人もいれば、「半分しかない」と危機感を覚える人もいる。海野さんも後者のタイプでしょう。そういう人は、器に水をいっぱいにしようと努力してどんどん足していこうとするんです。あふれたら、もう少し大きい器に変えて、また次の器へと……。
海野P:意識高い系の人間なので(苦笑)。
森本:でもね、人はそうやって器を大きくしていくんです。だから、自分にはこれもあれも足らないという危機感や焦燥感はすごく大事だし、健全なことなんですよ。成長へのプロセスなんです。
鈴木:つまり、「自分なんか雑用係で市場価値なんかないし……」と危機感を覚えている今の海野Pは、まさに成長の途上にある、と。
森本:そうです。危機感や焦燥感があるうちは、自分は成長しているんだ、と思っていただいて大丈夫です。むしろ、そういうのを感じなくなったら、成長していない証拠だから、「やばい!」と思って場所を変えた方がいいですね。
海野P:そこで初めて転職とか、キャリアチェンジを考えた方がいいんですね。
森本:そうそう。「最近、なんか仕事がラクだなあ」と感じ始めたら伸びしろがなくなり始めているサインです。
海野P:でも、実際には逆で「私、この仕事全然向いてないわ」「能力ないからできないわ」って落ち込んでる時ほど、キャリアチェンジを考えちゃうような気がする。転職した方がいいのかな、って。
森本:だから、うまくいかないんです。ネガティブなマインドのまま転職しちゃダメなんです。「ここから逃げたい/離れたい」という気持ちで転職しても、新しい職場でまた同じことになっちゃいますから。
エグゼクティブ・アシスタントに転身!?
海野P:最後にどうしても森本さんに聞いておきたいことがあるんですけど……。
森本:聞きましょう、聞きましょう。
海野P:ぶっちゃけ今より年収、上げられますか?
森本:あげられます!
海野P:(おっ!!!)ど、ど、ど、どのくらい!?
森本:この先の選択肢はいろいろありますけど、例えば、伸びしろが大きそうなものだと、「エグゼクティブ・アシスタント」とか向いてると思いますね。
海野P:私がエグゼクティブ・アシスタント!?
森本:はい。最近ニーズが急激に増えている仕事です。オーナーカンパニーで数年以内に上場予定くらいのフェーズにあるベンチャー企業で、オーナー社長をサポートする仕事です。「社長秘書」とも言えるんですが、秘書の領域に収まらず戦略面にまで関わるので本当にマルチタスクが求められます。海野さんは、こうしてお話していると、テキパキして仕事が速そうだし、何より性格が明るいし、向いてると思いますよ!
鈴木:(確かに仕事はめっちゃ速いぞ、海野P。すごい、わずか1時間足らずの取材でここまで見抜いてしまう森本さん!)
森本:社長の「こぼれ球拾い」のような仕事ですが、経営者のそばで仕事をするので、認められたら大きなチャンスがあります。将来的には、認められてパートナー(共同経営者)のようなポジションまで引き上げられる可能性もありますし。さらに経験を積めば、次は「社長室長」のポジションも目指せますよ。
海野P:ハッ!
鈴木:一気に可能性が広がりましたねー!
森本:「社長室長」といえば、会社にとって超コンフィデンシャルな情報を握っている人。絶対に手放せない人材です。
鈴木:現在32歳でウェブメディアのプロデューサーを日々泣きながらやっている海野Pに、こんなに明るい未来が待っているとは!
海野P:いやあ、マジか……エグゼクティブ・アシスタントから社長室長……1ミリも考えたことありませんでした。
森本:海野さん、ホントに必要だったら、いつでも紹介しますよ!
鈴木:(えっ!……それは困る!)
(構成:ウートピ編集長・鈴木円香)