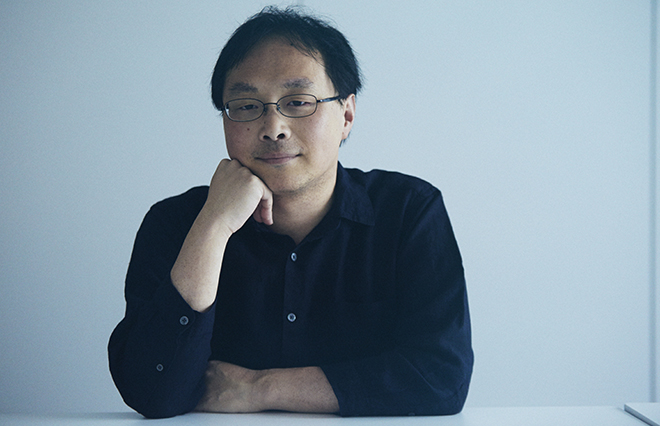2009年に、ホラー小説『!』(アルファポリス)で作家デビュー後、フィクション、ノンフィクション問わず、さまざまな作品を発表してきた二宮敦人(にのみや・あつと)さん。結婚時に東京藝術大学彫刻科の学生だった妻への興味から、“芸術家の卵”たちの知られざる日常をつづったエッセイ集『最後の秘境 東京藝大ー天才たちのカオスな日常』(新潮社)は、累計部数40万部を超えるベストセラーになりました。
そんな二宮さんのエッセイ集『ぼくらは人間修行中ーはんぶん人間、はんぶんおさる。』(新潮社)が、7月に発売されました。「小さな生命体」であるところの長男(ちんたん)と次男(たっちゃん)を「親の欲目に惑わされず観察」して記録したエッセイ。日々巻き起こる何げない出来事を通して、親と子供が一緒に育っていく様子が描かれています。
二宮さんに執筆のきっかけや「父性」をテーマにお話を伺いました。前後編。

二宮敦人さん(以下、二宮):自分が親になってみて、「こんなことまで考えてくれてたんだな」「こういうときすごく心配だっただろうな」とか、親の心遣いが分かるようになりました。すると、今まで親から押し付けられたと感じて反発していたことが、ちょっと見方が変わって受け入れられるようになったりとか。簡単に言うと、親が前より好きになりました。
もう一つ面白い発見は、「自分が思っていたより親は偉大だったな」「こうして僕にも夜中までミルクをあげてくれてたんだな」と尊敬する一方で、「親も適当なんだな」というのが分かったことでした。僕の感覚ですけど、常に“理想の親”ではいられないんですよね。“理想の親”でいてもしょうがないというか。
——「親は適当」というのが分かったというのは?
二宮:例えば、「ダンゴムシはどうやって増えるの?」と子供に聞かれたときに、ちゃんと答えてあげようと思っていろいろ調べるんですけど、調べてきた答えを言うと「ふーん、つまんない」とか言われてそっぽを向かれることもあるんです。「お前、せっかく調べたのに!」みたいな(笑)。50回に1回ぐらいしか、「へー、そうなの?」ってならない。49回は徒労に終わるので、こっちもやってられないという気持ちがあって。だから、ちょっと聞かれたぐらいだと、「はいはい。なんかダンゴムシの星から来るんじゃない?」って、適当にごまかし始めちゃう。何回も聞いてきたら、「本気かも……よし、ちゃんと調べないと!」ってなるけど、大体は流しちゃうというか、そういう手抜きが結構あるんです。
——親にも親の事情というか言い分があったんですね……。
二宮:こっちも人間なので、できないことはあるんですよね。そこで自分も思い返すわけです。「親が適当なときも結構あったな」「言っていることとやっていることが違うことも結構あったな」って。「あぁ、こういうことね」「親も同じ人間なのね」と分かるんです。「自分より上の世代の人も、自分と同じ程度の人間なんだ」みたいに、良い意味で同類感だったり、親近感がわいたりする感じがありますよね。
それに、親って結構、子供にケガさせてしまうこともあるんですよね。不注意から机に頭がぶつかっちゃったとか。でも、痛みがひいてくると、子供はコロッと「お父さん、遊ぼう」って笑いかけてくる。これが大人同士だったら、多分こうはいかなくて、しこりが残るはずなんです。嫌なヤツだったら、それで絶縁なんてこともあるじゃないですか。でも、子供は親に傷つけられたという記憶が、少なくとも乳児くらいの頃は残らないようで、実際、僕にもそんな記憶はないんです。だから、欠けてしまった記憶、物心がつく前の過程を、親になってからもう一回見ることで、親を尊敬する部分もあり、同じ人間だって思う部分もあり……。この発見があると、自分の親とも同じ土台に立ってお酒が飲める、みたいな。そういうのは楽しいですね(笑)。
——親の新しい一面が見えるんですね。
二宮:家族によると思うんですけどね。うちの親は、僕が気づくよりも前から、自然体で接してくれていたのですが、僕がやっとそこに追いついたという感覚です。完全に追いついたわけではないんですけど……。

「父親」というより「職人」の感覚
——個人的に「父性って、何?」の章が印象的でした。 「僕は、自分に父性があると言い切れない」と書いてらっしゃいましたが、ご自身は「父親」になった実感はありますか?
二宮:その質問は、結構難しいですね。僕は、性格的に、何かに属しているという意識が薄いんですよね。だから、普段は自分のことを男だとも女だとも思ってないし、日本人だとも思ってないかな。「男だから」「日本人だから」とか、そういうのがあまりないタイプなんです。でも、「男なのか?」と聞かれたときに、「そうですよ」と言うのには別に抵抗がない、要するに許容範囲ではあるので、知識として自分はこういう属性なんだなあとは認識しています。
だから、一応社会の中では、男で、日本人で、何年生まれで、父親で、という知識を持っている、ただそれだけな感じで。前回話したように、子供と大人って意外と変わらないなと思っているので、子供たちを見て、「俺は父親だぞ」って思うことはないです。
——ウートピもあまり属性や役割で分けたり、ジャッジしたりするのはやめようと思っているので、おっしゃろうとしていることはとてもしっくりきます。
二宮:でも、彼らからすると、すごく父親に見えるんだろうなっていう気はするんですよ。視点で言っても、子供たちから見た僕は巨人に見えるだろうし。
——確かに、子供から見た大人はすごく大きいですよね。
二宮:そうなんです。だから、無敵の存在だと思っているみたいで。ガッと抱きついてきて、グワーッて力を入れてくるんですよ。それくらいやっても、大人は平気だと思っているんでしょうね。「この存在は、すごいデカくて強いし、言っていることには従わないといけないし、自分では発見できないようなおいしいお菓子をどこからか手に入れてきてくれるし」って(笑)。そういうすごい存在だと思われているのは感じますね。
僕は、「お前とたいして変わらないよ」と思っているけれど、彼らから見たらすごく違って見えるんだろうなって。だから今は、「そういうことが、父親って感じなのかな?」みたいな気持ちですね。そもそも世の中の人は父親という感じをどう思っているんでしょうね? 父親っていう感じを細分化するとどういうことになるんですかね? お子さんがいる方にそれを聞いてみたいです。
——個人的な話で恐縮ですが、うちの父親が「子供が生まれた瞬間に父親の自覚が生まれたわけではなくて、布おむつが部屋中に干してある中で生活していくうちに父親の実感が生まれた」と話していたのですが、それに通じるものがあるなと思いました。
二宮:そういう方向でも語れますよね。180mlのお湯を哺乳瓶にほぼピッタリサーッと入れられるとか、オムツを替えるのがめちゃくちゃはやくなってくるとか、父親というより職人の感覚に近いのかもしれないです。「いやー、自分もやっと熟練の父親になってきたな」って(笑)。あれは、完全に職人の感覚ですよね。「そろそろ厨房に入っていいよ」って言われるような感じで、父親が板についてきたなという感覚はありますね。

「父親」「母親」である以前に自分だから…
——改めて読者にメッセージをお願いします。
二宮:実は、妻も「あまり母性を感じてない」と言っていて……。子供がかわいいという気持ちはあるけど、「母親として」という意識はあまりないみたいなんです。そういう意味で、僕らは似ているのですが、世の中には、母性というものを信仰したり、「母は強し」という言葉もあるじゃないですか。だから、「実際はみんなどうなんだろう?」というのが、すごく謎で……。
それは別に、親をやっている人だけじゃなく、子供をつくらないって決めている人、あるいは子供をこれからつくろうとしてる人、子育てを終えた人、それぞれみんなの考えがあると思うんですけど、「どう思っていますか?」というのを知りたいんですよね。
僕は、子供が欲しいとか、子供は欲しくないとかいう気持ちも、よく分からないです。そこまで断定して言い切れるのかなって。自分は結果的にこういう人生になりましたし、なんとなく社会的に「子供はつくったほうがいい」というノリは感じますけど、実際のところ、「どっちのほうが人生価値が高いのか?」という万人が納得する結論は出ないじゃないですか。だから、そのあたりのことをみんなで話したいし、「僕はこうでした」というのをお伝えしたい。もしよかったら、この本を読んでいただいて、逆に「うちはこうだったよ」というのを教えてほしいなって思います。どっちが良いか比べたいというよりは、純粋な興味ですね。
——「父親だから」「母親だから」という役割を負わせすぎるのはつらいですよね。もちろんそれで頑張れる人もいるだろうけれど……。
二宮:「父親だからこういうことをしなさい」「母親だからこういうことをしなさい」って言われたら、嫌ですよね。僕も父親だけど、それ以前に“自分”ですもんね。それで嫌な思いをしている人がいたら、「全然気にしなくていいですよ」って言いたいです。むしろ、心から割り切っていいと思います。まあ、「男なんだから働かなきゃ!」とあえて自分を奮起させるときもあるから一概には言えないですが……。自分に都合よく使えばいいのかなって思います。

(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)