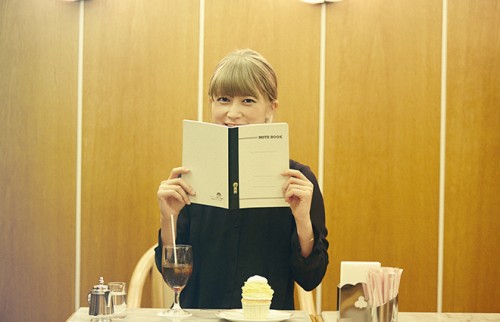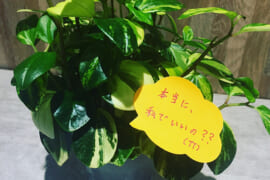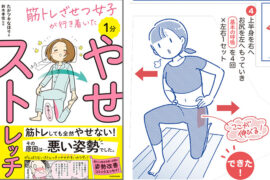20代で社会に出てから仕事でもプライベートでもいろんな人と出会ってきたけれど、たまに見かける「上から目線」な人。
精神科医の名越康文(なこし・やすふみ)先生によると、威圧的な印象を与えてしまいがちなこのタイプの人には、共通して陥りがちな思考があるのだそう。
メディアに潜む「又聞きの法則」
前回、自分の意見には「2割の疑いの余地を残したほうがいい」という話をしました。
こういうことを考えてしまうのは、僕の職業柄もあると思うんです。メディアの世界にいると、ハッキリと物を言うことがカッコよく見えるんですね。
特にテレビ画面って平面で、いくら立体に見えても二次元の世界でしょう。だから、やっぱり本質は「紙芝居」だと思うんです。紙芝居を観たことのある世代の人は分かると思うんですけど、紙芝居ってすごい没入感があるんですね。つまり、現実空間にはない没入感が生じるのが二次元の世界、つまり紙芝居の世界だと僕は思っています。
そしてそこでは基本、善玉と悪玉がしっかり分かれていて、悪玉はどこまでも真っ黒なんですよ。善玉のほうは葛藤したり、いったん逃げたり、いろいろ人間的な動きをするんですけど、悪玉は葛藤がないんです。それで結局は、勧善懲悪の気持ちよさに持っていくんですね。
でもそれは、ある一面、本来複雑で一筋縄ではいかない現実を、ものすごく単純化し、要約化し、記号化しちゃう危険な作業でもあるわけです。
僕たちがテレビから得る情報は、そういう特徴を引き継いでいる。たとえば巨大な権力というものに、我々一般庶民は三次元的に相対することはほとんどありません。つまり、権力の存在をひしひしと感じながら日常生活を送っているわけではない。そうすると、「権力に対してはすべて又聞きである」という法則が成り立つわけ。
だから、あらゆる権力をめぐるメディア・リテラシー(メディアが伝える情報を見極める能力)という意味でも「2割残しておく」という思考法が有用になってくるんです。メディアの中に現れる「悪玉」は、相当単純化されていると思ったほうがいいし、一見カッコいい「善玉」も、それが清廉潔白に見えれば見えるほど、裏の複雑さをずいぶん捨象していると考えたほうがいい。
権力に対する距離の取り方
メディア・リテラシーってことで言うと、できるだけニュートラルに自分の立場や意見を定める際に、具体的な策として有用なのは「複数の情報を持つ」ということでしょうね。
社会的な時事問題に関してだと、僕は少なくとも3つの立場を押さえるようにしているんです。前回話した「名越A」「名越B」「名越C」じゃないですけど、外に対しても三種類くらいの意見は検討したいっていう感覚ですかね。
例えば権力に対して言うと「権力寄り」「権力嫌い」。そして「合理主義」。この3つを踏まえると、自分の立ち位置がだいたい決まってくる。
それが僕の、権力に対する距離の取り方です。あえて言うなら「合理主義」にけっこう近いと思うんですけど、直線的に最短距離で利益や結果を出そうとする発想は、やっぱり「原因・結果論」の単純さに近づいてくる。だから、その考え方とも然るべき距離を取ろうと思っていますね。
「いい人」こそ権力を振りかざしてしまう理由
ちなみに、この3つの立場の中で、僕が基本的に最も警戒しているのは「権力嫌い」なんです。というのは、「権力嫌い」の人が権力を持つと、往々にして大変な権力者になってしまう可能性があるから。
つまり自分は「反・権力」の側だと信じきっちゃってる場合ね。その人は「権力嫌い」の自分は絶対的な正義なのだからと、むしろ傍若無人に権力を使いかねない。これが一番怖いかもしれない。心の奥底から権力というものに恐怖している「権力嫌い」の人なら別ですけど。
ついでにもうひとつ、いいですか。「権力を倒した人間は、倒された側の魂が乗り移る」みたいなところもあると思う。これは「悪」の問題と言い換えてもいい。「悪」とはなんですか?って訊かれたら、「悪を倒した者です」って僕は答えますね。
みんな唖然とすると思うんですけど(笑)、この法則、僕の中では結構な確信なんです。いま、すっごい悪人だと世の中から認識されている権力者の多くは、実は昔、悪を倒した正義の人だったっていう。
こういう逸話は世界中に残っていますよね。キリスト教神学ではサタンも、実は堕天使。かつては神に仕える御使いでありながら、地獄の長になった。革命の歴史もそうですよね。あの悪名高きアドルフ・ヒトラーだって、もともと景気の悪化に苦しむ大衆に「革命」側として支持されて、民主主義の中でのし上がってきた。
だから僕の感覚では、悪を倒した者は5年以内に引退せなあかん(笑)。かえって「いい人」であればあるほど、いろんな恩義とかに縛られて、悪に染まった権力にとどまりやすい。歴史というのはそうやって、非常に因縁めいて回っているところがあると思います。だから注意しなければいけない。これは一国の中でも、職場のような小さなコミュニティーの中でも基本的に同じ法則なんですけどね。
その点、弘法大師として知られる空海は、自分の権力の絶頂期の時に高野山にのぼって、二度と世俗に降りなかった。歴史的に見てもあの人くらいじゃないかな、権力の絶頂期に権力のすべてから距離を置いたのは。
理解した「つもり」は「上から目線」
ちょっと脱線しちゃいました。「有り合わせの物」の話に戻りますと、これって「上から目線」っていう問題にもつながってくると思うんです。
意識的にしろ無意識にしろ(ほとんどの場合は無意識に、ですが)、要は、相手を自分自身より下に見ているから「有り合わせの物」で認識を済ませちゃうんですね。自分が今までに知っている非常に限定的な知識や情報、事例に、安直に重ね合わせて、自分の小さな世界認識のサイズに当てはめて、相手のことを理解した「つもり」になってしまう。
だけど、先に申し上げた「権力に対してはすべて又聞きである」ということにも重なるように、僕たちはほとんど誰かの受け売りのような噂話レベルで、いろんな人や物を単純に判断して、勝手に決めつけている。
すごく単純な話で言うと、例えばプロ野球を見ていて期待の選手がエラーした場合。一度もマウンドで勝負したことのない観客が「お前、エースやのにちゃんとせえよ!」と野次を飛ばす、いかにもおっちゃん・おばちゃん的な「上から目線」(笑)。それと同質のものを、僕たちも普通に行使しちゃってるんです。しかも、それが肝心な思索の時にも出ちゃってることがよくあるわけですね。
こう考えると「又聞き」も「上から目線」も「有り合わせの物に帰する」ことも、同じ問題レベルのことに思えてきましたね。やっぱりこれって仕事のうえでも、日常生活の人間関係においても、ひとつの戒めとして押さえておいたほうがいい。
例えば第三者から「あの人はいい人です」「あいつはイヤな奴なんだよね」って聞くだけで、相手の人物像を自分の中のステレオタイプなイメージに瞬時に落とし込んじゃうようなことありますよね。でも、そうなると実際に生身の相手とコミュニケーションする際に、ある偏見を持って接することになってしまう。特にネガティブなイメージが前提にあった場合、相手も自分もまったく気持ちのいいもんではないですよね。
これが最も身近な「有り合わせの物に帰する」ことの罠です。
それ以上「思考」すると、自分がいままで固定したパターンとして理解していた対象が崩れるからね。この「固定パターンの崩れ」っておそらく脳にとってはものすごく面倒臭いことなんです。だけど、思考することをあきらめてはいけない。
翻って言うと「2割残していく」、明確な判断をある程度保留していくということは、イコール「思考し続ける」ということなんですね。
哲学用語では「エポケー」(判断を保留する態度)と言いますけども、僕たちは本来複雑で繊細な対象を、単純に固定するような考え方にすごく毒されているよ、と。それをできるだけ回避するためには、まずは複数の立場の意見を知ったほうがいいよ。当たり前ですけど、シンプルなところで導き出せるのは、こういう戒めですかね。
ありていなアドバイスにまとめると、「反対意見も聞いといたほうがええよ」(笑)。でもほとんどの場合、反対意見って聞いているふりをしているだけなんですよね。だから本当に反対意見を真摯に検討できるような余地を、自分の心の中に持たないといけませんよね。特に自分の中で「答え」が出ちゃっているものには、注意して。それを信じすぎずに、2割くらい差し引いておいてください。